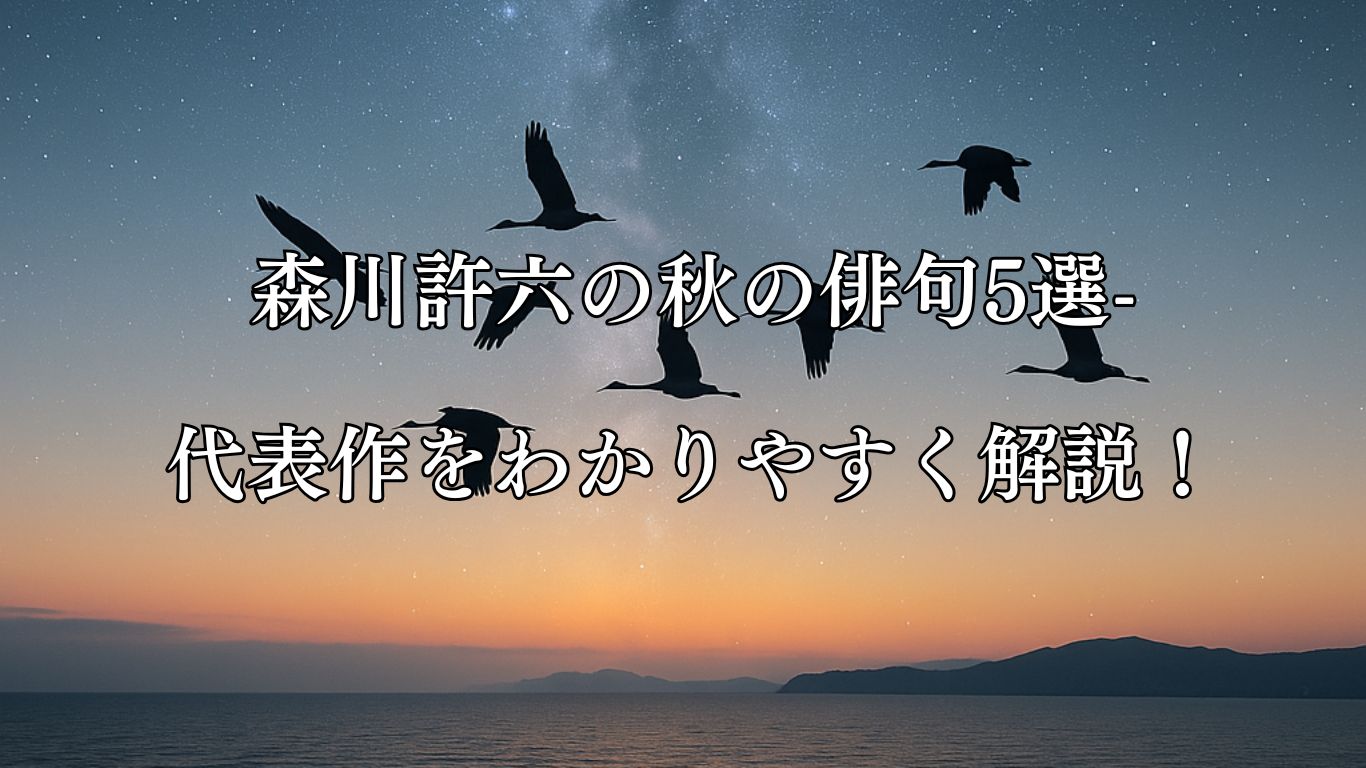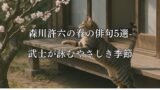森川許六の秋の俳句で、
秋の静けさを感じてみませんか?
許六の俳句は、
自然の静けさと人の心の響きを
大切にした表現が魅力です。

この記事では、秋を題材にした代表的な5句を初心者にもわかりやすく紹介します。

尾花や菊、野分や雁などを通して、秋の深まりと静かな情感を感じる許六の世界を、一緒に味わってみませんか。
▶前回の記事はこちらから!
前回は、森川許六が詠んだ夏の俳句をご紹介しました。
白牡丹や雲の峯、田植えや夏の月など、季節の生命力と旅情が交わる名句をぜひこちらからご覧ください。
森川許六の人物像を解説
芭蕉十哲-森川許六とは?
森川許六- Wikipedia(もりかわ きょりく)は、
「蕉門十哲 – Wikipedia」(しょうもんじってつ)の中でも
武士でありながら俳諧にも深く親しんだ人物
として知られています。

また画家・書家としても活動し、芭蕉の句風に理論的な視点から関わったことでも注目されています。
夏を詠んだ森川許六とは?
彼の句は、
理知的で落ち着いた語り口と、
自然の中に潜む静かな情緒が特徴です。

秋を詠んだ作品では、尾花や菊、雁などを通して、季節の移ろいと人の心の静けさを繊細に表現しました。

華やかさよりも、静けさの中にある美を大切にする姿勢が、多くの俳人に影響を与えました。
▶森川許六も学んだ師、松尾芭蕉の秋の俳句もあわせて楽しんでみませんか?芭蕉ならではの秋の情景と詩情を、わかりやすくまとめた記事はこちらからご覧いただけます。
森川許六の秋の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!
『ない袖を 振て見せたる 尾花哉』

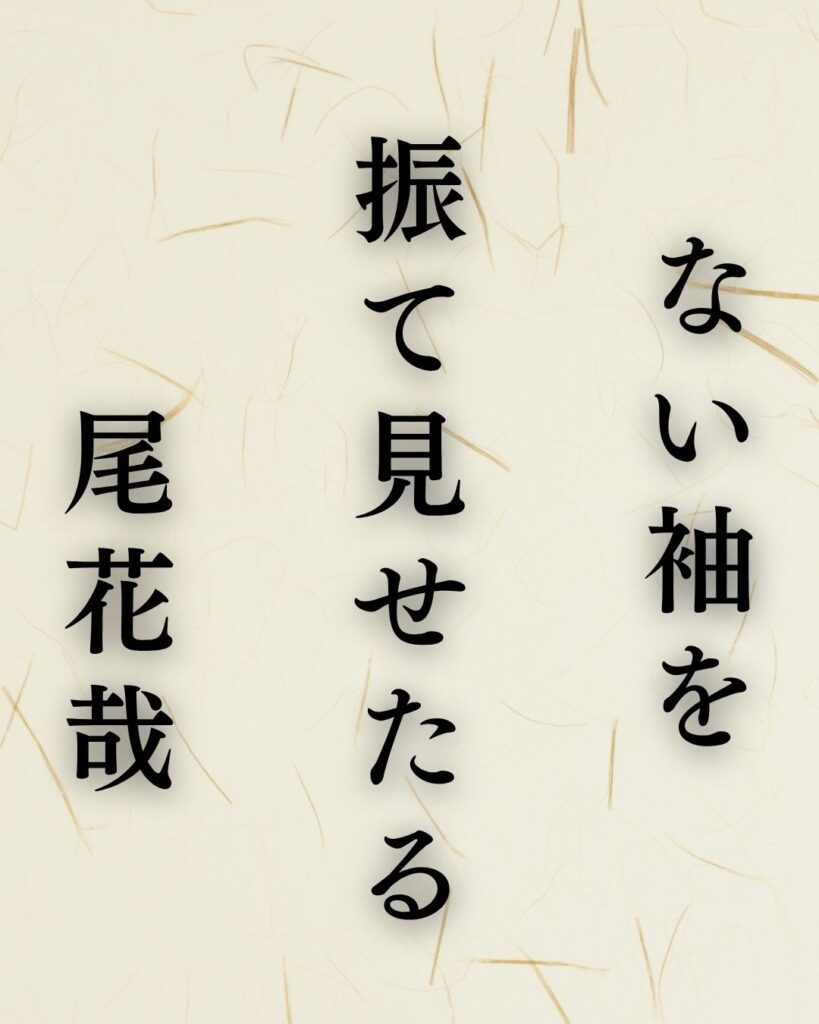
ない袖を 振て見せたる 尾花哉
読み方:ないそでを ふるてみせたる おばなかな
季語:尾花(おばな)
句意:この句では、風に揺れる尾花が袖を振るように見え、儚くも愛らしい情景が詠まれています。

つまりこの俳句は、尾花が袖を振るように見える幻想的な情景を描いています。

また、自然の動きに人の心を重ねる優しい感性がポイントです。
森川許六は、秋の草花に人の感情を映すことで、寂しさの中にも温もりを感じさせる句を多く残しました。この句もまた、秋風にそよぐ命のやわらかな美を見事に捉えています。
『のびのびて 衰ふ菊や 秋の暮』

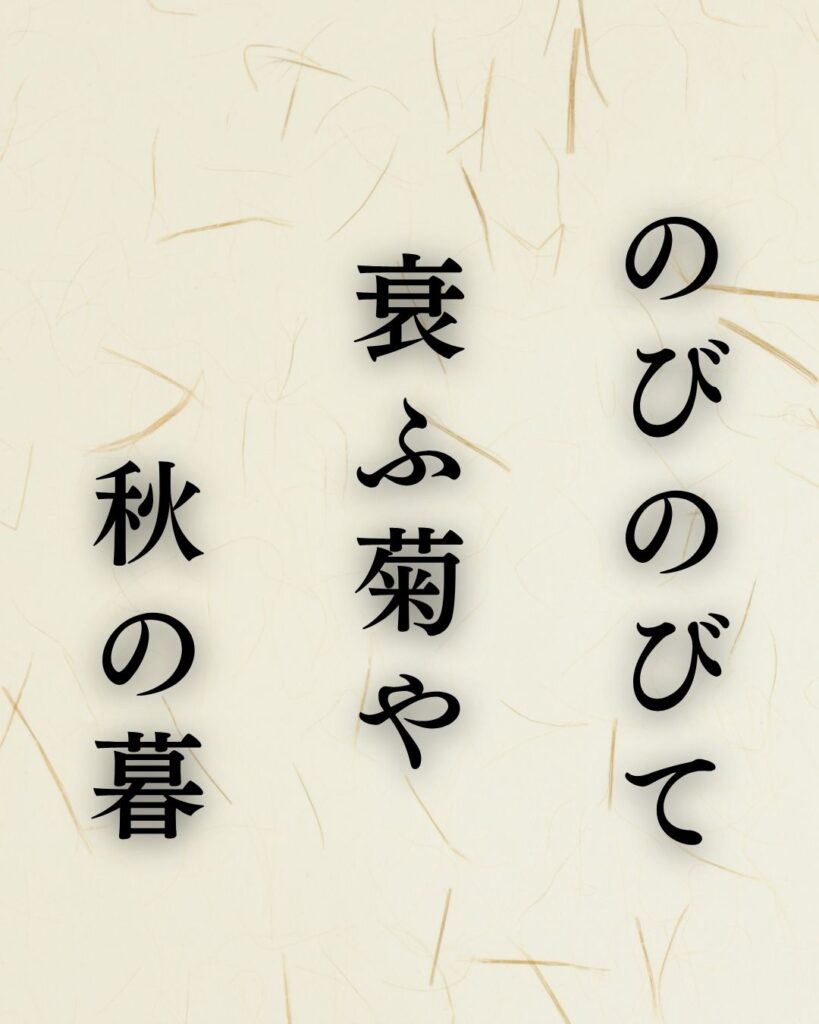
のびのびて 衰ふ菊や 秋の暮
読み方:のびのびて おとろうきくや あきのくれ
季語:秋の暮(あきのくれ)
句意:この句では、盛りを過ぎてしおれた菊に秋の暮れの寂しさを感じ取る情景が詠まれています。

つまりこの俳句は、衰えゆく菊の姿に季節の終わりを重ねた一句です。

また、老いと静寂を受け入れる落ち着いた心情がポイントです。
森川許六は、花の盛りよりもその後に宿る静かな美を見つめ、秋の夕暮れに漂う寂寥感とともに、人生のはかなさと穏やかな諦観を見事に描き出しています。
『大きなる 家ほど秋の ゆふべかな』

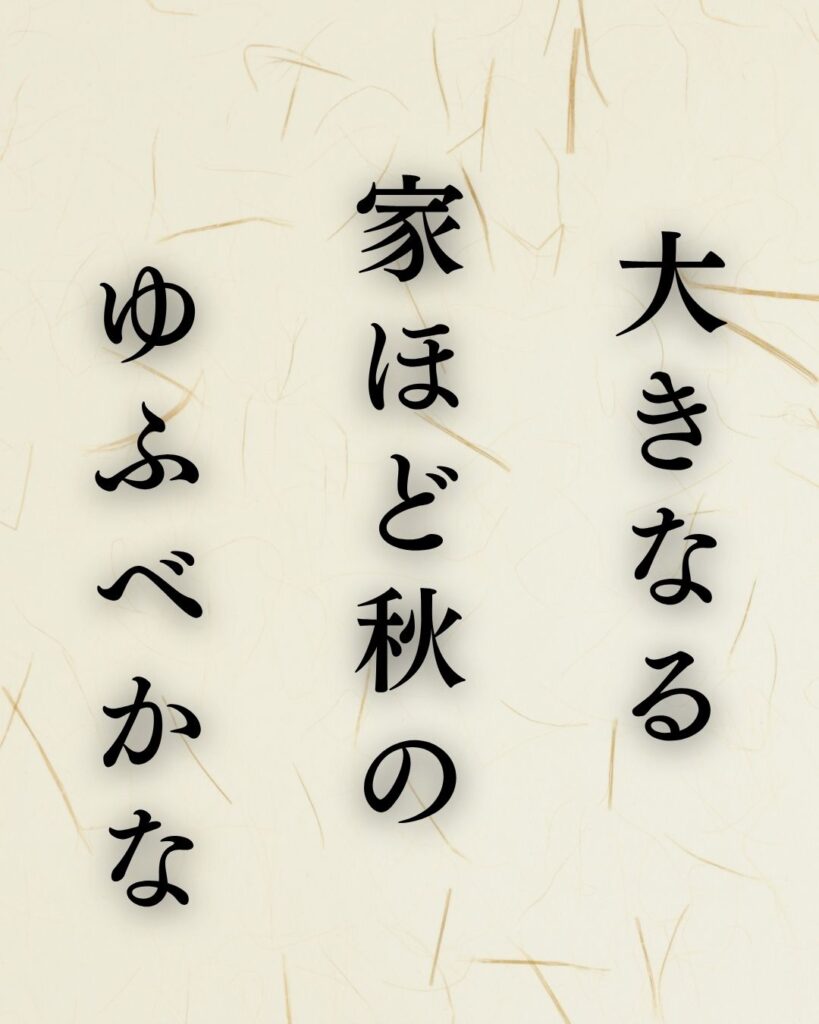
大きなる 家ほど秋の ゆふべかな
読み方:おおきなる いえほどあきの ゆうべかな
季語:秋(あき)
句意:この句では、大きな家ほど秋の夕暮れの静けさが深く感じられる情景が詠まれています。

つまりこの俳句は、大きな家と秋の夕暮れという対比を通して、静けさと寂しさを描いています。

また、空間の広さがそのまま人の心の余白として響く点がポイントです。
森川許六は、何も起こらない時間の中に、秋特有の情感と人生の深みを見出し、穏やかな孤独の美を詠み上げた一句となっています。
『一番に かがしをこかす 野分かな』

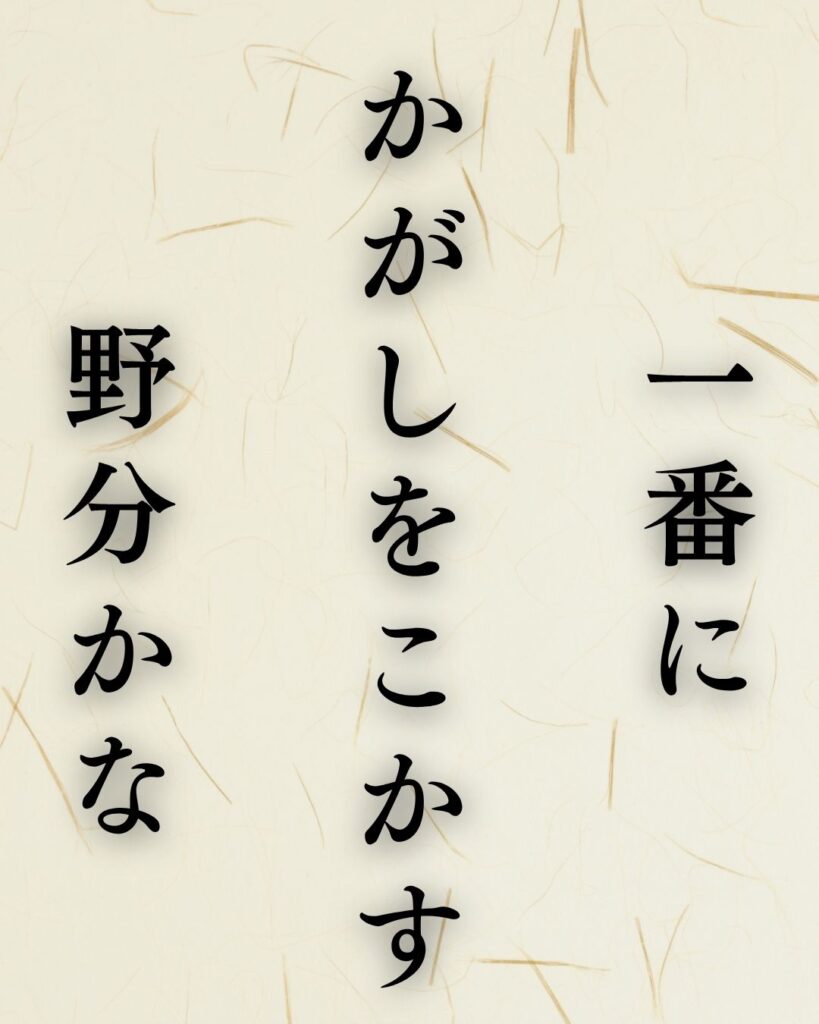
一番に かがしをこかす 野分かな
読み方:いちばんに かがしをこかす のわきかな
季語:野分(のわき)
句意:この句では、秋の野分の風が田の案山子を真っ先に倒す情景が詠まれています。

つまりこの俳句は、秋の強風が案山子を倒す瞬間を生き生きと描いています。

また、自然の力に対する人の無力さと、季節の激しさがポイントです。
許六は、風という目に見えない存在を通じて、秋の勢いと移ろいを象徴的に表現しました。そして人の手が加わったものが自然に崩される姿に、儚くも力強い季節のドラマが感じられます。
『鵲の 橋かけわたせ 佐渡の雁』

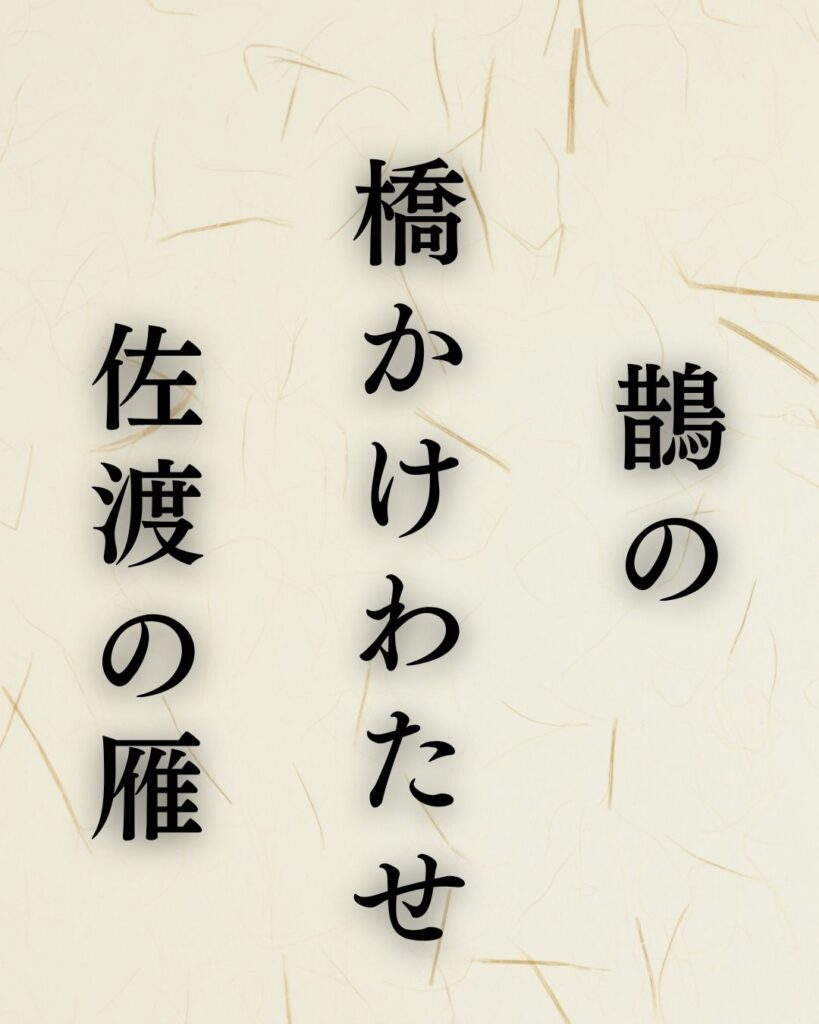
鵲の 橋かけわたせ 佐渡の雁
読み方:かささぎの はしかけわたせ さどのかり
季語:雁(かり)
句意:この句では、鵲の橋のように佐渡の空を渡る雁の姿を幻想的に詠んでいます。

つまりこの俳句は、鵲の橋と佐渡の雁を結びつけた幻想的な情景を描いています。

また、自然と伝説を重ねて詩情を生み出す構成がポイントです。
森川許六は、雁の渡りという秋の風物に、神話的な想像を織り交ぜることで、現実の風景を超えた広がりと静かなロマンを感じさせる一句に仕上げています。
森川許六の俳句ちょっとむずかしいクイズ
クイズ:「ない袖を ふるてみせたる 尾花哉」に登場する“尾花”は、どんな植物を指しているでしょう?
- 菊
- ススキ
- 萩
▶森川許六が詠んだ春の俳句では、梅や富士、花曇りなどのやわらかな情景に、武士らしい品格と静けさがにじみます。そして芭蕉の高弟として知られる許六の、凛としてやさしい春の句をぜひこちらからご覧ください。
森川許六の秋の俳句5選まとめ
森川許六は、
松尾芭蕉の高弟として活躍した俳人で、
武士らしい気品と繊細な感性を
あわせ持つ人物です。
秋の句では、
月や風、草花などの自然を通して、
静かな情緒と深い余韻を表現しています。
素朴ながらも味わい深い世界が、
初心者にもやさしく心に残ります。

この記事「森川許六の秋の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」では、許六の秋の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。
クイズの答え:2.ススキ