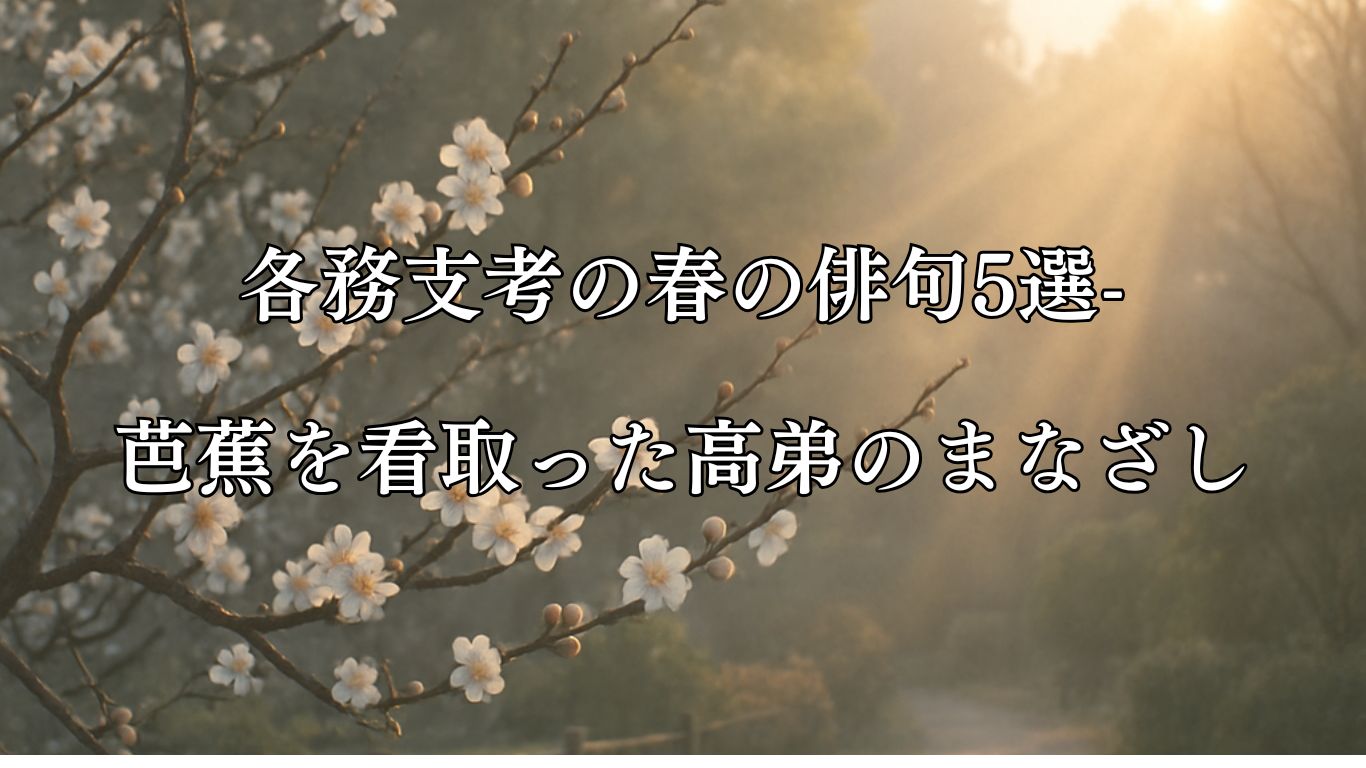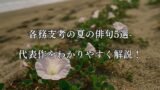各務支考の春の俳句で、
静けさの中の美しさにふれてみませんか?
芭蕉の最期を見届けた高弟・支考のまなざしは、
どこかやさしく、静かな余韻を残します。
また自然に寄り添いながら詠まれた句には、
日常の小さな感動や、移ろう季節の美しさが
さりげなく映し出されています。

本記事では、初心者でも楽しめる各務支考の春の俳句を5つ厳選してわかりやすく解説します。
各務支考の人物像を解説
芭蕉十哲-各務支考とは?
各務支考- Wikipedia(かがみ しこう)は、
「蕉門十哲 – Wikipedia」(しょうもんじってつ)の中でも
芭蕉にもっとも近しく仕えた高弟の一人とされます。

伊賀から大坂への旅にも同行し、芭蕉の臨終を看取った人物として知られ、その作品には深い敬愛と静かな感性がにじんでいます。
春を詠んだ各務支考とは?
春を詠んだ各務支考の俳句は、
華やかさよりも静けさや
余韻を大切にするのが特徴です。

自然の一瞬に目をとめ、やさしく寄り添うような視点で詠まれた句には、芭蕉譲りの感性と支考ならではの情趣がそっと息づいています。
▶各務支考も学んだ師、松尾芭蕉の春の俳句もあわせて楽しんでみませんか?
芭蕉ならではの春の情景と詩情を、わかりやすくまとめた記事はこちらからご覧いただけます。
各務支考の春の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!
『梅が香の 筋に立よる 初日哉』

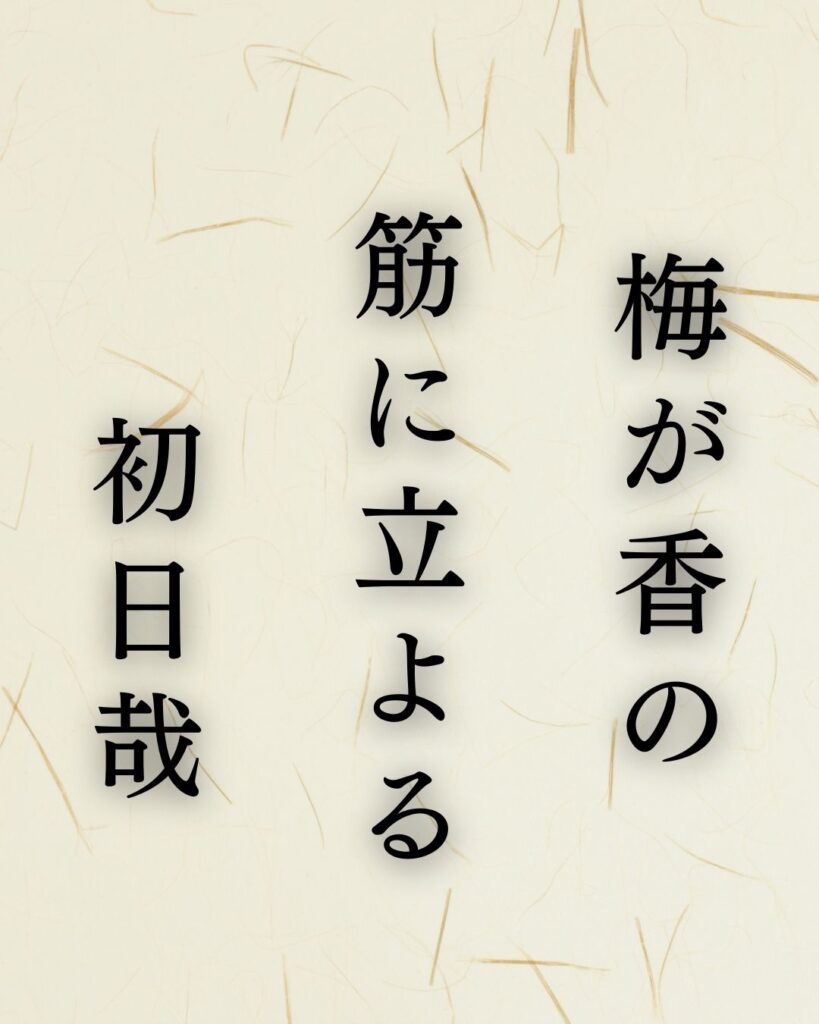
梅が香の 筋に立よる 初日哉
読み方:うめがかの すじにたちよる はつひかな
季語:初日
句意:この句では、梅の香りが流れる空間に、元日の朝日が寄り添うように差し込む様子が詠まれています。

この句は、梅の香りが風にのって流れる“筋”に、元日の朝日がすっと差し込んでくる瞬間を詠んだものです。

また「梅が香の筋」という表現が繊細で、香りに“かたち”を与える感覚が印象的です。
「立よる」という言い回しに、自然と光が寄り添ってくるような優しさがあり、そして支考らしい静かな気配と品のある美意識がにじみ出ています。
『ちりぢりに 春やぼたんの 花の上』

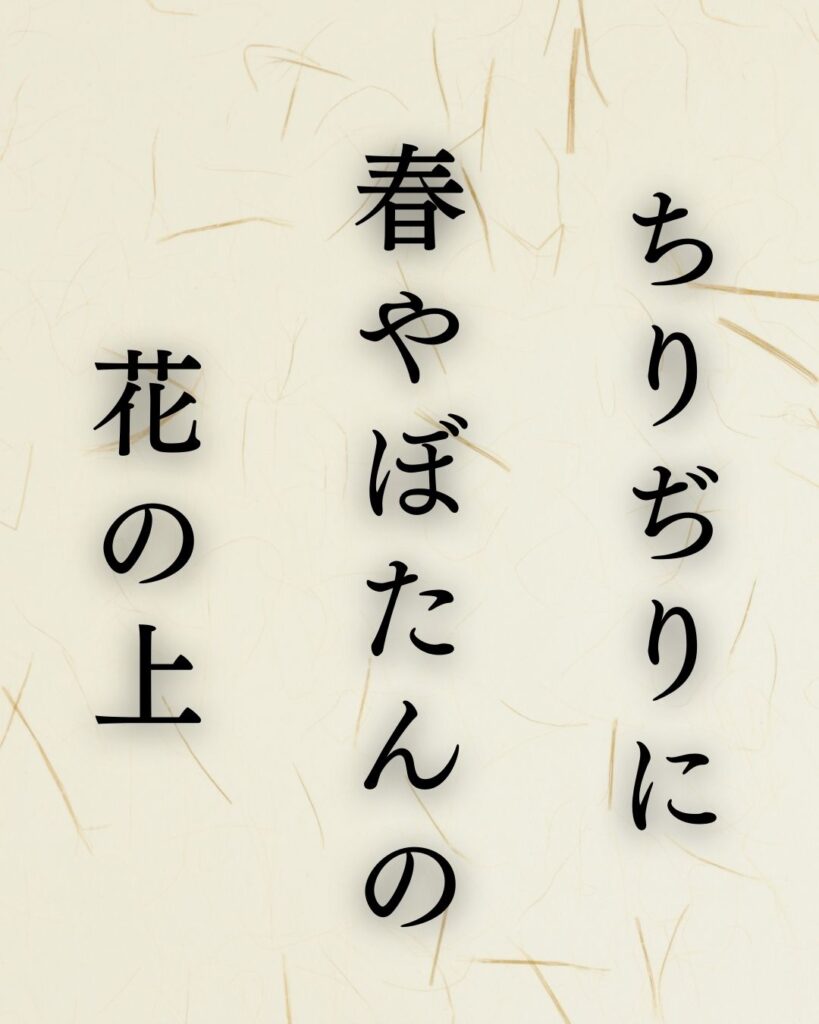
ちりぢりに 春やぼたんの 花の上
読み方:ちりぢりに はるやぼたんの はなのうえ
季語:春
句意:この句では、牡丹の花の上に、春風で花びらが「ちりぢりに」舞い散っていく様子が詠まれています。

この句は、春風に花びらが舞い散る牡丹の上に、さらに細かな花びらが「ちりぢりに」散っていく様子を描いています。

また「ちりぢりに」という言葉が、乱れながらも美しく舞う動きを印象的に捉えており、春という季節のはかなさと華やかさを重ねています。
ぼたんの豪華な花と、散る瞬間の繊細な美しさが共存する構図は、支考の美意識をよく表しています。
『ほのかなる 梅の雫や 淡路島』

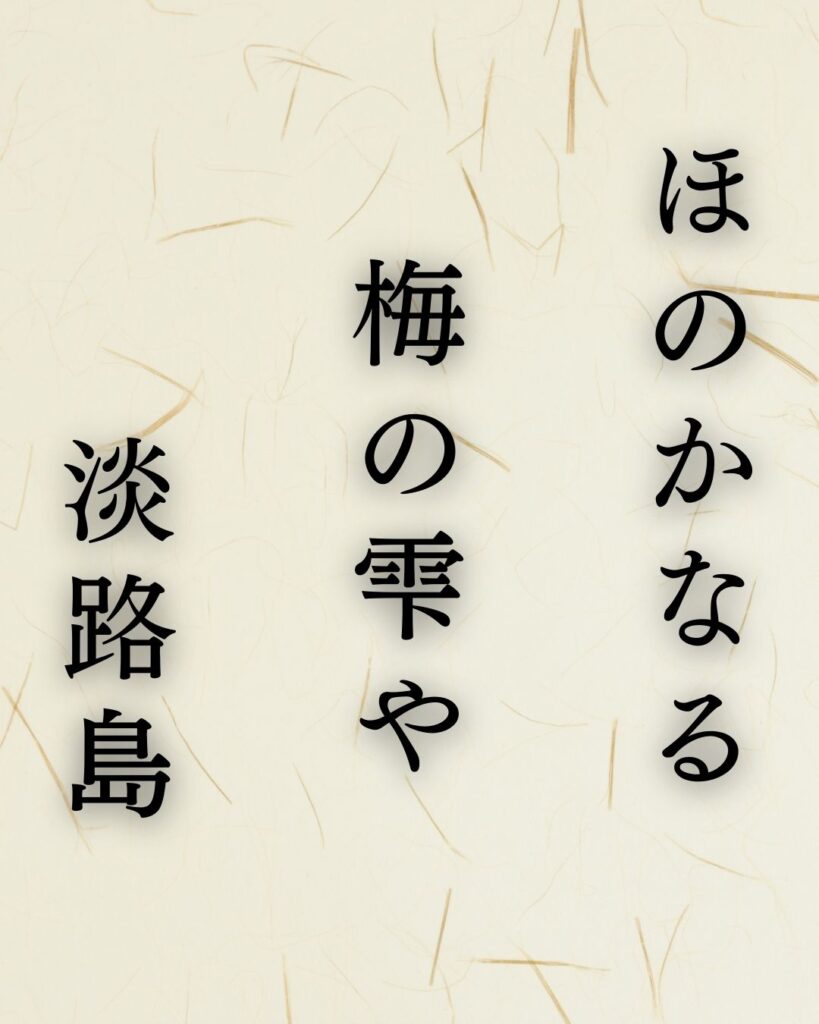
ほのかなる 梅の雫や 淡路島
読み方:ほのかなる うめのしずくや あわじしま
季語:梅
句意:この句では、淡路島に咲く梅の花に、うっすらと宿る雫の存在がやさしく詠まれています。

この句は、淡路島に咲く梅の花に、ほんのりと宿る“雫”の美しさを詠んだものです。

「ほのかなる梅の雫」という表現では、梅の香や気配が静かに漂う早春の情景を巧みにとらえており、支考の繊細な観察力と情趣の深さがうかがえます。
地名「淡路島」を置くことで、句全体に奥行きと旅情が加わり、春の訪れとともにある一瞬の美を印象づけています。
『鳥の音も 絶ず家陰の 花椿』


鳥の音も 絶ず家陰の 花椿
読み方:とりのねも たえずやかげの はなつばき
季語:花椿
句意:この句では、家の陰に咲く花椿のそばで、鳥の声が途切れることなく響いている様子が詠まれています。

この句は、人家のかげに咲く花椿と、途切れず響く鳥のさえずりを対比的に捉えた春の一景を描いています。

また「鳥の音も絶ず」という表現には、生命の気配と日常の静けさが溶け合うような穏やかさが感じられます。
「家陰の花椿」という言葉により、華やかさを控えた椿の凛とした美しさと、生活の匂いのする情景がにじみ出ており、また支考らしい品のある自然描写が際立ちます。
『明星の 東へちろり 夜の雛』

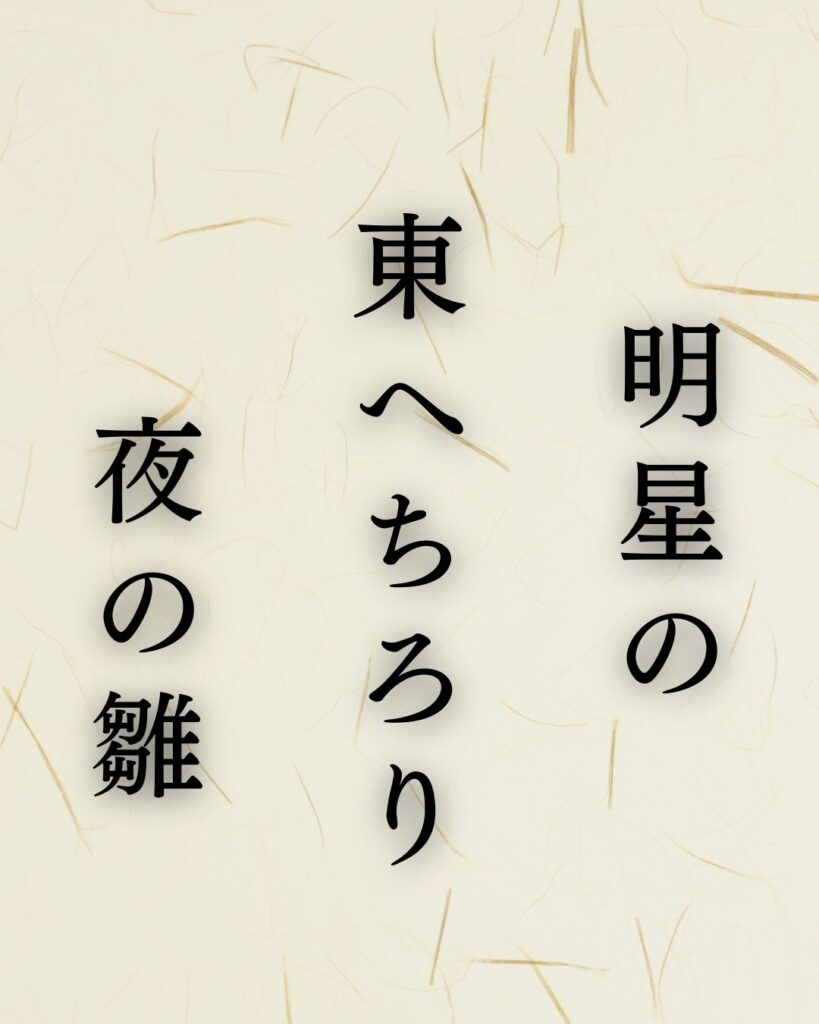
明星の 東へちろり 夜の雛
読み方:あけほしの ひがしへちろり よるのひな
季語:雛
句意:この句では、明星が東の空にかすかに輝く中、夜の雛人形が静かに飾られている様子が詠まれています。

この句は、宵の明星(金星)が東の空にかすかに輝く夜、お雛さまが静かに飾られている様子を描いた春の一句です。

また「ちろり」という柔らかな擬音により、明星のほのかな瞬きが静かな室内や闇の中に溶け込む情景を詩的に表現しています。
「夜の雛」は、明かりを落としたあとも残る余韻のような美しさを連想させ、支考の感性が光ります。また夜と春の情感が静かに溶け合う一句です。
各務支考の俳句ちょっとむずかしいクイズ
クイズ:各務支考が芭蕉とともに経験した出来事として正しいものはどれ?
- 奥の細道の旅に随行した
- 芭蕉の最期を看取った
- 芭蕉庵(ばしょうあん)を建てた
▶各務支考が詠んだ夏の俳句では、百合や昼顔、蝉の声など、暑さの中にも涼を感じる情景が広がっています。そして芭蕉の高弟として知られる支考の、写実の中にやさしさが光る夏の句をぜひこちらからご覧ください。
各務支考の春の俳句5選まとめ
芭蕉の最期を看取った高弟・各務支考の春の俳句は、
派手さこそありませんが、
読むほどに心へ静かに響きます。
また、自然や日常にそっと息づくやさしさや
余韻が浮かび上がってきます。
今回はそんな支考の句を通して、
春という季節の深い味わいにふれてみてください。

この記事「各務支考の春の俳句5選−芭蕉を看取った高弟のまなざし」では、支考の春の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。
クイズの答え:2.芭蕉の最期を看取った
※解説:支考は芭蕉の晩年に同行し、その最期まで付き添った高弟の一人です。また芭蕉の遺書の代筆も行いました。