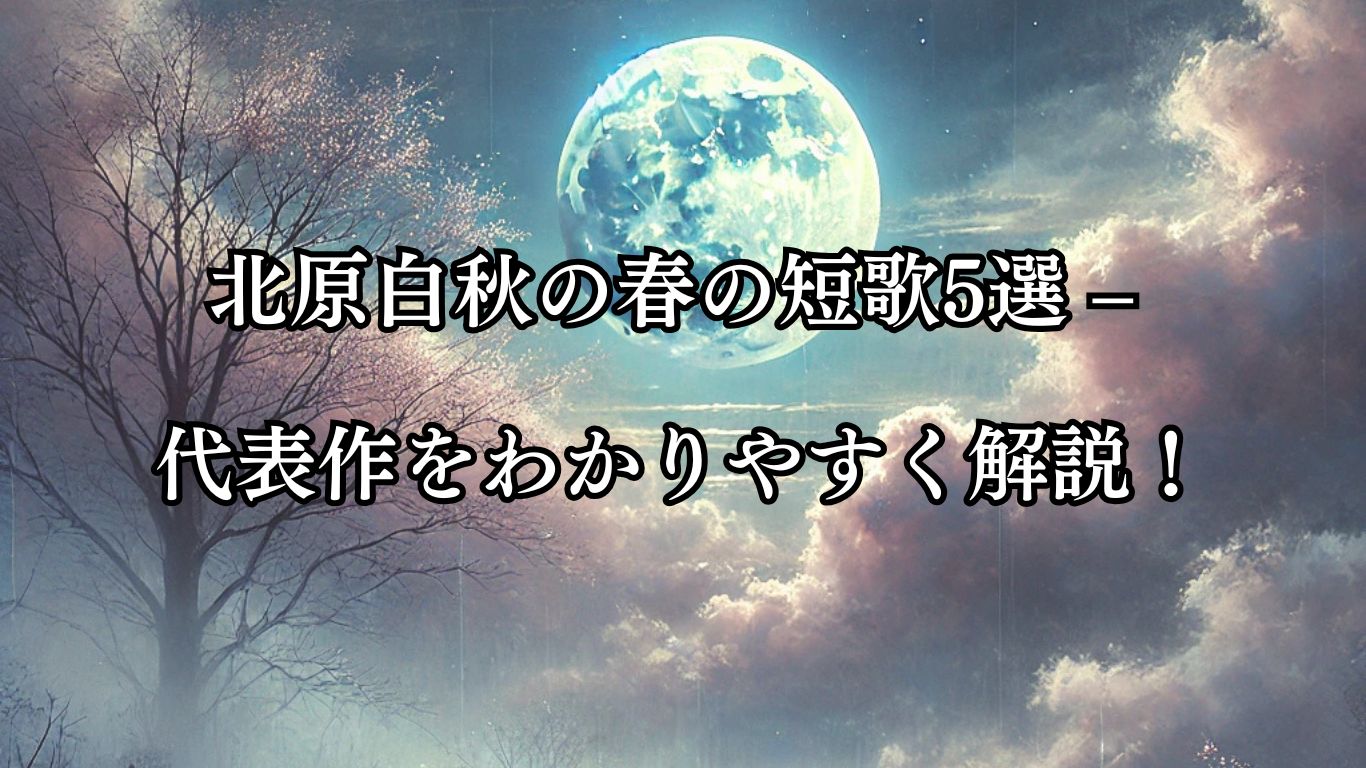北原白秋の春の短歌で
春の訪れを感じてみませんか?
北原白秋は、豊かな感性と繊細な言葉で、
春の情景を美しく詠んだ歌人です。
春の雨に濡れる花々、移りゆく季節の空、
穏やかな陽光に包まれる風景など、
白秋が描いた春の世界をイラストとともにお楽しみください。

本記事では、白秋の春を詠んだ代表的な短歌を5つ厳選し、その魅力をわかりやすく解説します。

シンプルな言葉で紡がれる短歌の世界を、ぜひ一緒に楽しんでみましょう!
▶前回の記事はこちらから!
🖌️ 北原白秋の短歌を、やさしいイラストとともに楽しめるシリーズ第1弾!
月や雨、若葉など、白秋が詠んだ鮮やかな季節の情景をシンプルに紹介しました。
短歌の世界を気軽に味わってみませんか?
春を詠んだ北原白秋とは?
北原白秋 – Wikipedia(きたはら はくしゅう)は、
日本を代表する詩人・歌人で、
美しい自然や四季の移ろいを
繊細な言葉で表現しました。
特に春の短歌では、春の雨や花々、
霞む月などを巧みに詠み、
春の情景を鮮やかに描き出しています。

また、言葉のリズムや響きを大切にし、読む人の心に深く響く作品を多く残しました。
北原白秋が言葉のリズムや色彩豊かな表現で春の情景を描いたのに対し、同級生の若山牧水は、旅の中で感じた自然の美しさを短歌に詠みました。
牧水の春の短歌には、移ろう季節の儚さや、旅人ならではの視点が感じられます。北原白秋とはまた異なる春の魅力を味わいたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。
北原白秋の春の短歌5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!
『菫咲く 春は夢殿 日おもてを 石段の目に 乾く埴土』

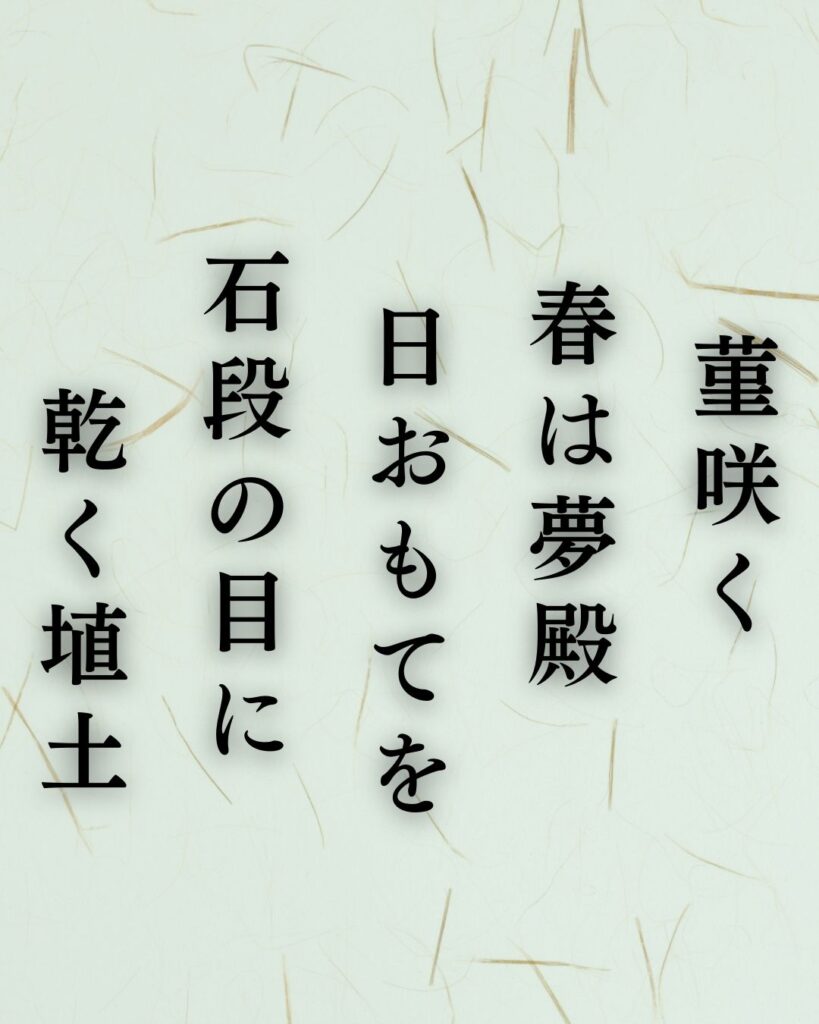
菫咲く 春は夢殿 日おもてを 石段の目に 乾く埴土
読み方:すみれさく はるはゆめどの ひおもてを いしきだのめに かわくはにつち
出典:夢殿
句意:この短歌では、春の日差しのもと、夢殿の石段には乾いた赤土が見え、そこに菫の花が咲き、静かな歴史の息吹と春の訪れを感じさせる情景を詠んでいます。

つまり「菫咲く」は春の訪れを象徴し、「夢殿」は法隆寺の八角円堂を指し、古の雅な雰囲気を醸し出しています。

また、「日おもてを」は陽の光を受けて輝く様子を表し、「石段の目に 乾く埴土」は、石段の隙間に乾いた赤土が見える情景を描写しています。
この短歌は、これらの要素が融合し、時の流れと春の穏やかな陽射しを詠んだ一首となっています。
『花ひとつ 枝にとどめぬ 玉蘭の 夏むかふなり 我も移らむ』
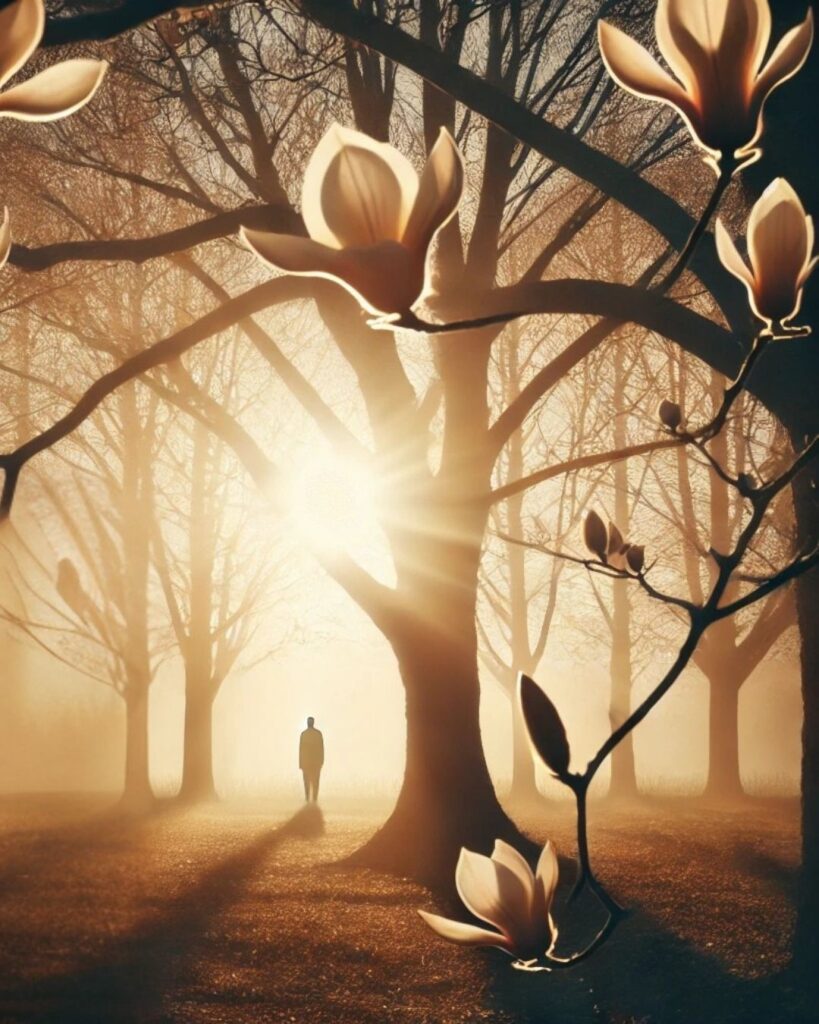
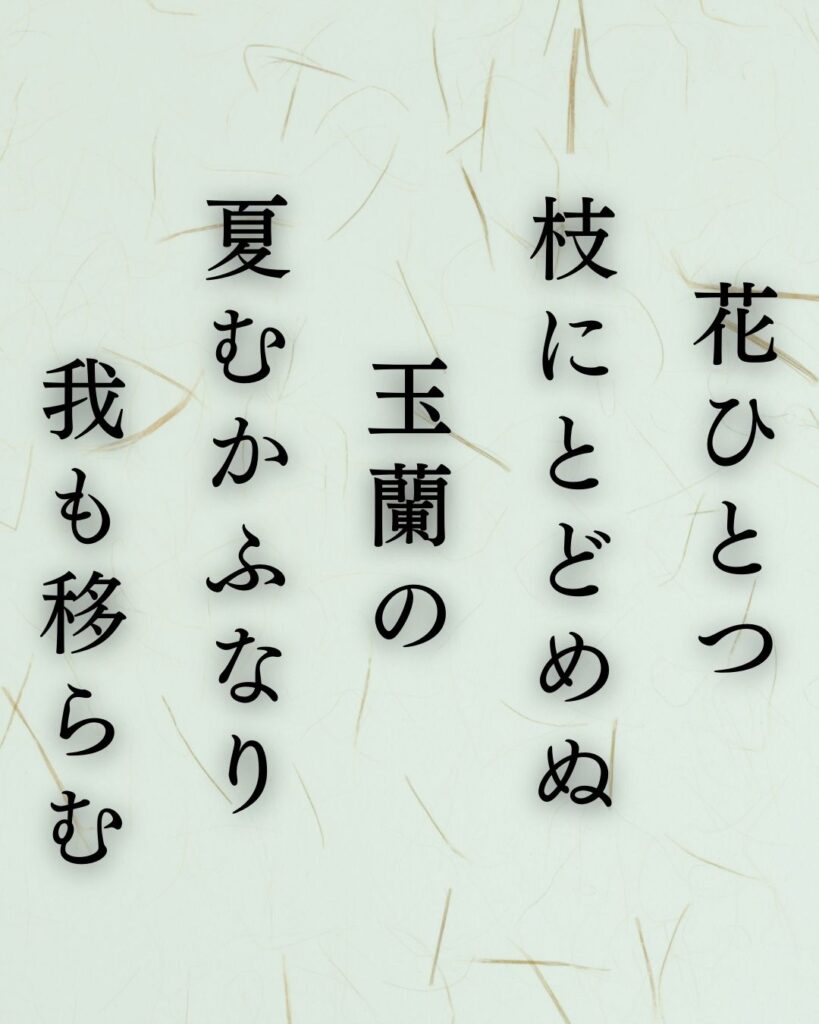
花ひとつ 枝にとどめぬ 玉蘭の 夏むかふなり 我も移らむ
読み方:はなひとつ えだにとどめぬ ぎょくらんの なつむかうなり われもうつらむ
出典:黒檜
句意:この短歌では、玉蘭の花がすべて散り、枝には一輪も残らない。季節が夏へと向かう中、自分自身もまた変わっていくのだと詠んでいます。

この短歌は、玉蘭(モクレン)の花がすべて散り、枝には一輪も残っていない様子が描かれています。

また、季節が春から夏へと移り変わることを示し、「我も移らむ」には、自らもその変化に従うという思いが込められています。
この短歌は、花の散り際を見つめながら、時の流れと共に自分自身も変わっていくという北原白秋の感受性が表現された一首です。
『春山は 杉も青みて いつしかと 鶯の声が 鶸に代りぬ』

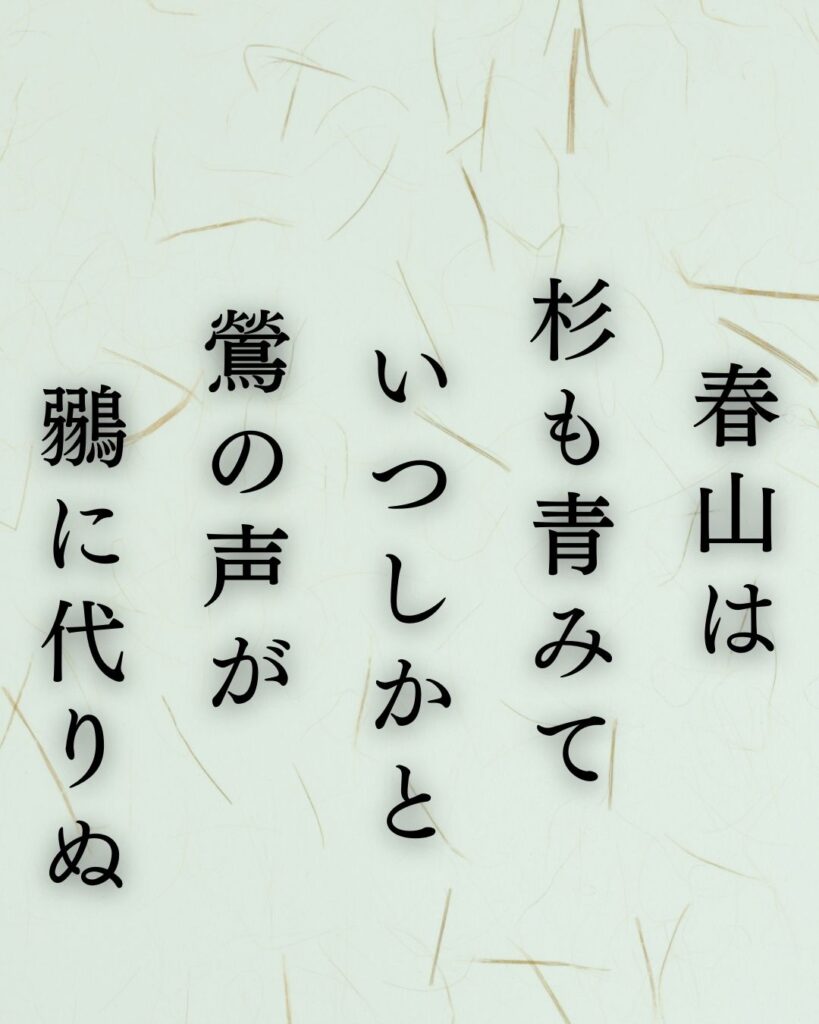
春山は 杉も青みて いつしかと 鶯の声が 鶸に代りぬ
読み方:はるやまは すぎもあおみて いつしかと うぐいすのこえが ひわにかわりぬ
出典:風隠集
句意:この短歌では、春の山は、杉の緑が濃くなり、気づかぬうちに季節が移ろう。鶯の鳴き声も、やがて鶸の声へと変わり、自然の流れを感じさせると詠んでいます。

「杉も青みて」では、春の訪れとともに木々が生き生きと色づく様子を表し、「いつしかと」には、気づかぬうちに季節が変わるという驚きが込められています。

さらに、「鶯の声が鶸に代りぬ」と続き、春を象徴する鶯の声が、やがて鶸の鳴き声へと移り変わることで、自然の流れと季節の移り変わりを繊細に表現しています。
この短歌は、春の山の移ろいが鮮やかに描かれた一首です。
『春昼の 雨ふりこぼす 薄ら雲 ややありて明る 牡丹の花びら』

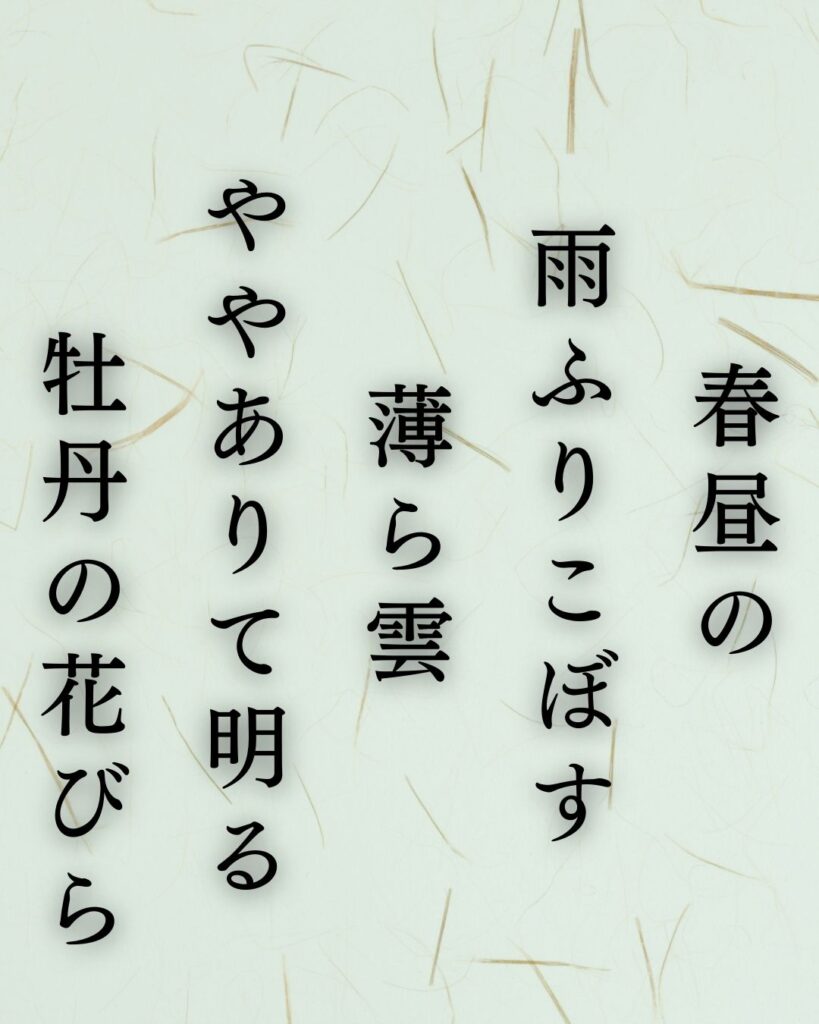
春昼の 雨ふりこぼす 薄ら雲 ややありて明る 牡丹の花びら
読み方:しゅんちゅうの あめふりこぼす うすらぐも ややありてあかる ぼたんのはなびら
出典:橡(つるばみ)
句意:この短歌では、春の昼下がり、薄雲から雨が静かに降り、やがて光が差し込む。その光に照らされ、牡丹の花びらが美しく輝く情景を詠んでいます。

「雨ふりこぼす薄ら雲」では、淡い雲から静かにこぼれ落ちる春の雨を表し、「ややありて明る」は、雨が止みかけた後、ほのかに差し込む光を示しています。

そして「牡丹の花びら」は、雨に濡れながらも、光を受けて美しく映える情景を象徴しています。
この短歌は、春の儚い移ろいと美しさが余韻を残す一首です。
『雨ふくむ 春の月夜の 薄雲は 薔薇いろなせど まだ寒く見ゆ』

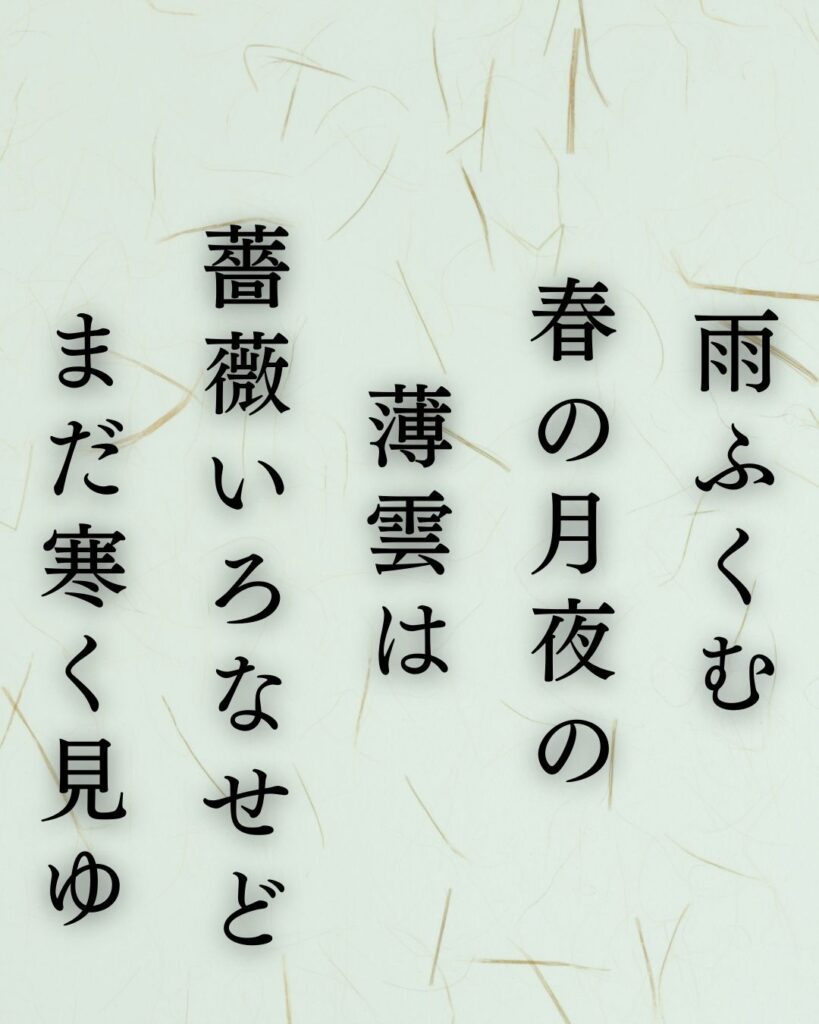
雨ふくむ 春の月夜の 薄雲は 薔薇いろなせど まだ寒く見ゆ
読み方:あめふくむ はるのつきよの うすぐもは ばらいろなせど まださむくみゆ
出典:雀の卵
句意:この短歌では、春の月夜に漂う薄雲は、月の光を受けて薔薇色に染まるが、まだ寒さが残る夜の空気が感じられると詠んでいます。

「雨ふくむ春の月夜の薄雲」では、雨を含んだ春の夜空にたなびく雲を指し、「薔薇いろなせど」は、雲が月の光を受けて淡い薔薇色に染まる様を表現しています。

しかし、「まだ寒く見ゆ」と続くことで、春とはいえ寒さが残る情景が浮かび上がります。
この短歌は、月光に照らされた雲の優美さと、春の夜の冷たさが対照的に描かれた一首です。
北原白秋の春の短歌ちょっとむずかしいクイズ
クイズ:北原白秋が最初に発表した詩集のタイトルは?
- 邪宗門
- 思ひ出
- 春と修羅

解答はまとめの最後にあります!
🌻 北原白秋が詠んだ夏の短歌には、
熱気とともに繊細な情感が息づいています。
桐の香り、燃える花々、街の光景――その言葉は鮮やかな夏を映し出します。
代表作5首をわかりやすく解説しました。
北原白秋の春の短歌5選まとめ
今回は、春の光や風、雨や花々など、
季節の移ろいを繊細に詠んだ
北原白秋の短歌を5首ご紹介しました。
すみれ咲く夢殿の情景、
春雨に輝く牡丹の花びら、
春山に響く鳥の声など、
白秋ならではの色彩豊かな表現が光ります

「北原白秋の春の短歌5選 – 代表作をわかりやすく解説!」では、初心者の方にも楽しんでいただける内容で、短歌の魅力や奥深さに触れることができます。

短歌を通じて、春の空気を感じ、詩の美しさに触れていただけたら幸いです。ぜひ、お気に入りの一首を見つけてみてください!
クイズの答え:1.邪宗門