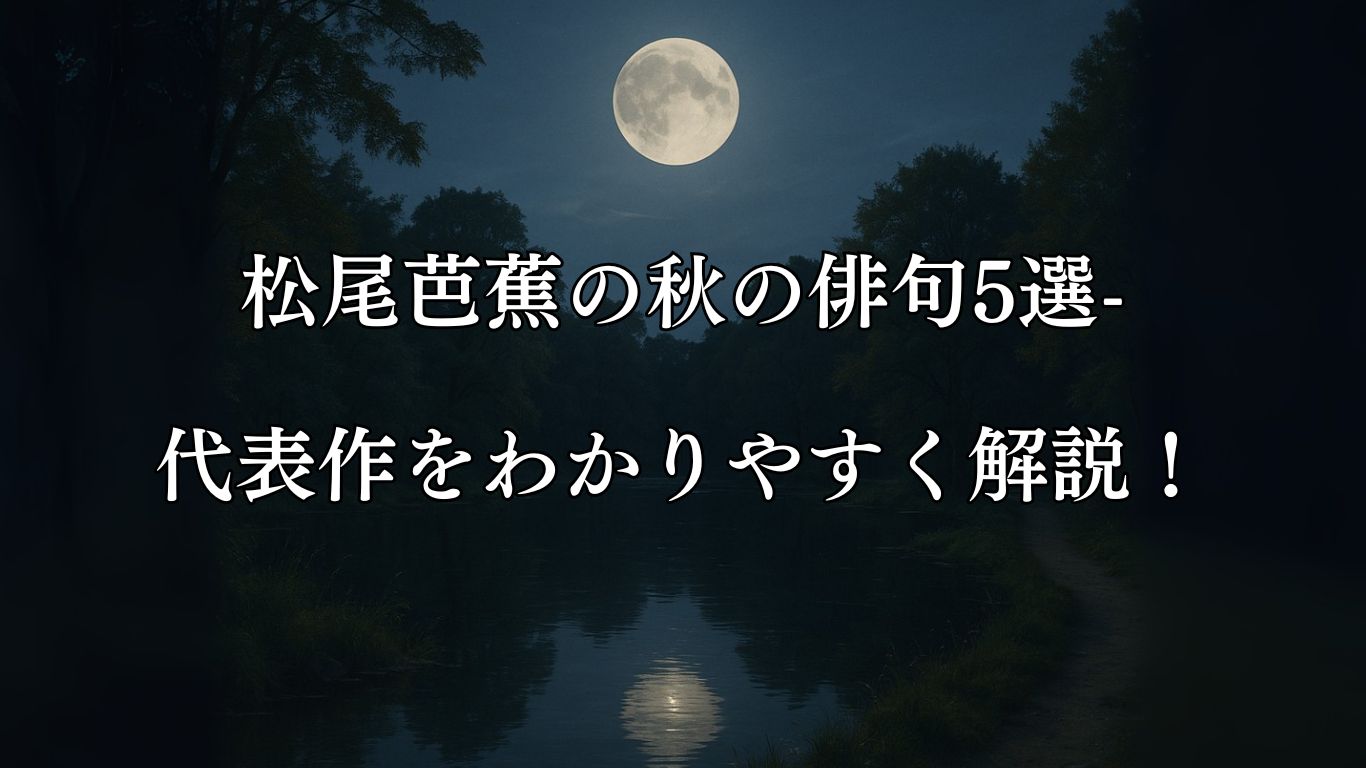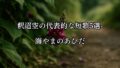松尾芭蕉の秋の俳句で、
静けさの中に浸ってみませんか?
松尾芭蕉が詠んだ秋の俳句では、
澄んだ空気や枯れゆく景色の美しさが
静かに息づいています。

本記事では、その中から選りすぐりの代表的な5句を取り上げ、背景や意味を初心者にもわかりやすく解説します。
▶前回の記事はこちらから!
さらに芭蕉の世界を味わうなら、夏の情景を描いた俳句もおすすめです。
瑞々しい季節感と旅情あふれる句を集めた「松尾芭蕉の夏の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」も、ぜひあわせてご覧ください。
秋を詠んだ松尾芭蕉とは?
松尾芭蕉 – Wikipedia(まつお ばしょう)は、
江戸時代を代表する俳人で、
「奥の細道」などの旅日記でも知られます。
また秋を詠んだ芭蕉の句は、
自然の変化と人の心の移ろいを
深く結びつけるのが特徴です。

そして紅葉や秋風、月などの景物を通し、静けさや侘び寂びの美意識を表現しました。

その作風は、季節感だけでなく人生観もにじませ、多くの人の心に響き続けています。
彼の生涯や代表作について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。また俳句の背景を知ることで、より味わい深く楽しめます。
松尾芭蕉の秋の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!
『行秋の けしにせまりて かくれけり』

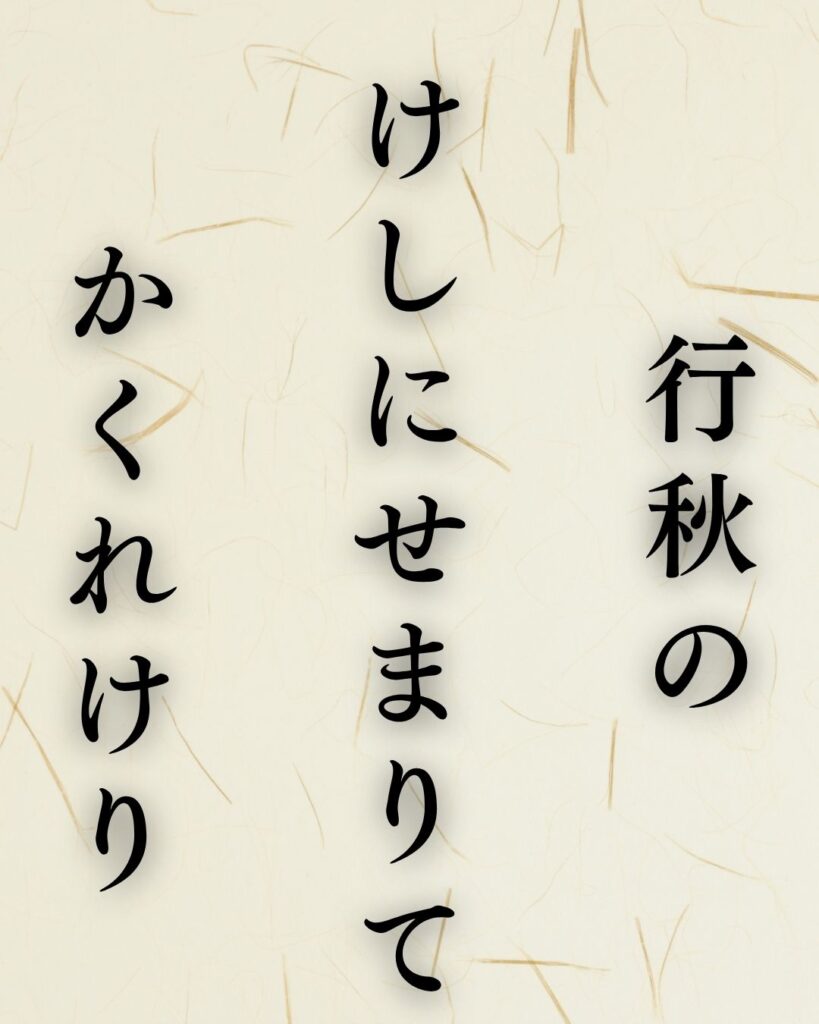
行秋の けしにせまりて かくれけり
読み方:ゆくあきの けしにせまりて かくれけり
季語:行秋(ゆくあき)
句意:この句では、秋がいつの間にか去り、まるで芥子粒の中に隠れてしまったかのように、季節が急に小さく消えてしまった感覚が詠まれています。

つまりこの句は、秋の終わりが予想以上に早く迫り、突然姿を消すような感覚を詠んでいます。

また「けし(芥子)」は極小の象徴であり、広大な秋が小さな粒に押し込められるような比喩が印象的です。
背景には「芥子に須弥山を隠す」という仏教的な発想があり、大きな季節感を極端に縮めた独特の感性が光ります。
『いなづまや かほのところが 薄の穂』

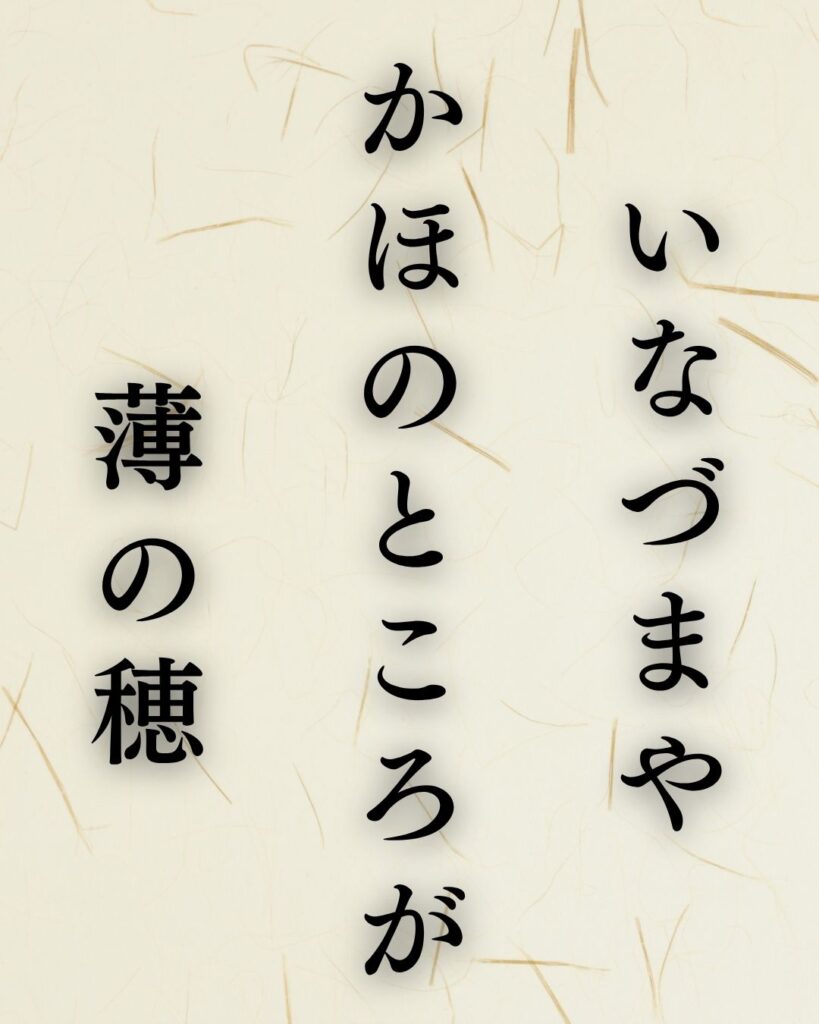
いなづまや かほのところが 薄の穂
読み方:いなづまや かほのところが すすきのほ
季語:薄(すすき)
句意:この句では、稲妻が光る中、骸骨の顔のあたりに薄の穂が重なり、死と秋の寂しさを重ねた情景が詠まれています。

つまりこの句は、稲妻の閃光と骸骨の顔、その位置に重なる薄の穂という、強烈で静かな映像を描きます。

また謡曲『通小町』の一節を踏まえ、秋の衰えと死の気配を響かせた一句です。
晩年の芭蕉の鬱屈した死生観と、自然への鋭い眼差しが融合し、そして切なさと美しさが共存する表現になっています。
『名月や 池をめぐりて 夜もすがら』

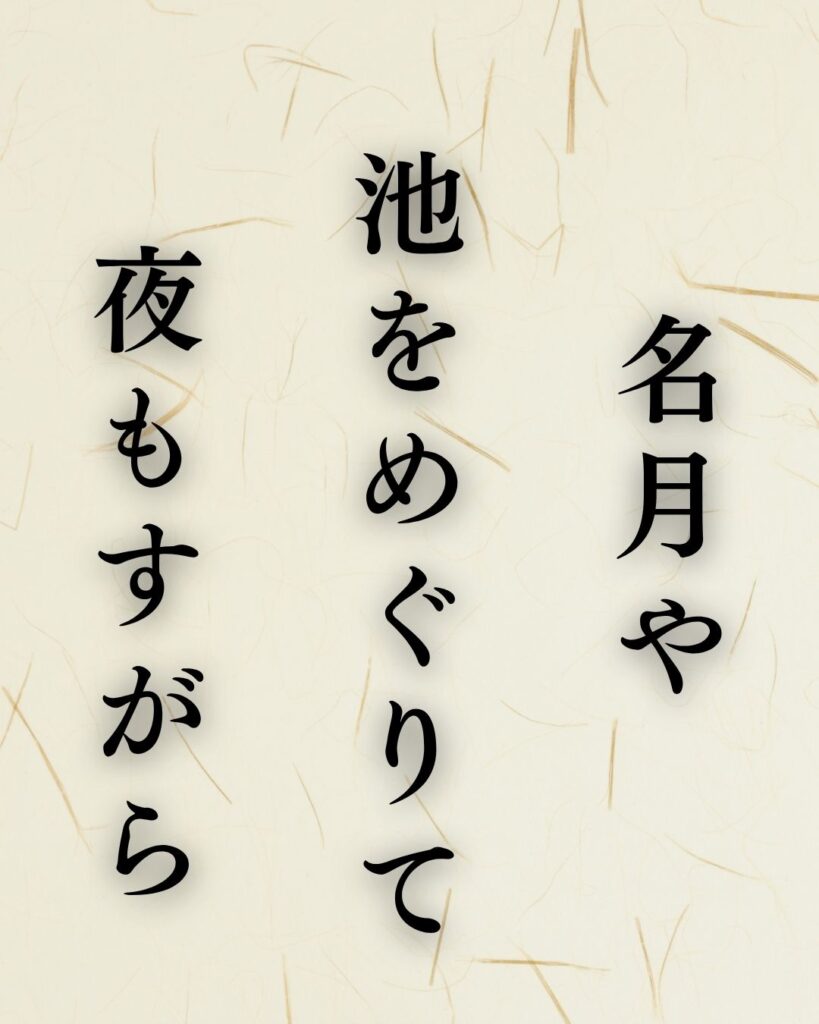
名月や 池をめぐりて 夜もすがら
読み方:めいげつや いけをめぐりて よもすがら
季語:名月(めいげつ)
句意:この句では、名月を愛でながら池のまわりを一晩中歩き、その美しさに心を奪われ続けた情景が詠まれています。

つまりこの句は、名月の美しさに魅せられ、池の周囲を一晩中歩き続ける作者の姿を描きます。

また「夜もすがら」が示すのは、月明かりの中で時を忘れるほどの没入感。池に映る月と空の月、両方を味わい尽くすような静謐で贅沢な時間が広がります。
自然と一体化した心の動きが、簡潔ながら深く響く一句です。
『七夕の 逢はぬ心や 雨中天』

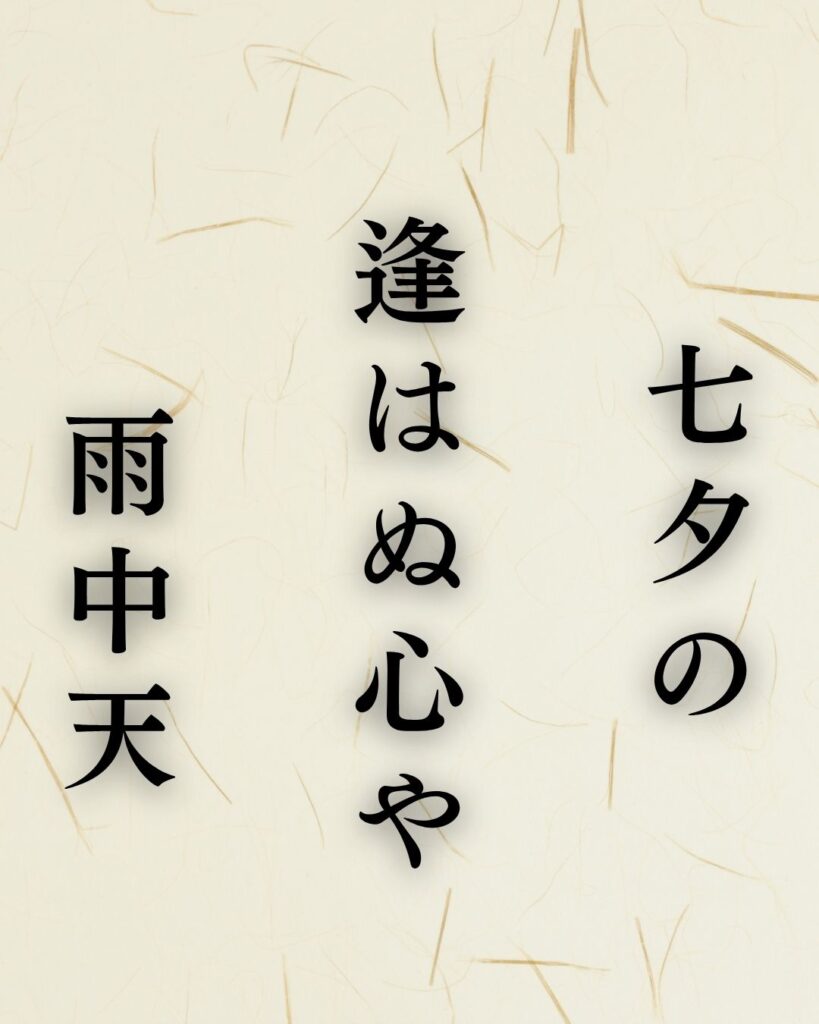
七夕の 逢はぬ心や 雨中天
読み方:たなばたの あわぬこころや うちゅうてん
季語:七夕(たなばた)
句意:この句では、雨の七夕で織姫と彦星は会えず、至福の有頂天どころか雨中天となり、残念な心情をユーモラスに詠まれています。

つまりこの句は、雨で会えない七夕の二星を、仏教語「有頂天」と造語「雨中天」に掛けて詠んだ洒落の効いた一句です。

また会えない寂しさを、ユーモアと機知で軽やかに表現しており、貞門風俳諧の遊び心が感じられます。
背景には仏教用語の深みがあり、軽妙さと教養が同居しています。
『石山の 石より白し 秋の風』

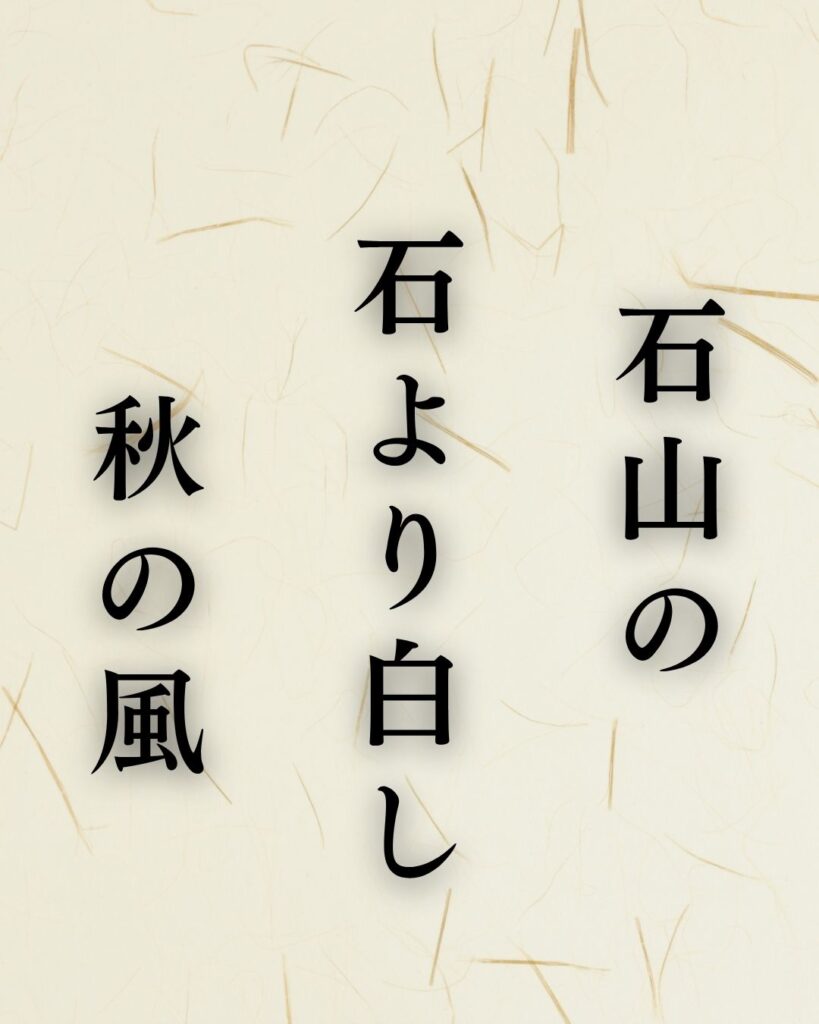
石山の 石より白し 秋の風
読み方:いしやまの いしよりしろし あきのかぜ
季語:秋の風(あきのかぜ)
句意:この句では、石山の白い岩よりも、秋の風の清らかさや冴えが際立っていることを鮮やかに詠まれています。

つまりこの句は、滋賀の石山寺の白い岩肌よりも、秋の風の清らかさが勝ると詠んだ一句です。

また視覚的な白さと、風の透明感・冷ややかさを感覚で比較することで、秋の到来を鮮やかに描き出しています。
静かな景と鋭い感性が融合し、自然の質感を五感で味わえるのが魅力です。
松尾芭蕉のちょっとむずかしいクイズ
クイズ:芭蕉の句「名月や 池をめぐりて 夜もすがら」に登場する「名月」とは、どの時期の月を指すでしょう?
- 旧暦八月十五夜の月
- 冬至の満月
- 新月直前の月
▶さらに気軽に芭蕉の秋を味わいたい方は、
「シンプルに楽しむ松尾芭蕉の秋の俳句5選」もおすすめです。
短い解説で、秋の情緒と侘び寂びの魅力をコンパクトに感じられます🍁
▶秋だけでなく、松尾芭蕉が詠んだ春の俳句もお楽しみください。
季節ごとの俳句の移り変わりを感じることで、より一層俳句の世界が広がります。
松尾芭蕉の秋の俳句5選まとめ
松尾芭蕉の秋の俳句は、
自然の変化と人の心を静かに
映し出す名句ぞろいです。

この記事「松尾芭蕉の秋の俳句5選-代表作をわかりやすく解説」では、芭蕉の秋の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。

侘び寂びの美意識と深まる秋の情緒をぜひ味わってください。
クイズの答え:1.旧暦八月十五夜の月