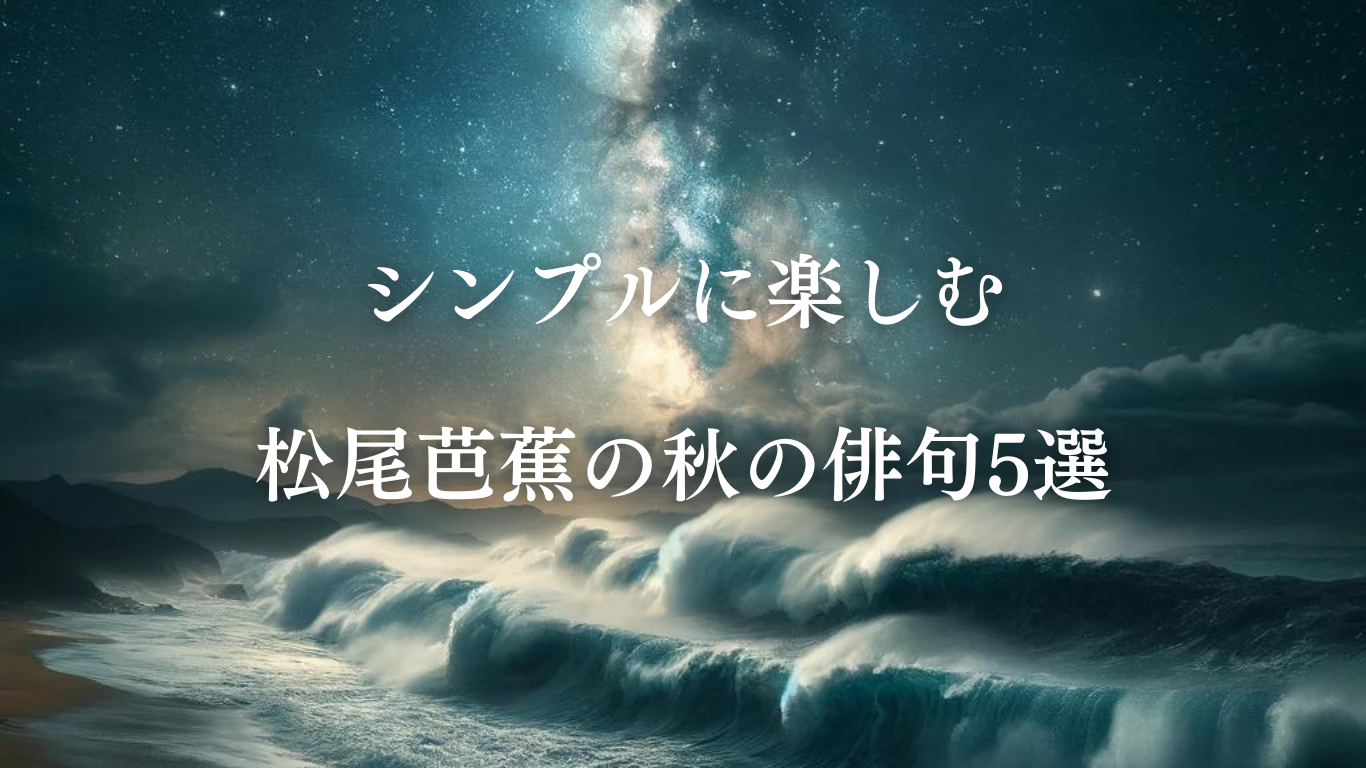シンプルに楽しむ松尾芭蕉の秋の俳句では、
季節の移ろいと心の静けさを繊細な感性と
余韻をもって巧みに表現しました。
また芭蕉の世界は難しく思われがちですが、
実は誰でも楽しめるものです。

今回は、シンプルに楽しむ松尾芭蕉の秋の俳句を5つ厳選し、その魅力を紹介します。

自然の美しさや深い感慨が短い言葉の中に凝縮されたこれらの句を通して、秋のひとときをより豊かに感じてみてください。
▶前回の記事はこちらから!
松尾芭蕉の代表句「古池や 蛙飛び込む 水の音」を例に、俳句の魅力と基礎知識をやさしく解説しています。
俳句の世界への第一歩として、ぜひご覧ください。
松尾芭蕉とは?
松尾芭蕉 – Wikipedia(まつお ばしょう)は、
秋の深まりとともに感じる侘び寂びを巧みに詠みました。
また旅の途中で出会う木々の紅葉や澄んだ夜空、
静寂の中に漂う寂しさを表現し、
そして自然の美しさと人生の無常を重ね合わせています。

彼の秋の句には、季節の移ろいを感じながら深い余韻を楽しめる魅力があります。
彼の生涯や代表作について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。また俳句の背景を知ることで、より味わい深く楽しめます。
松尾芭蕉の秋の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!
送られつ 送りつ果ては 木曽の秋

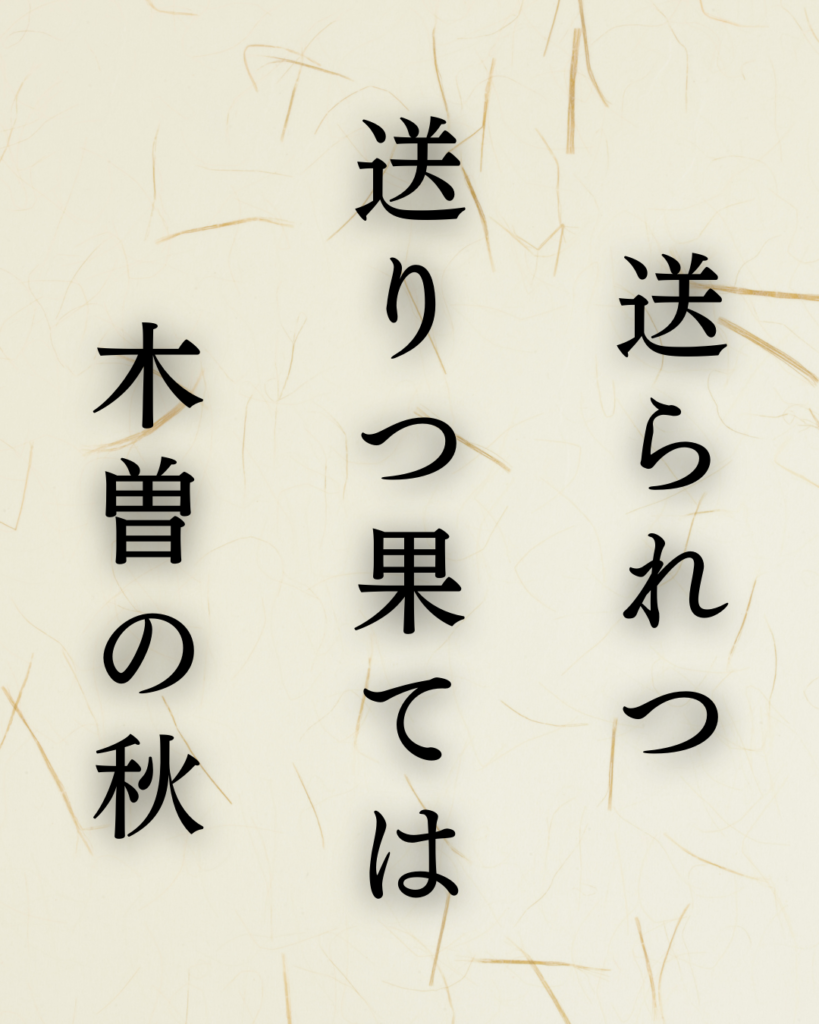
送られつ 送りつ果ては 木曽の秋
読み:おくられつ おくりつはては きそのあき
季語:秋
意味:この句では、送られたり送ったりして別れを重ねながら、木曽路にたどり着いたと詠まれています。

最終的に彼が感じたのは、深まる「木曽の秋」の静けさと寂しさです。

旅の出会いと別れの繰り返しが、秋のもの寂しい情景と重なり、そして季節の移ろいと人生の儚さを表現しています。
荒海や 佐渡に横たふ 天の川

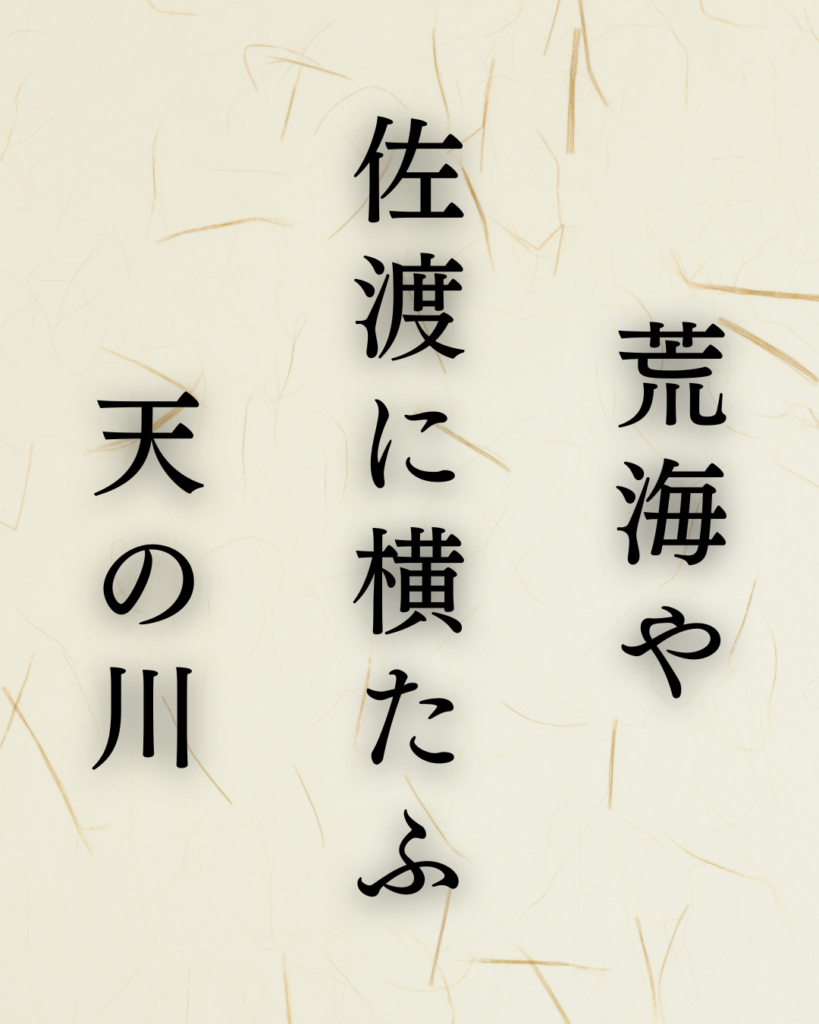
荒海や 佐渡に横たふ 天の川
読み:あらうみや さどによこたふ あまのかわ
季語:天の川
意味:この句では、荒々しい海の上に、佐渡島を横切るように天の川が広がっていると詠まれています。

つまりこの句は、佐渡と本土を隔てる荒海と天の川が簡単には渡れない様相を描いてます。

また七夕の夜、二星が合う天の川に寄せる流人たちの思いと、そして長旅をしてきた作者自身の思いが重なる深い句です。
蓑虫の 音を聞きに来よ 草の庵

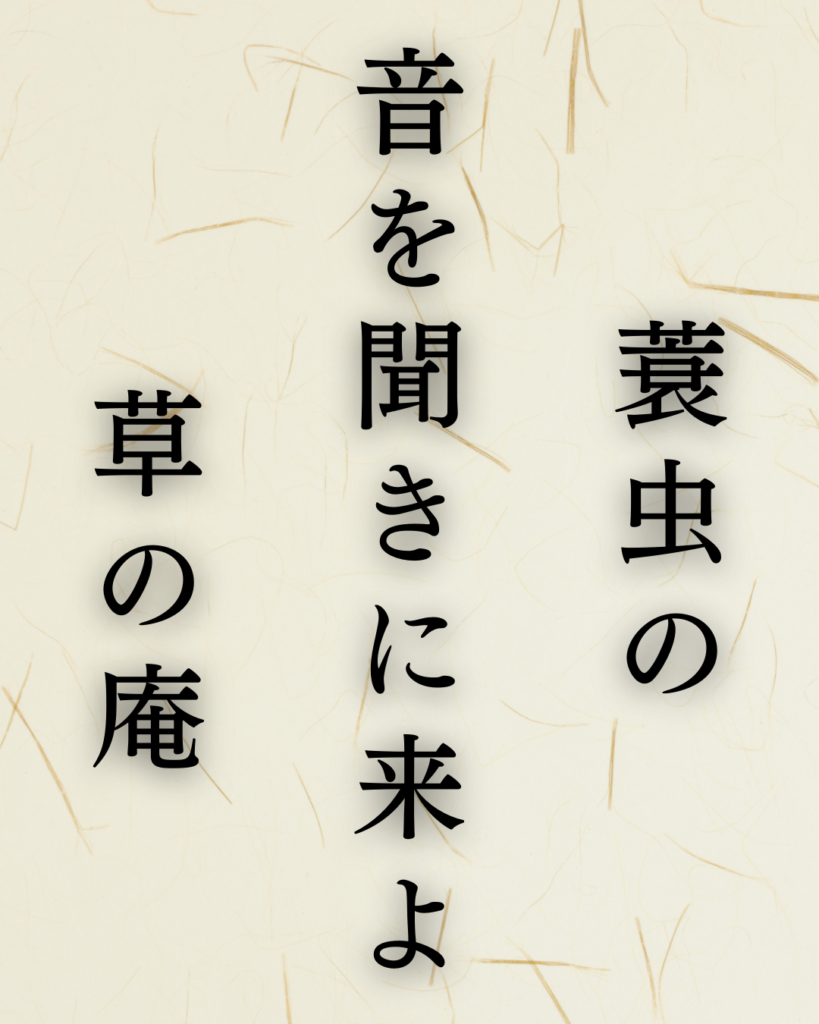
蓑虫の 音を聞きに来よ 草の庵
読み:みのむしの ねをききにこよ くさのいほ
季語:蓑虫
意味:この句では、草の庵に招き、蓑虫のかそけき声を共に聞こうと詠まれています。

つまりこの句は、草庵に住む作者が、秋の静けさの中で、蓑虫が奏でる小さな音を聞きに来てほしいと、誰かを招いている情景を表現しています。
白菊の 目に立てて見る 塵もなし

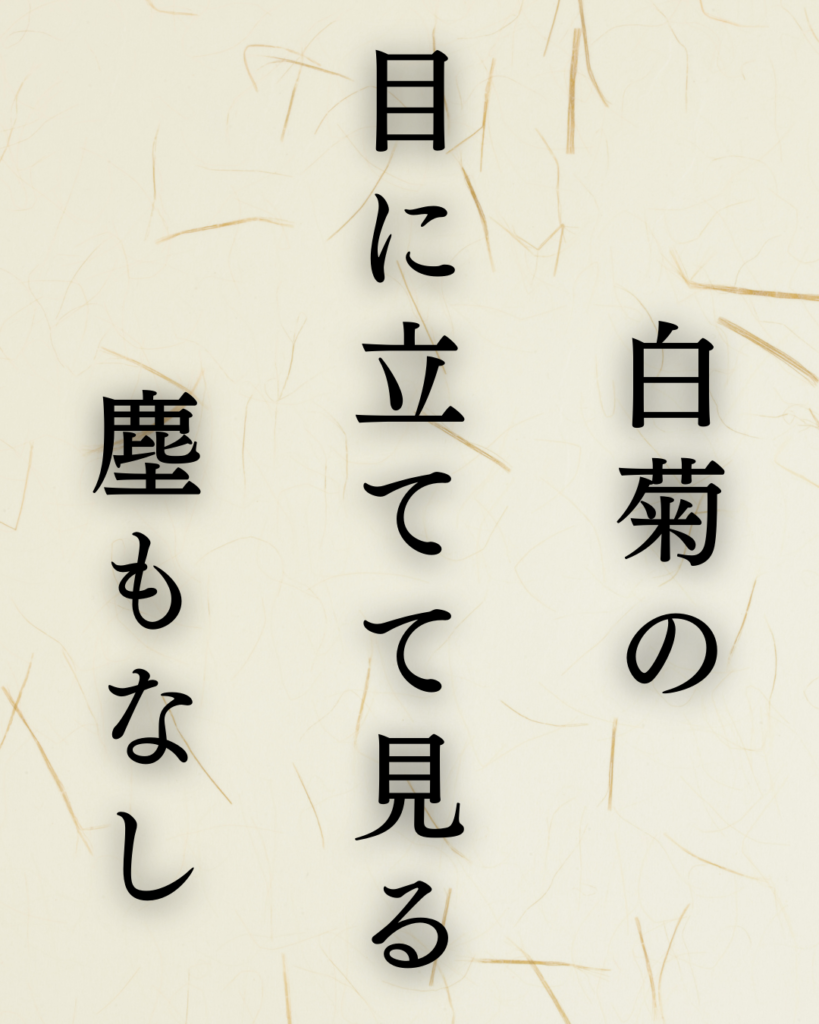
白菊の 目に立てて見る 塵もなし
読み:しらぎくの めにたててみる ちりもなし
季語:白菊
意味:この句では、白菊を目の前に見つめると、どんな小さな塵さえも見当たらない清らかさがあると詠まれています。

つまりこの句は、菊の花の白さが際立ち、特に何の汚れも感じられないほどの美しさがあることを「塵もなし」と強調しています。
蔦の葉は 昔めきたる 紅葉かな

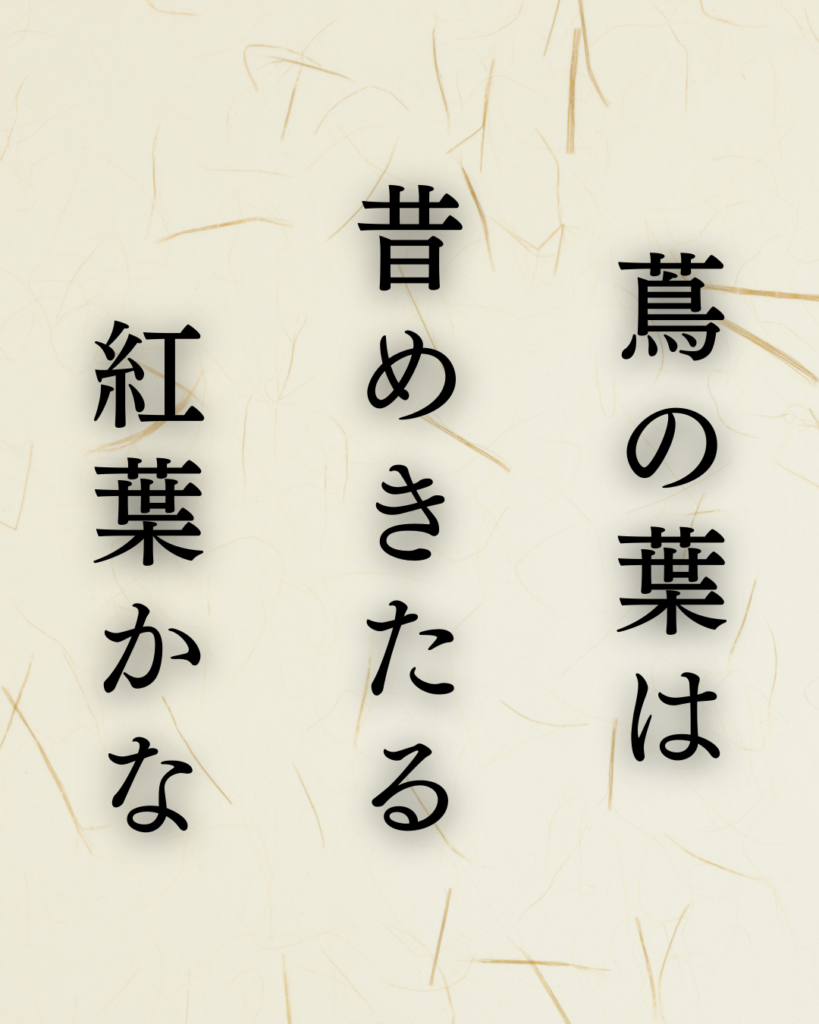
蔦の葉は 昔めきたる 紅葉かな
読み:つたのはは むかしめきたる もみじかな
季語:紅葉
意味:この句では、紅葉した蔦の葉は、どこか古風で昔を思わせる趣があり、秋の風情が漂っていると詠まれています。

つまりこの句は、紅葉した蔦の葉が、古風で懐かしい趣を感じさせる情景を表しています。

秋の深まりとともに色づいた蔦の葉は、ただ美しいだけでなく、どこか古めかしい風情を漂わせ、過去の記憶や昔の風景を思い起こさせます。
松尾芭蕉の秋の俳句ちょっとむずかしいクイズ
クイズ:松尾芭蕉の「奥の細道」は全長何キロでしょう?
- 約600キロ
- 約1200キロ
- 約2400キロ
▶秋だけでなく、松尾芭蕉が詠んだ冬の俳句もお楽しみください。また代表作を深く掘り下げた松尾芭蕉の名句『五月雨を』に迫る!の記事もおすすめです。
👉松尾芭蕉の名句「五月雨を」に迫る!代表作や人物像を徹底解説!
松尾芭蕉の秋の俳句まとめ
松尾芭蕉の秋の俳句では、
自然の美しさや季節の移ろいを
シンプルな言葉で表現しています。
また紹介した5つの句は、
秋の風景とともに静けさや
心の豊かさを感じさせるものです。

秋のひとときに、芭蕉の句を味わいながら心の安らぎを感じてみてください。
クイズの答え:3.約2400キロ