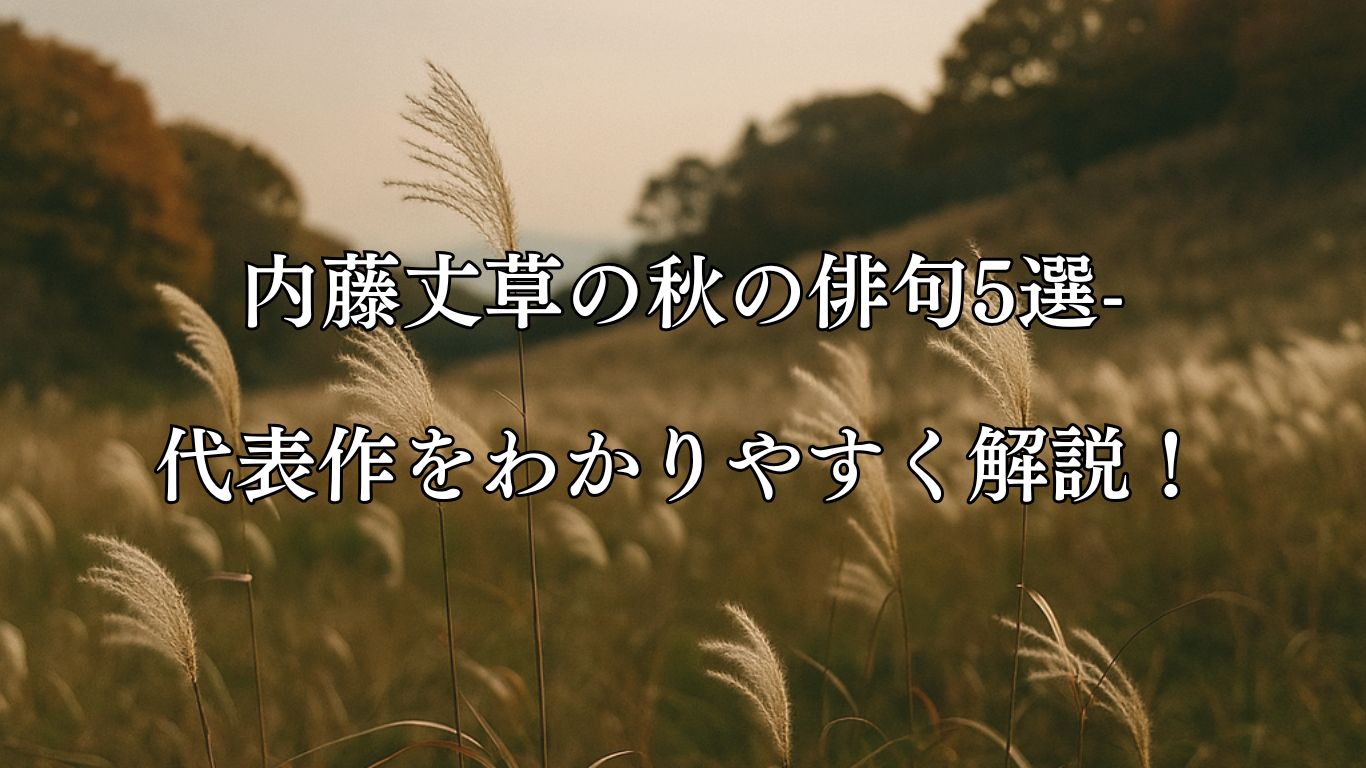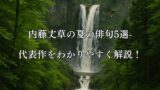内藤丈草の秋の俳句で
秋の訪れを感じてみませんか?
内藤丈草は、
松尾芭蕉の高弟として知られる俳人で、
特に身近な生活や自然の変化を
繊細に詠みました。

本記事では、秋を題材にした代表作5選をわかりやすく解説。

また初心者でも楽しめるように、句の情景や魅力をやさしく紹介します。
▶前回の記事はこちらから!
夏を題材にした丈草の句も、身近な情景と自然の移ろいが生き生きと描かれています。そして「内藤丈草の夏の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」もあわせてご覧いただき、四季を通して丈草の魅力を味わってみてください。
内藤丈草の人物像を解説
芭蕉十哲-内藤丈草とは?
内藤丈草 – Wikipedia(ないとう じょうそう)は、
「蕉門十哲 – Wikipedia」(しょうもんじってつ)の中でも
世俗を離れた静かな暮らしを好み、
精神性の高い俳句を詠んだことで評価されています。

そして芭蕉の教えを受けながらも、独自の静謐な作風を貫いた孤高の俳人です。
▶ 芭蕉を支えた高弟たち「蕉門十哲」の俳句もあわせて楽しみませんか?
それぞれが芭蕉とは違う個性を持ちながら、また俳諧の魅力を広げていった名俳人たちの句をまとめています。
秋を詠んだ内藤丈草とは?
彼の俳句は、
日常生活や自然の小さな変化を
丁寧にとらえる表現に優れ、
また素朴で親しみやすいのが特徴です。
秋を詠んだ句では、
吊柿やすすき、送り火や秋の蝉などを題材に、
季節の移ろいと人の心の機微を
重ね合わせています。

丈草の俳句では、静かな中に余情が漂う表現が魅力で、初心者でもわかりやすく、秋の風情を身近に感じられる作品が多く残されています。
内藤丈草の俳句の背景には、師である松尾芭蕉の影響が色濃く表れています。
松尾芭蕉の人物像についてはこちらの記事をご覧ください。
内藤丈草の秋の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!
『釣柿や 障子にくるふ 夕日影』

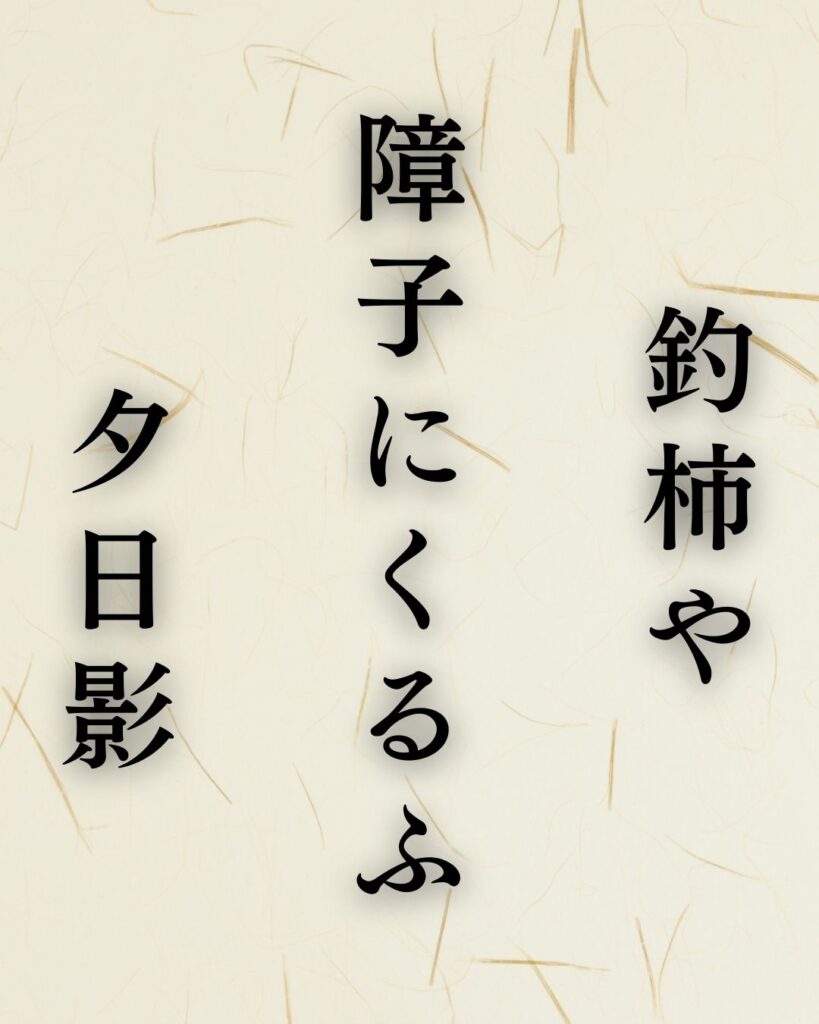
釣柿や 障子にくるふ 夕日影
読み方:つりがきや しょうじにくるう ゆうひかげ
季語:吊柿(つりがき)
句意:この句では、吊るされた柿と障子に揺れる夕日の影が重なり、秋の暮れの静かな趣が詠まれています。

つまりこの俳句は、家先に下がる吊柿の姿と、障子に映る夕日の揺らめきを描いています。

また素朴な生活の情景に、秋の暮れ特有の寂しさと温もりが漂うのが特徴です。
丈草は、何気ない日常を通して、光と影が織りなす秋の余情を巧みに表現しました。
『送り火の 山へのぼるや 家の数』

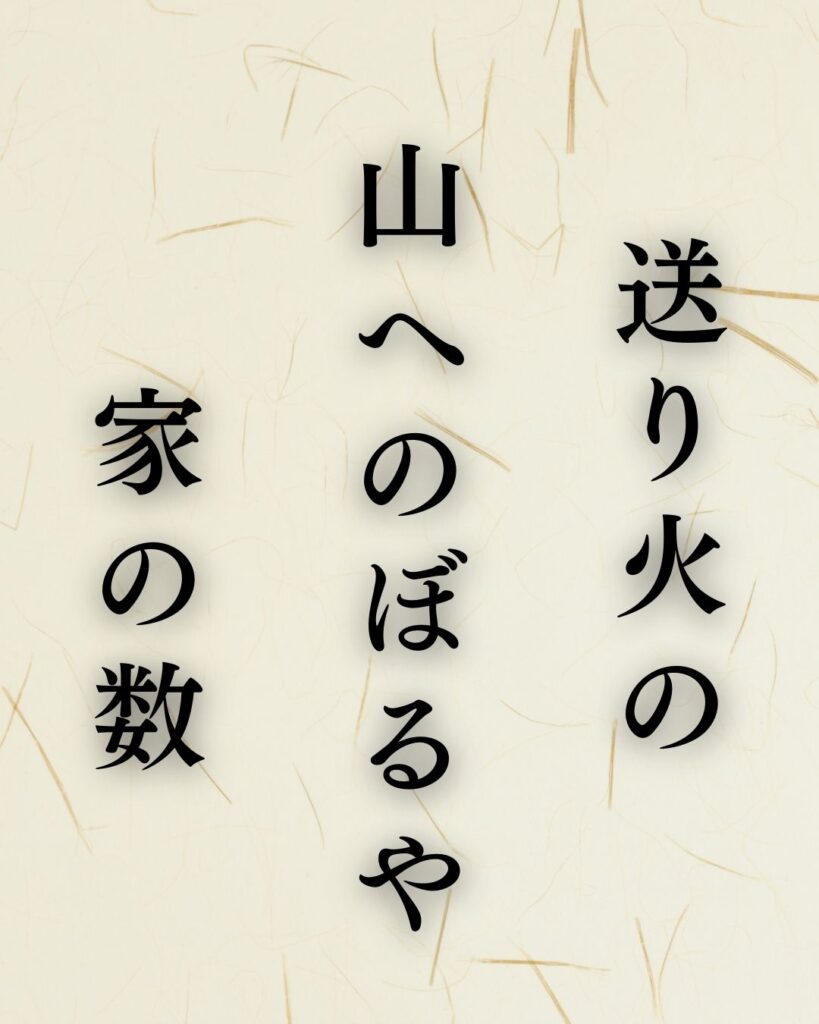
送り火の 山へのぼるや 家の数
読み方:おくりびの やまへのぼるや いえのかず
季語:送り火(おくりび)
句意:この句では、山へと登っていく送り火の明かりが、家々の数だけ灯る情景として詠まれています。

つまりこの俳句は、盆の終わりに焚かれる送り火が、山へと昇っていく様子を描いています。

また家々の数だけ灯る火が並ぶことで、人々の祈りや故人を送る心が一体となるのが印象的です。
丈草は、身近な行事の光景を通して、共同体の絆と秋の夕暮れの余情を鮮やかに表現しました。
『行秋の 四五日弱る すすき哉』

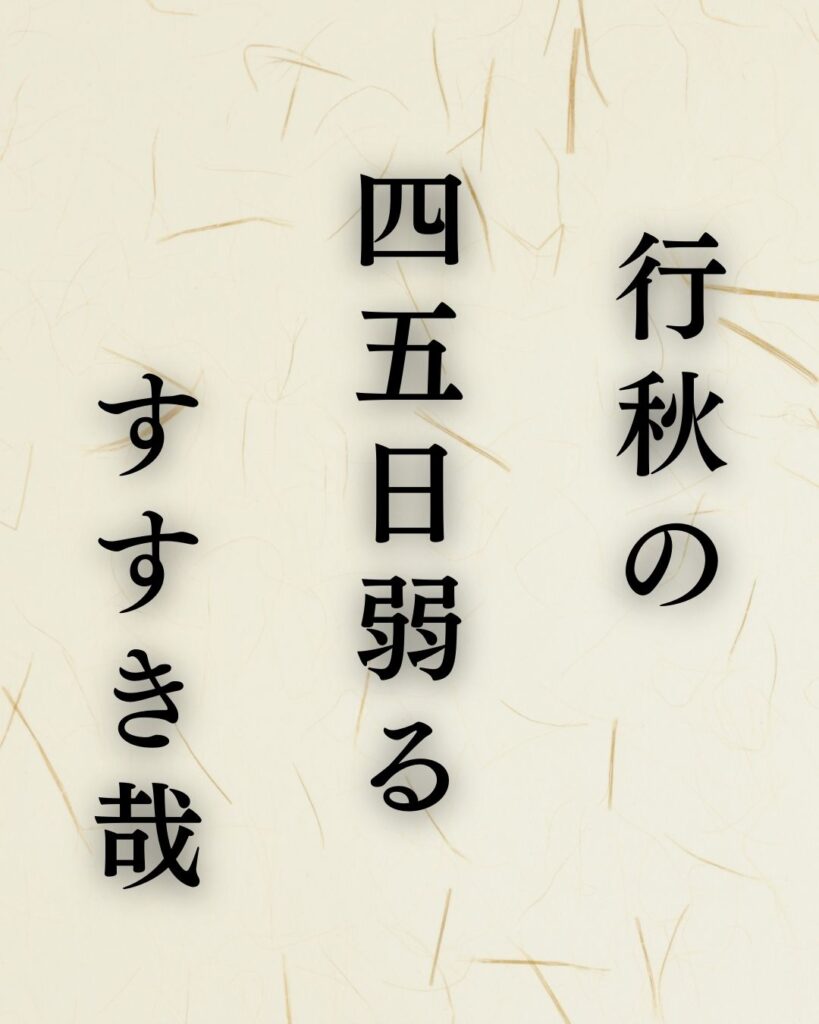
行秋の 四五日弱る すすき哉
読み方:ゆくあきの しごにちよわる すすきかな
季語:すすき
句意:この句では、秋が過ぎゆくにつれて四、五日で衰えていくすすきの姿が、季節のはかなさとして詠まれています。

つまりこの俳句は、行く秋の気配の中で、わずか数日の間に力を失っていくすすきの姿を描いています。

また、丈草は、草の衰えを通して、季節の移ろいの速さと命のはかなさを象徴的に表現しました。
日常の小さな変化から、深い余情を読み取る感性が光る一句です。
『舟引の 道かたよけて 月見哉』

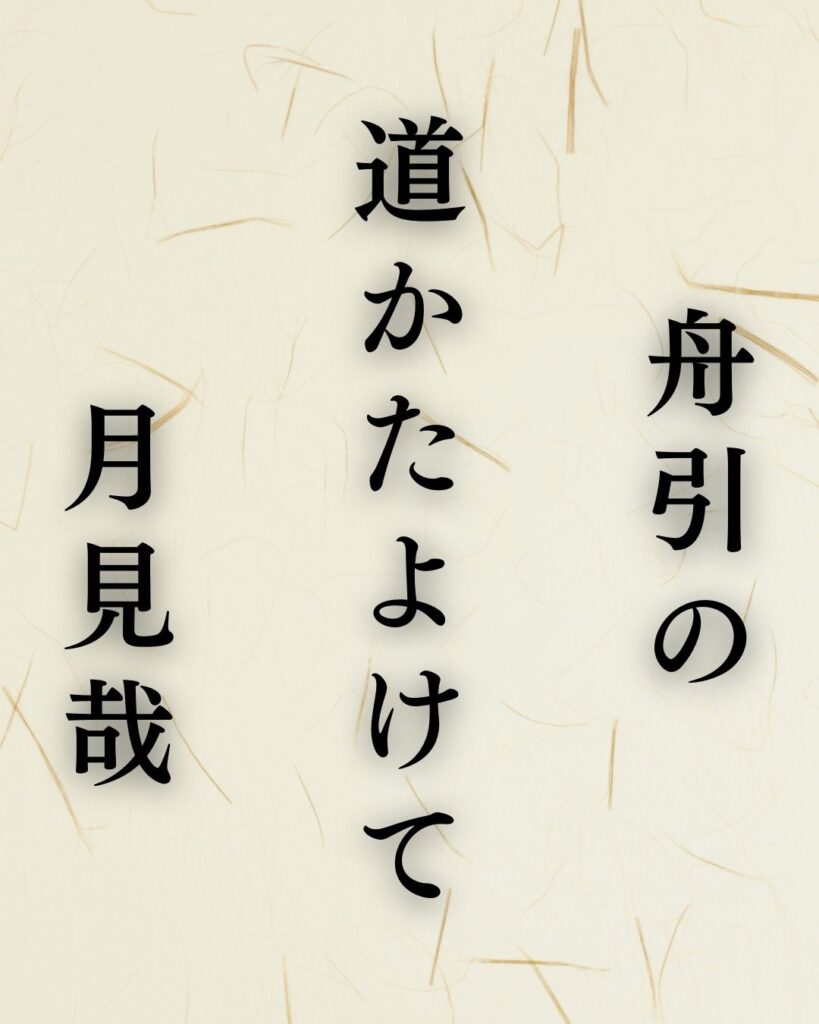
舟引の 道かたよけて 月見哉
読み方:ふなびきの みちかたよけて つきみかな
季語:月見(つきみ)
句意:この句では、舟を引く道を少し外れ、ひととき月見を楽しむ人の姿が、秋の風流として詠まれています。

つまりこの俳句は、労働の場である舟引の道を少し避けて、月見を楽しむ人の姿を描いています。

また日常の労苦の中にも、月の美しさに心を寄せる余裕があるのが印象的です。
丈草は、働く人々の生活と風流を重ね、自然と人の心が調和する秋の情景を巧みに表現しました。
『ぬけがらに ならびて死る 秋のせみ』

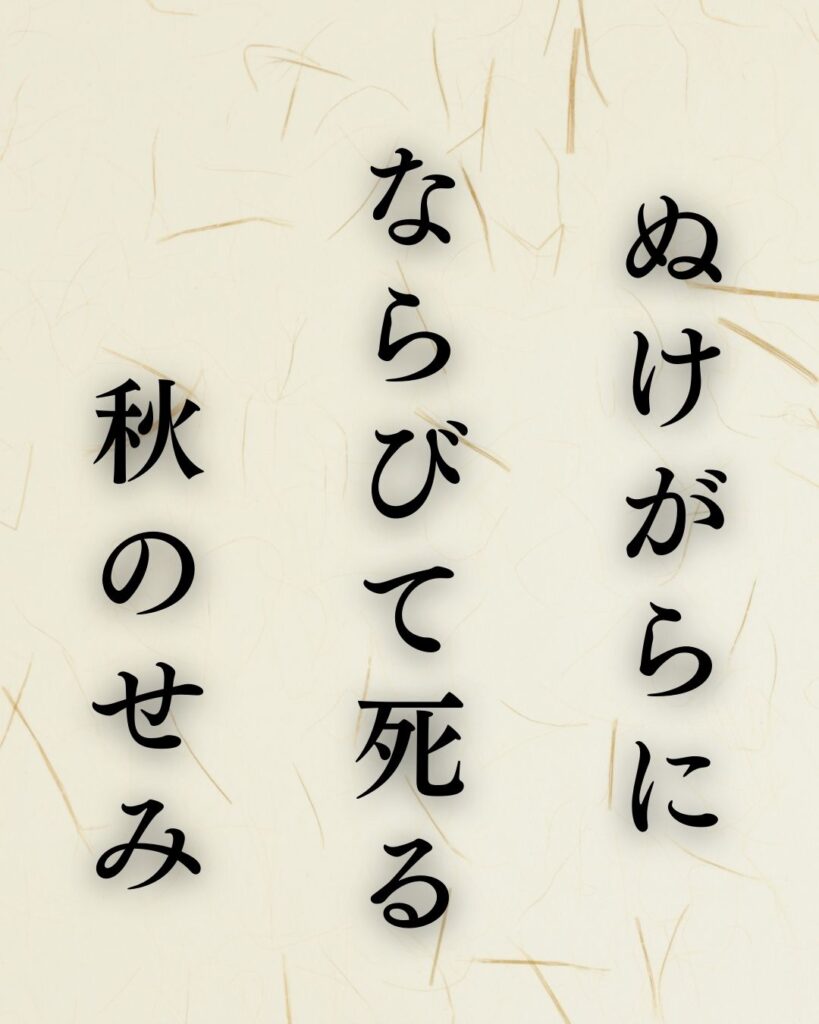
ぬけがらに ならびて死る 秋のせみ
読み方:ぬけがらに ならびてしぬる あきのせみ
季語:秋のせみ
句意:この句では、蝉の抜け殻のそばに並んで死んでいる秋の蝉の姿を通し、命のはかなさが詠まれています。

つまりこの俳句は、木に残る抜け殻のそばで、命を終えた秋の蝉が並んでいる姿を描いています。

また幼虫から成虫へ、そして死へ至る蝉の一生が一画面に収まり、命の循環と儚さが強調されます。
丈草は、自然の小さな出来事を通して、生と死の対比を鮮やかにとらえ、そして秋特有の深い余情を表現しました。
内藤丈草の秋の俳句ちょっとむずかしいクイズ
クイズ:内藤丈草は、どの俳人の高弟として知られているでしょうか?
- 与謝蕪村
- 松尾芭蕉
- 小林一茶
▶四季を通して丈草の句を味わうと、蕉門俳人としての個性がより深く見えてきます。
静けさの中に春を映した「内藤丈草の春の俳句5選-春を映す蕉門の孤高」や、
生活感と自然を重ねた「内藤丈草の夏の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」も、ぜひあわせてご覧ください。
内藤丈草の秋の俳句5選まとめ
内藤丈草の秋の俳句では、
吊柿や送り火、すすきや秋の蝉を題材に、
身近な生活と自然の変化を繊細に描いています。
丈草ならではの素朴で余情ある表現が、
秋の趣をより深く伝えてくれます。

この記事「内藤丈草の秋の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」では、内藤丈草が詠んだ秋の名句5選を紹介しました。
クイズの答え:2.松尾芭蕉