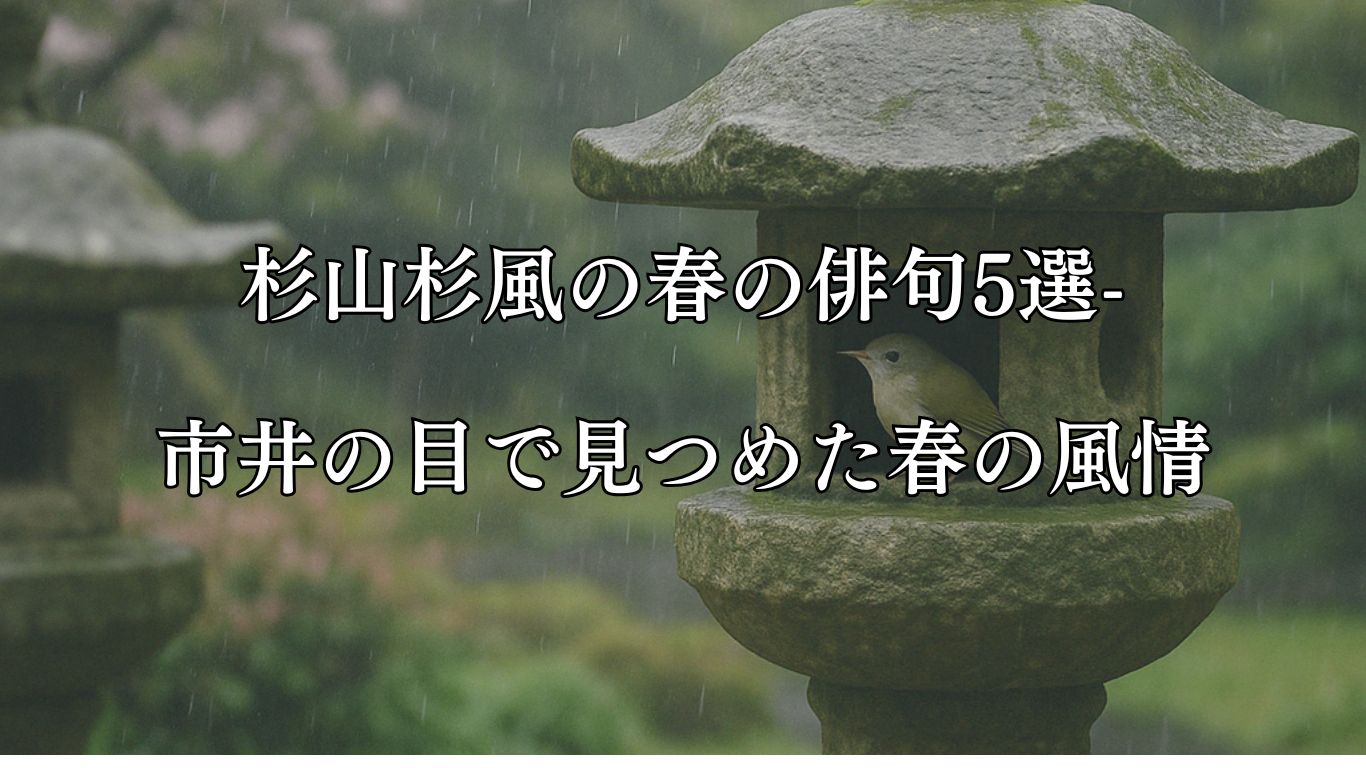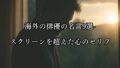杉山杉風の春の俳句で
春の訪れを感じてみませんか?
杉山杉風は、身近な風景を
丁寧に見つめた俳人として知られています。
また春の景色に、庶民の暮らしや
感情がそっと溶け込むとき、
俳句は静かな温もりを帯びて響きます。

本記事では、初心者でも楽しめる杉山杉風の春の俳句を5つ厳選してわかりやすく解説します。

言葉で感じる春の美しさを、一緒に味わいましょう!
杉山杉風の人物像を解説
芭蕉十哲-杉山杉風とは?
杉山杉風 – Wikipedia(すぎやま さんぷう)は、
「蕉門十哲 – Wikipedia」(しょうもんじってつ)の中でも
江戸深川に居を構え、旅に出る芭蕉を
たびたび迎え入れた篤実な性格の持ち主でした。

芭蕉からは「去来は西三十三国の俳諧奉行、杉風は東三十三国の俳諧奉行」と戯評され、東国における俳諧の重鎮として厚い信頼を寄せられていました。

また華美に流れず、素朴な暮らしの中に詩情を見出す句風は、芭蕉の精神を受け継いだものといえます。
杉山杉風の俳句の背景には、師である松尾芭蕉の影響が色濃く表れています。また松尾芭蕉の人物像についてはこちらの記事をご覧ください。
春を詠んだ杉山杉風とは?
杉山杉風の春の俳句は、
華やかさよりも素朴で生活感のある春の情景が特徴です。
また市井の暮らしを大切にしながら、自然と調和した視点で
春を見つめています。

特に身近な感動を繊細にとらえた句から、心の温もりが伝わってきます。
▶杉山杉風の俳句は、師・松尾芭蕉の精神を忠実に受け継ぎつつも、日常に根ざした静かな情趣が魅力です。またそんな杉風の作風をより深く味わうには、芭蕉自身が春に詠んだ句の世界にも触れてみるのがおすすめです。
杉山杉風の春の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!
『春雨や 鴬這入る 石灯籠』

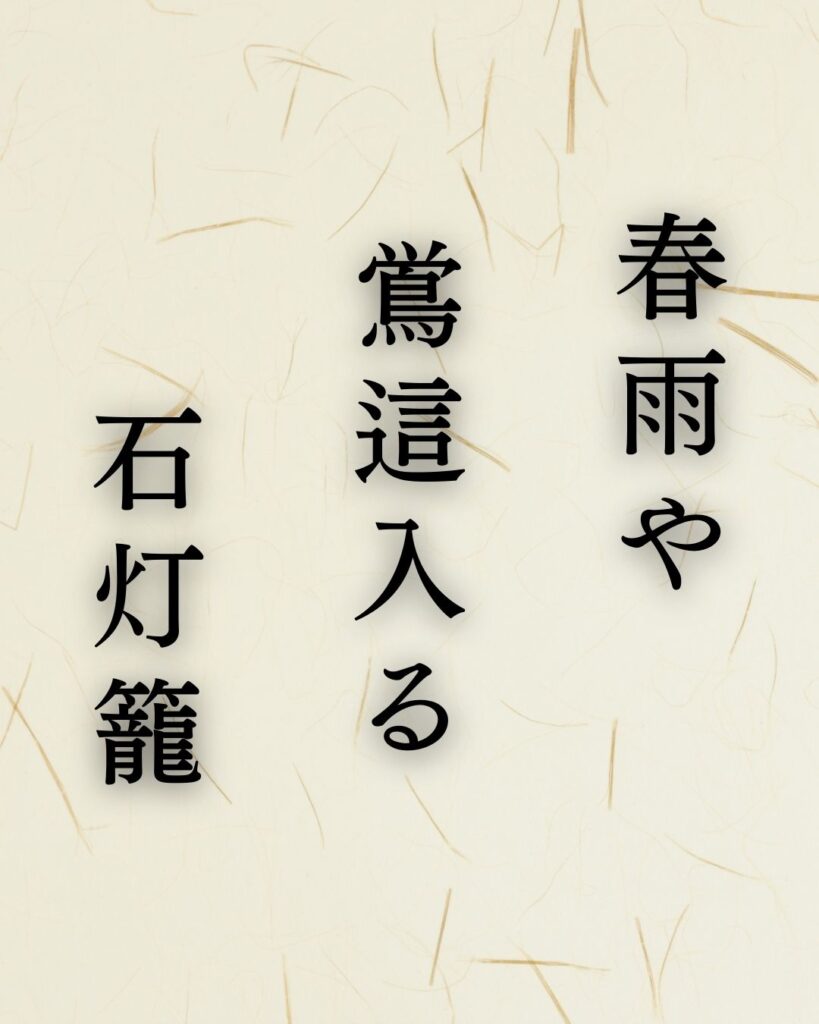
春雨や 鴬這入る 石灯籠
読み方:はるさめや うぐいすはいいる いしどうろう
季語:春雨
句意:この俳句では、春雨のなかで鴬が石灯籠に入る様子を、静けさとともに繊細に詠んでいます。

つまり、しとしとと降る春雨の中、鴬(うぐいす)が石灯籠の中に這い入っていくという、微細で静謐な春の一場面を描いています。

また「石灯籠」という人工物に自然の命が交差する構図が美しく、杉風らしい日常の中の詩情を感じさせます。
音なき動きに春の気配がしっとりと漂い、静寂の中に命の息吹がにじみます。
『ふり上る 鍬の光や 春の野ら』

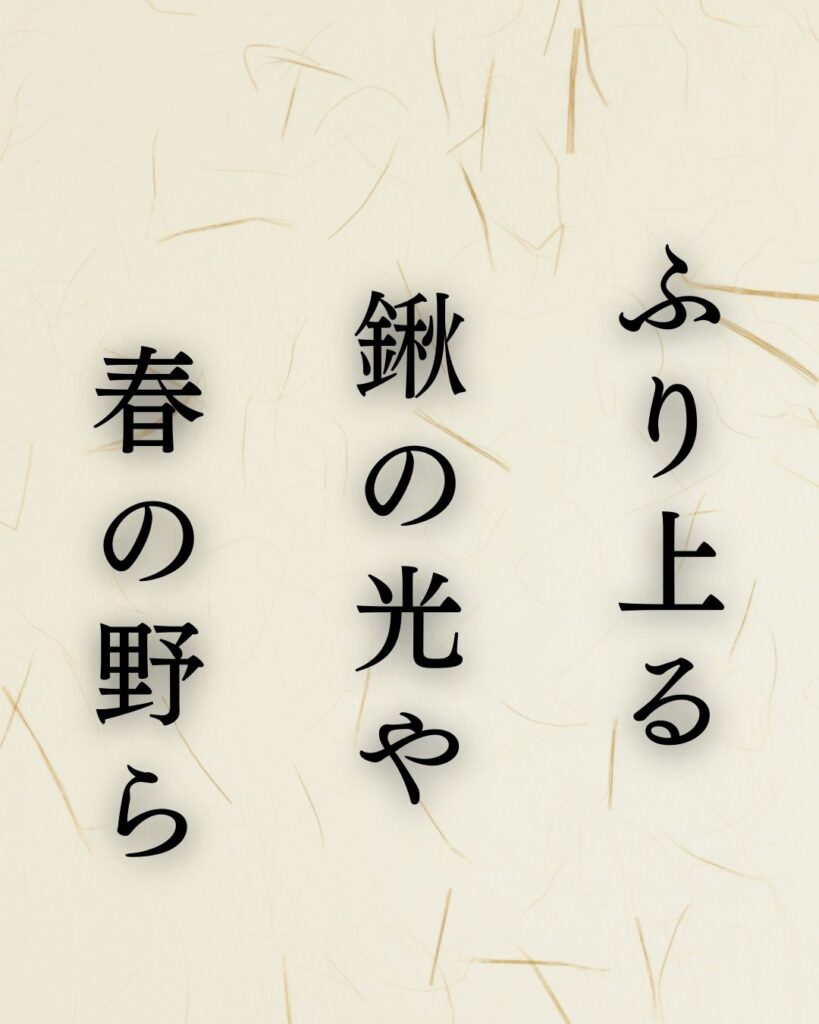
ふり上る 鍬の光や 春の野ら
読み方:ふりあがる くわのひかりや はるののら
季語:春の野
句意:この俳句では、春の野で鍬をふるう動作とその光の輝きを詠んでいます。

つまりこの句は、春の野原で農作業に励む人の一瞬の動きに注目しています。

まだ「ふり上る鍬」に光が反射する描写から、自然と人とのかかわり、そして生命の躍動が伝わってきます。
「春の野ら」という広がりのある季語が、明るく伸びやかな光景を広げ、日常の中にある詩情を見事に掬い上げています。
『提灯の 空に詮なし ほとゝぎす』

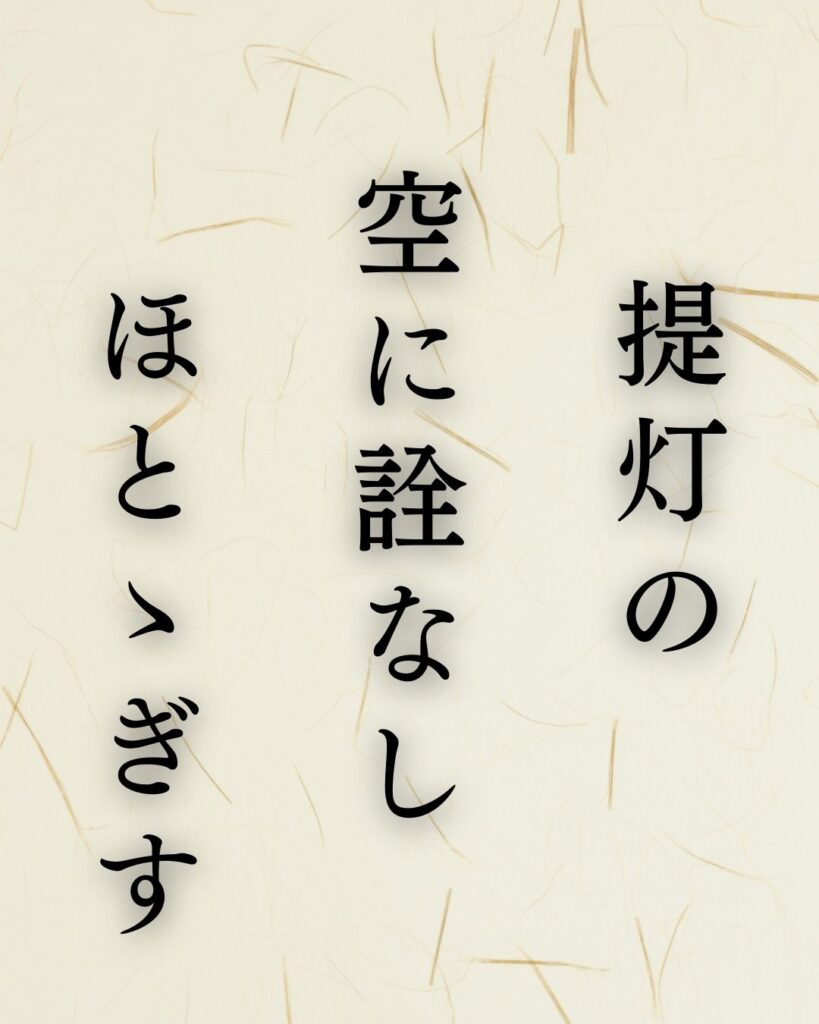
提灯の 空に詮なし ほとゝぎす
読み方:ちょうちんの そらにせんなし ほととぎす
季語:ほととぎす
句意:この俳句では、提灯の光が頼りなく、ほととぎすの声が空しく響く夜の寂しさを詠んでいます。

夜道を照らす提灯の頼りなさと、空に響くほととぎすの声の儚さが響き合います。

また「詮なし(せんなし)」は、どうしようもないという嘆きや虚無感を表し、人の営みと自然の営みの対比が静かに胸に迫ります。
杉風らしい市井の目線で詠まれた、感傷的な一句です。
『紅梅は 娘すまする 妻戸哉』

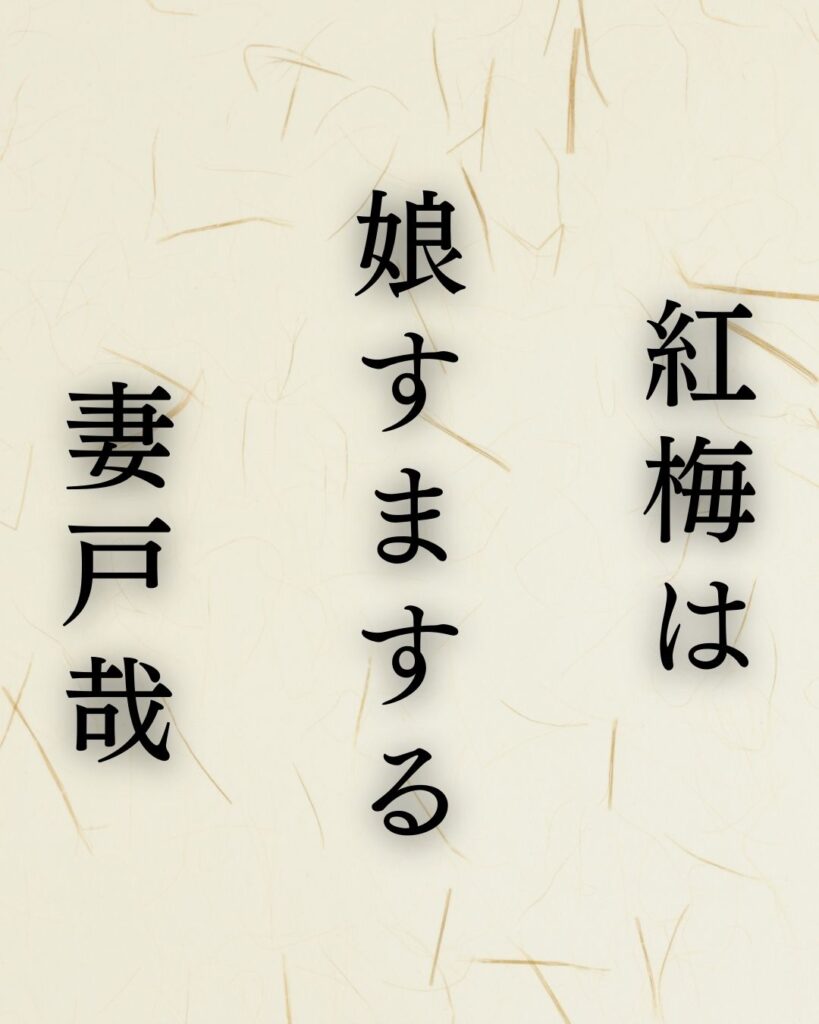
紅梅は 娘すまする 妻戸哉
読み方:こうばいは むすめすまする つまどかな
季語:紅梅
句意:この俳句では、紅梅の咲く中で娘が丁寧に妻戸を閉める静かな光景を詠んでいます。

紅梅が咲く春の庭先、娘が妻戸(障子戸)をきちんと閉める慎ましい所作が描かれています。

また日常の一瞬を切り取った描写の中に、少女の成長やしとやかさがにじみます。
華やかな紅梅と娘の清らかな動きが響き合い、また素朴な生活の中に美しさを感じさせる一句です。
『子や待ん 餘り雲雀の 高あがり』

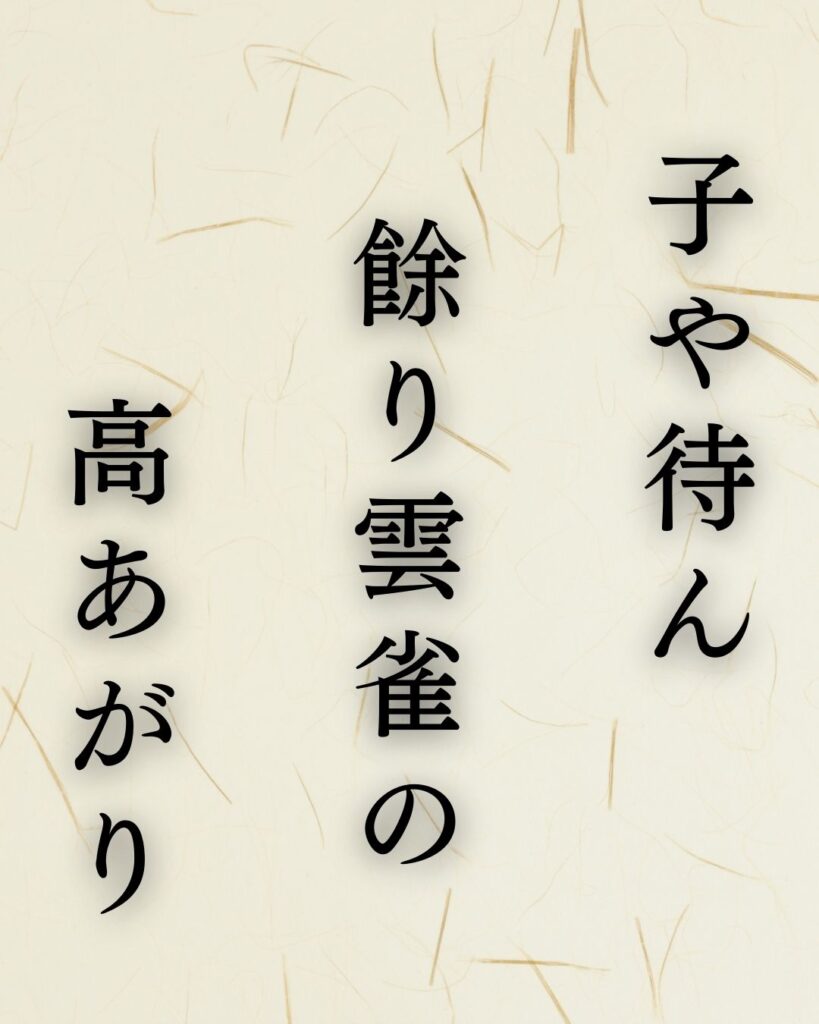
子や待ん 餘り雲雀の 高あがり
読み方:こやまたん あまりひばりの たかあがり
季語:雲雀
句意:この俳句では、子どもを待つ親の心情を、空高く舞う雲雀に重ねて詠んでいます。

雲雀が空高く舞い上がっていく様子を見つめながら、子どもが帰るのを待っている情景が描かれています。

また空の高さと子への思いが静かに重なり、日常の一瞬に深い詩情が宿ります。
ひとつの春の光景に、親心の余情がにじみます。
杉山杉風の俳句ちょっとむずかしいクイズ
クイズ:杉山杉風が芭蕉から評された言葉として正しいのはどれでしょう?
- 杉風は東の風流人、去来は西の詩仙
- 去来は西三十三国の俳諧奉行、杉風は東三十三国の俳諧奉行
- 杉風は蕉門の影法師、去来は蕉門の道化者
▶杉山杉風が詠んだ夏の俳句では、蛙や蛍、杜若など、自然のいのちが息づく明るい季節の風景が描かれています。芭蕉の門弟として知られる杉風の、素朴であたたかな感性が光る名句をぜひこちらからご覧ください。
杉山杉風の春の俳句5選まとめ
杉山杉風は、市井に寄り添う視点と
細やかな感性で春の情景を描いた俳人です。
また日常の一コマに春の気配を見出し、
静けさの中に温もりを宿す句風が特徴です。
そして芭蕉の信頼厚い門弟でありながら、
自身の素朴で写実的な美意識を大切にした作品が、
今なお心に響きます。

この記事「杉山杉風の春の俳句5選-市井の目で見つめた春の風情」では、杉風の春の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。
クイズの答え:2.去来は西三十三国の俳諧奉行、杉風は東三十三国の俳諧奉行
※「去来は西三十三国の俳諧奉行、杉風は東三十三国の俳諧奉行」と芭蕉に戯評されるほど、杉風は東国俳壇の信頼厚き存在でした。