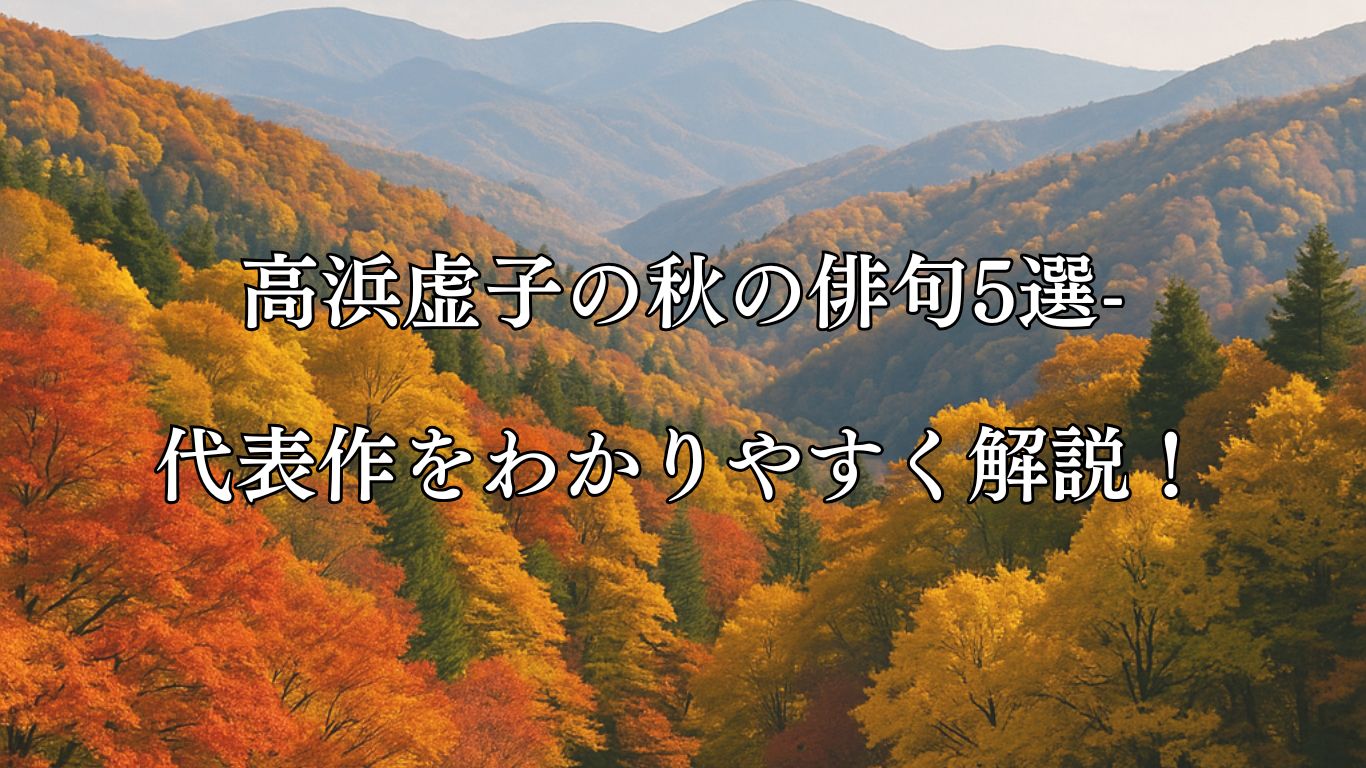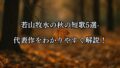高浜虚子の秋の俳句で
秋の訪れを感じてみませんか?
高浜虚子は、
近代俳句を大成させた俳人で、
自然の美しさや人の営みを
写実的に詠みました。

本記事では、秋を題材にした代表作5選を紹介し、やさしく解説します。

初心者の方にも、俳句の魅力をそっと感じていただけますように。
▶前回の記事はこちらから!
夏の虚子の句も、写実と風流が光ります。
「蛍火の今宵の闇の美しき」「蝸牛 葉裏に雨の三日ほど」などを取り上げた
「高浜虚子の夏の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」も、ぜひあわせてご覧ください。
秋を詠んだ高浜虚子とは?
正岡子規の弟子として学び、
のちに近代俳句を大成させた俳人です。
また彼の俳句は、
自然をありのままに写す写生の姿勢と、
そこに漂う余情が特徴です。

秋を詠んだ句では、桐の葉や萩、秋の山野や夕暮れの景色などを題材に、季節の深まりと人生の機微を重ねました。

そして、身近な情景を鮮やかに描き出す表現力によって、初心者にもわかりやすく、親しみやすい作品が多く残されています。
彼の生涯や代表作について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。また俳句の背景を知ることで、より味わい深く楽しめます。
高浜虚子の秋の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!
『桐一葉 月の光に ひろがりて』

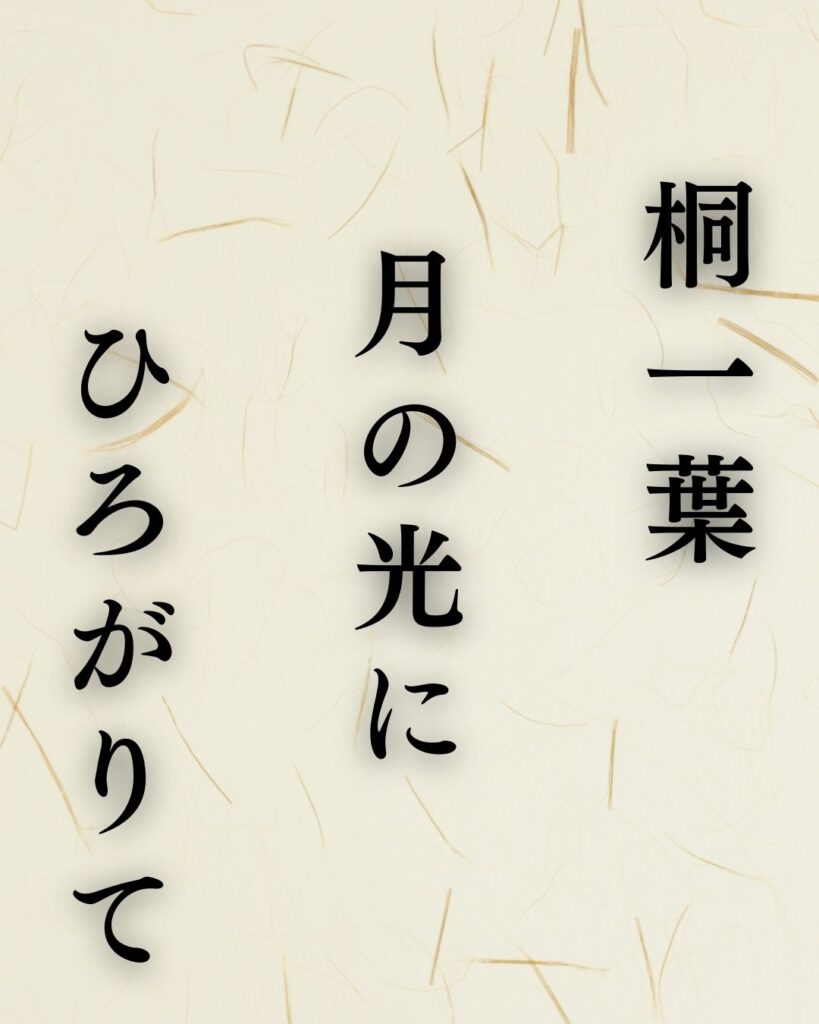
桐一葉 月の光に ひろがりて
読み方:きりひとは つきのひかりに ひろがりて
季語:桐一葉(きりひとは)
句意:この句では、桐の葉が一枚落ちて月光に広がる様子を通し、秋の静けさと人生の無常を詠んでいます。

つまりこの俳句は、一枚の桐の葉が落ちて、静かに月の光に照らされ広がる姿を描いています。

またわずかな動きの中に、秋の深まりと人生の無常感が漂うのが特徴です。
虚子は、自然の細やかな現象を通して、静寂と余情を端的に表現しました。そして桐一葉の象徴性が、秋の夜をより深く印象づけています。
『萩吹くや 葉山通ひの 仕舞馬車』

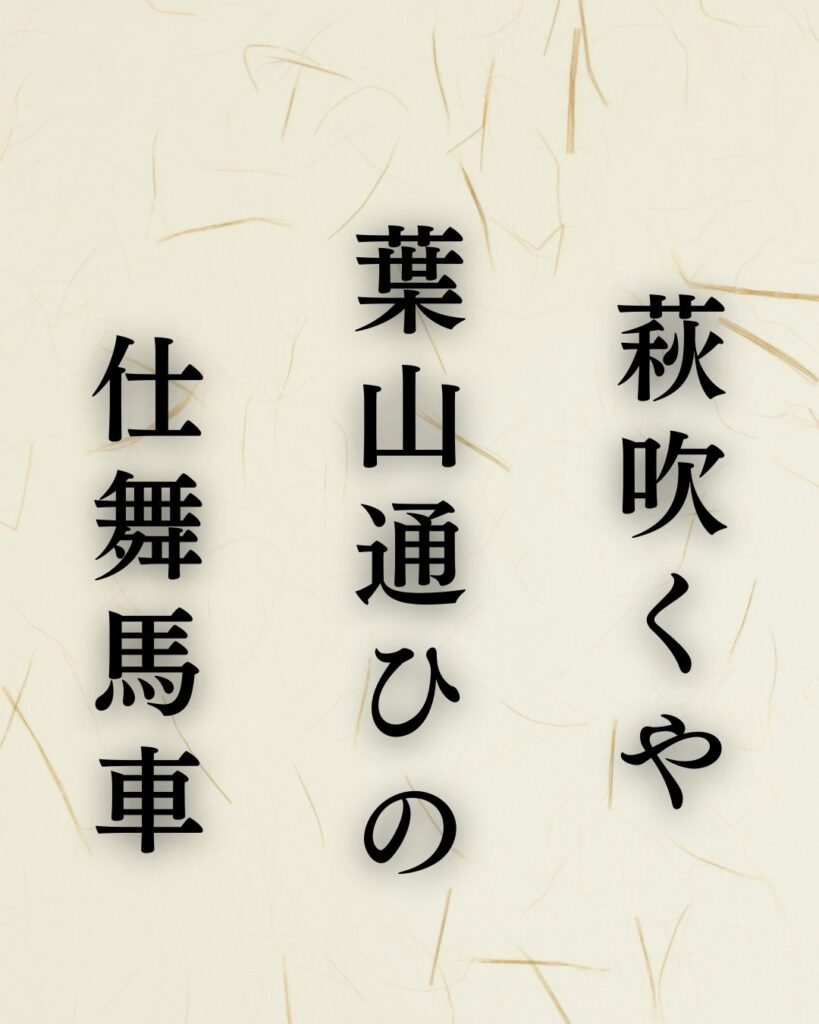
萩吹くや 葉山通ひの 仕舞馬車
読み方:おぎふくや はやまがよいの しまいばしゃ
季語:萩の声(おぎのこえ)
句意:この句では、萩の風に吹かれる音を背景に、葉山へ通う最後の馬車の去りゆく情景が詠まれています。

つまりこの俳句は、秋風に揺れる萩の音を聞きながら、葉山への行き来を終える仕舞馬車が通る場面を描いています。

また自然の音と人の営みが重なり、季節の移ろいと時代の変化を感じさせるのが特徴です。
虚子は、日常の風景に郷愁と詩情を重ね、秋の余韻を豊かに表現しました。
『眼つむれば 今日の錦の 野山かな』

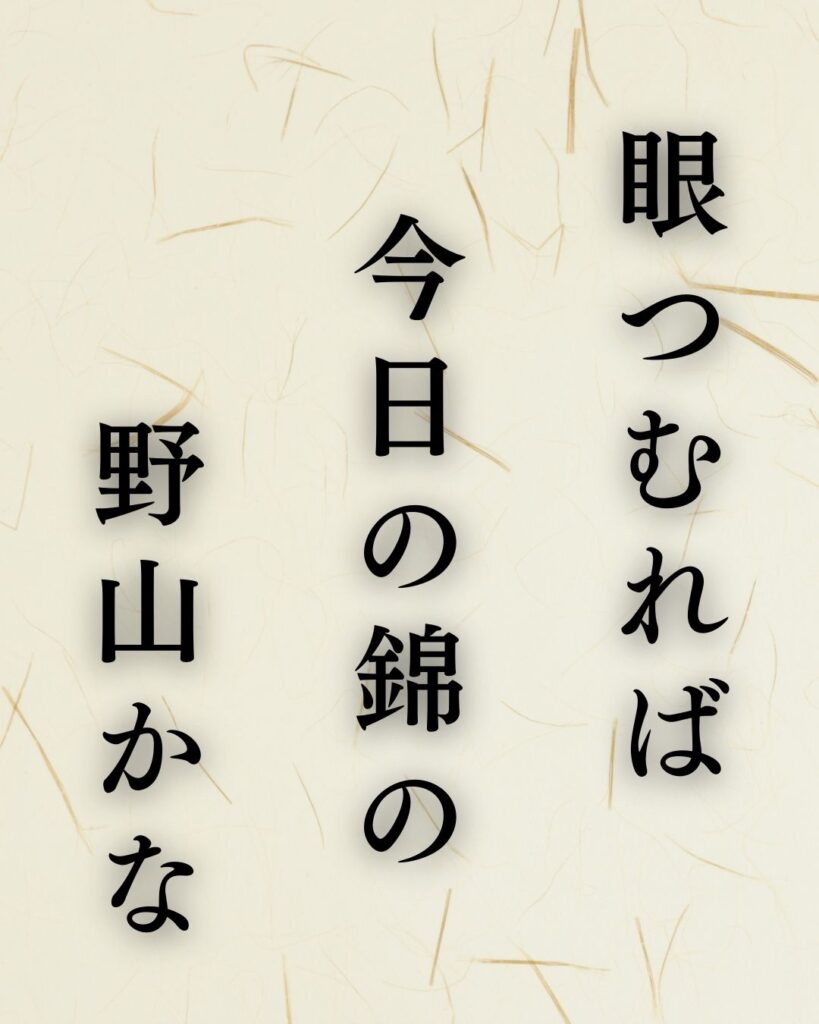
眼つむれば 今日の錦の 野山かな
読み方:めつむれば きょうのにしきの のやまかな
季語:山粧う(やまよそおう)
句意:この句では、錦のように彩られた秋の山野の光景が、目を閉じても鮮やかに心に残る様子を詠んでいます。

つまりこの俳句は、錦の織物のように色鮮やかに粧った秋の山野を描いています。

また目を閉じてもその景色が残るほど、自然の美が強く心に刻まれているのが特徴です。
虚子は、山粧うという季語を通して、自然の壮麗さと感動を余韻豊かに表現しました。そして視覚と心象風景が重なり、秋の彩りを深く伝える一句です。
『盆礼に 忍び来しにも 似たるかな』

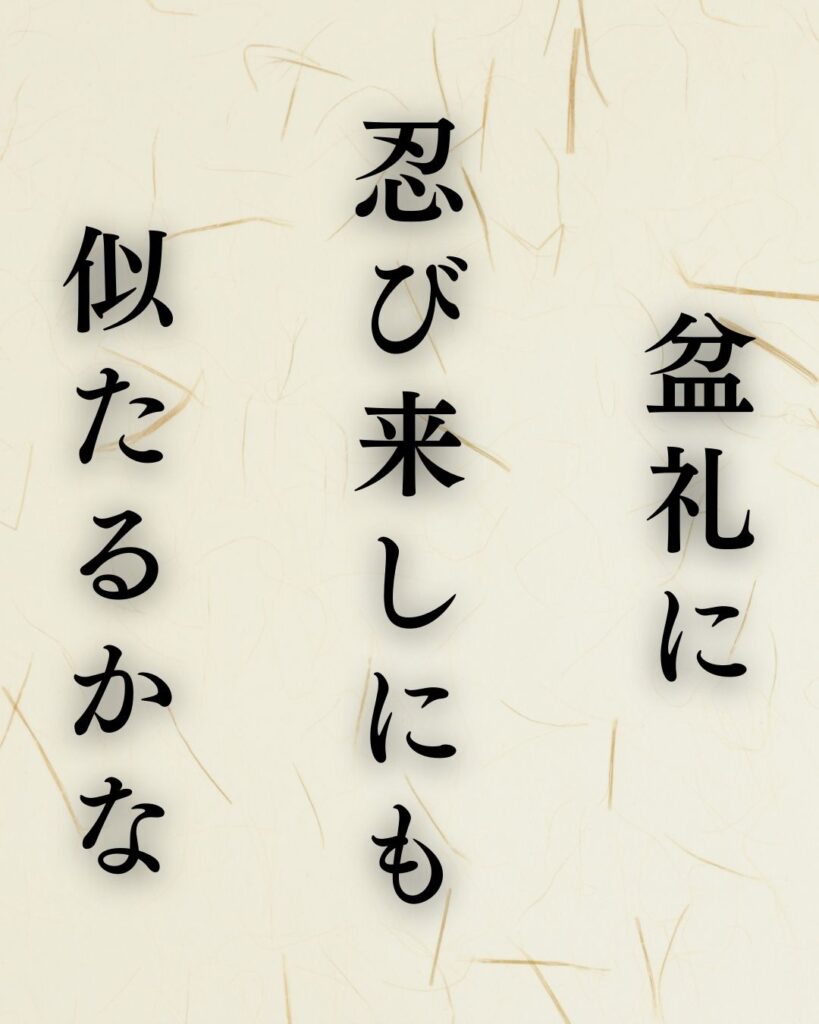
盆礼に 忍び来しにも 似たるかな
読み方:ぼんれいに しのびきしにも にたるかな
季語:中元(ちゅうげん)
句意:この句では、中元の贈り物を持って訪れる姿が、忍ぶように静かにやって来る様子に重ねて詠まれています。

つまりこの俳句は、中元の挨拶に贈り物を携えて訪れる人の様子を描いています。

またその姿は、まるで忍びやかにやって来る人影のようで、控えめで丁寧な気配が漂います。
虚子は、季語「中元」を通して、人と人のつながりの奥ゆかしさや、贈答文化の持つ情感を巧みに表現しました。そして日常の習わしを詩情に昇華させた一句です。
『高くあげて 提灯越ゆる 萩むらを』

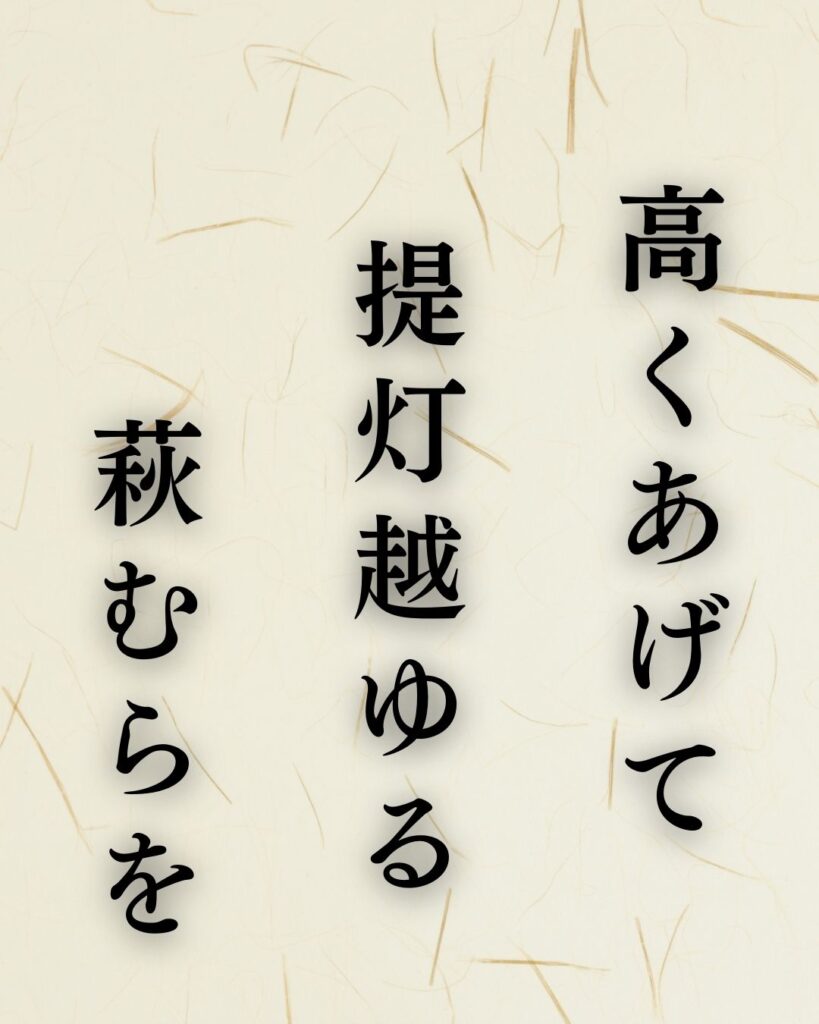
高くあげて 提灯越ゆる 萩むらを
読み方:たかくあげて ちょうちんこゆる はぎむらを
季語:萩(はぎ)
句意:この句では、高く掲げた提灯が萩の群れを越えて進む情景が、秋の風物詩として風流に詠まれています。

つまりこの句は、夜道を照らす提灯が高く掲げられ、群れ咲く萩の花を越えて進む光景を描いています。

また提灯の灯りと萩の彩りが重なり、秋の夜の趣が鮮やかに表現されているのが特徴です。
虚子は、身近な場面に自然と人の営みの調和を見出し、秋らしい詩情を巧みに描き出しました。
高浜虚子の俳句ちょっとむずかしいクイズ
クイズ:高浜虚子は、近代俳句を大成させた俳人ですが、師である人物は誰でしょうか?
- 与謝蕪村
- 正岡子規
- 松尾芭蕉
▶虚子の秋の句をもっと気軽に楽しみたい方には、「イラストでシンプルに楽しむ高浜虚子の秋の俳句5選」もおすすめです。また代表作を深く掘り下げた高浜虚子の代表作「遠山に」に迫る!の記事もぜひご覧ください。
👉高浜虚子の代表作「遠山に」に迫る!名句や人物像を徹底解説!
高浜虚子の秋の俳句5選まとめ
高浜虚子の秋の俳句は、
桐一葉や萩、秋の山野や月を題材に、
自然と人の営みを写実的に描いています。
また、虚子ならではの明快で余情ある表現が、
秋の深まりを鮮やかに伝えています。

この記事「高浜虚子の秋の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」では、虚子の秋の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。
クイズの答え:2.正岡子規
※高浜虚子は正岡子規の弟子として学び、その後「写生」の理念を受け継ぎながら独自の俳句観を築き、近代俳句を大成させました。