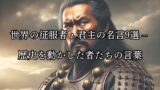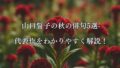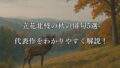徳川家康の名言で、
人生の指針を探しませんか?
徳川家康は戦国の乱世を生き抜き、
江戸幕府を開いた人物です。
彼の言葉には、勝ち負けの中で学んだ忍耐や、
慢心を戒める姿勢など、
現代にも通じる知恵が込められています。

本記事では、家康の名言9つを初心者にもわかりやすく解説し、日常に役立つヒントとして紹介します。
▶︎「世界の征服者・君主の名言9選 – 歴史を動かした者たちの言葉」では、信長やナポレオン、始皇帝など偉大なリーダーたちの言葉を紹介しました。
歴史を動かした名言は、現代を生きる私たちにも多くの学びを与えてくれます。ぜひあわせてご覧ください。
※本記事の文言は、演説・発言等の趣旨を参照した要約・再編集です。原文の直引用ではなく、正確性を保証するものではありません。エンターテインメントとしてお楽しみください。
- 徳川家康とは?
- 現代に響く教え9選
- 徳川家康の名言『勝ち方だけを知り、負け方を知らぬ者は、やがて身を滅ぼす。』
- 徳川家康の名言『心に欲が生じたときは、困窮に苦しんだ日々を思い出すべし。』
- 徳川家康の名言『大軍は勢いに頼り、小勢は心を一つにして戦う。』
- 徳川家康の名言『絶頂のときこそ油断は禁物。隙は必ず生まれる。』
- 徳川家康の名言『足りぬことは、過ぎることよりも優れている。』
- 徳川家康の名言『人の一生は重荷を背負い、遠い道を歩むようなもの。急ぐべからず。』
- 徳川家康の名言『堪忍は平穏を長く保つ基なり。怒りは己を滅ぼす敵と思え。』
- 徳川家康の名言『勝つことばかり知り、負けを知らぬは危うい。必ず身を損なう。』
- 徳川家康の名言『滅びの原因は外にあらず、自らの内に潜む。』
- ちょっとむずかしいクイズ
- 名言シリーズ最新記事紹介
徳川家康とは?
戦国時代に活躍した武将で、
江戸幕府を開いた人物です。
また天下統一を果たし、
およそ260年にわたる
江戸時代の基盤を築きました。
そして家康は忍耐強く慎重な性格で、
勝ち負けから学ぶ姿勢を大切にしました。

その生き方は「鳴くまで待とうホトトギス」にも表されます。

彼の残した言葉には、忍耐や謙虚さ、人生を安定して歩むための知恵が込められており、現代にも通じる教えとなっています。
現代に響く教え9選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!
徳川家康の名言『勝ち方だけを知り、負け方を知らぬ者は、やがて身を滅ぼす。』

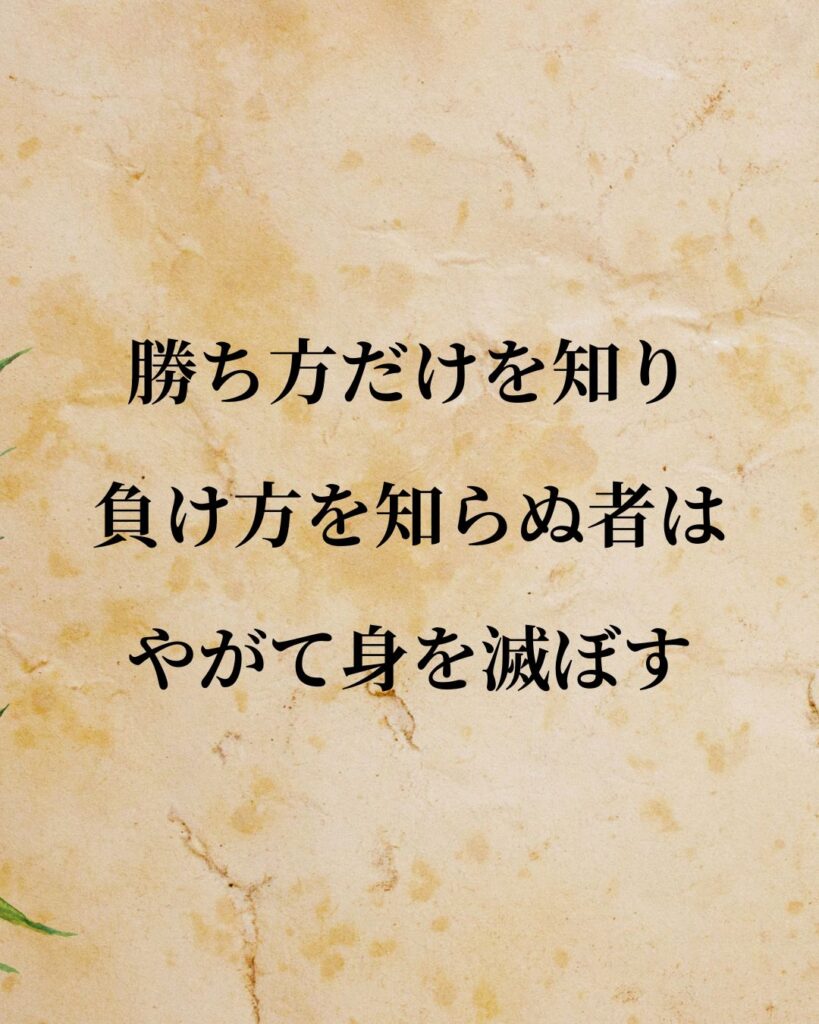
“勝ち方だけを知り、負け方を知らぬ者は、やがて身を滅ぼす。“
意味:この言葉では、勝つことばかりに執着し、負けを受け入れる姿勢を持たない人は、やがて大きな失敗に直面するという意味です。
また負けを知ることは謙虚さを学び、次への力になります。そして家康は、敗北を恐れず学ぶ姿勢こそが長く生き残る力だと説きました。

負けるのはいやだけど、“どう負けるか”で次が変わるんだね

家康は勝利よりも敗北の学びを重んじました。負けを知らぬ者は、やがて大敗を招くと警告しているのです。
「徳川家康の名言」を日常で取り入れるコツ
この名言は、失敗を受け入れられないときに使えます。
たとえば、負けを悔やんで立ち止まるとき、「負けも学びになる」と考えることで前へ進めます。
徳川家康の名言『心に欲が生じたときは、困窮に苦しんだ日々を思い出すべし。』

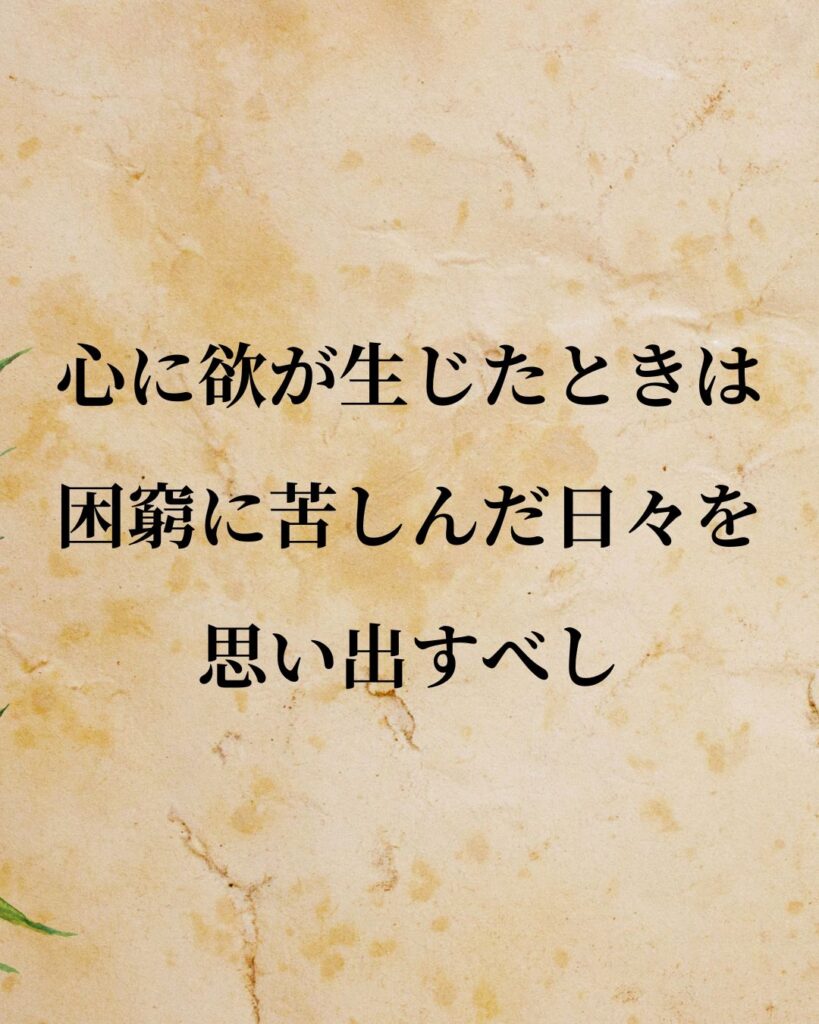
“心に欲が生じたときは、困窮に苦しんだ日々を思い出すべし。“
意味:この言葉では、欲望にとらわれそうになったとき、過去の苦しい経験を思い出し、慎みを持つことが大切だという意味です。
また豊かさに慣れると感謝を忘れがちになりますが、困難を忘れなければ節度を保てます。そして家康は、欲を抑える知恵が生き抜く力になると教えました。

“もっと欲しい!”って気持ちも、昔の苦しさを思い出したら落ち着けるのかもね

家康は欲望の危うさを知っていました。困窮を忘れぬ心が、慢心を防ぎ、堅実さを守るのです。
「徳川家康の名言」を日常で取り入れるコツ
この名言は、欲張りすぎて不安になるときに使えます。
たとえば、物欲や承認欲求に駆られたとき、「あの苦しい日を忘れずに」と心を戒めることができます。
徳川家康の名言『大軍は勢いに頼り、小勢は心を一つにして戦う。』

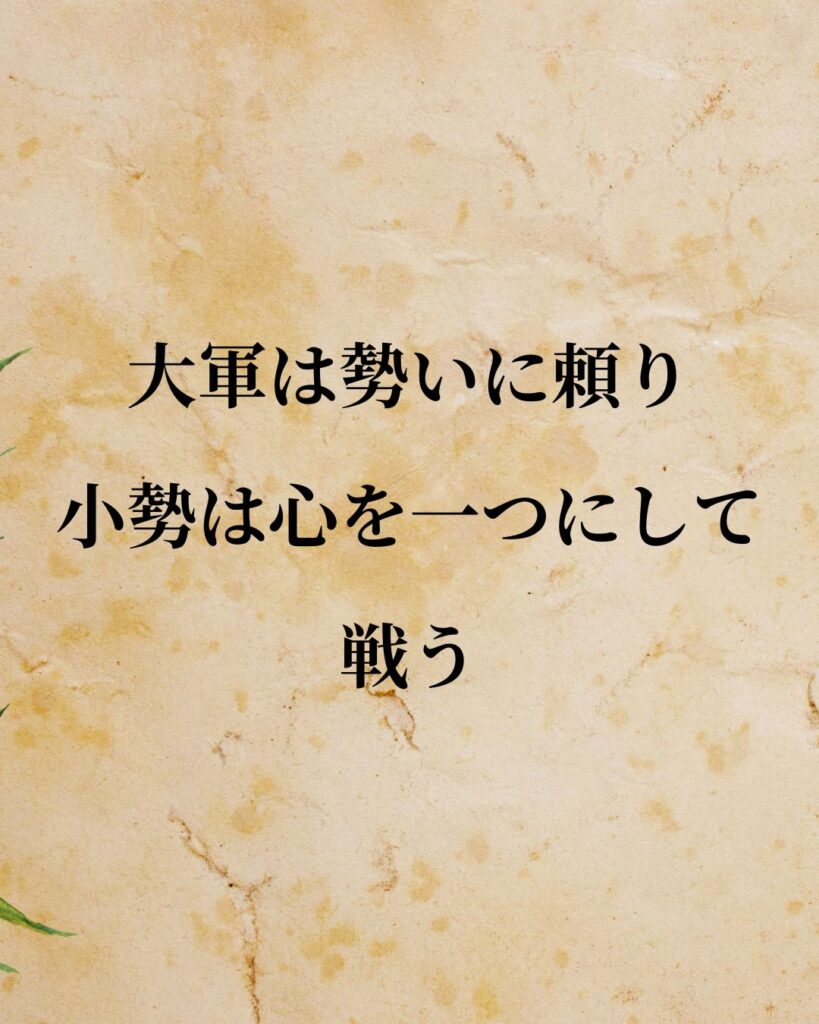
“大軍は勢いに頼り、小勢は心を一つにして戦う。“
意味:この言葉では、大きな集団は数の力や勢いに頼りがちだが、小さな集団は心を一つに団結することで大軍に立ち向かえる、という意味です。
また勝敗を決めるのは数ではなく結束力。そして家康は、仲間との絆こそが困難を超える力になると説きました。

人数が少なくても、気持ちを合わせたらすごい力になるんだね

家康は勢いよりも団結の力を重視しました。数の大小より心を一つにすることが勝敗を分けるのです。
「徳川家康の名言」を日常で取り入れるコツ
この名言は、チームで挑戦するときに使えます。
たとえば、少人数で大きな課題に向かうとき、「心を一つにすれば勝てる」と勇気をもらえます。
徳川家康の名言『絶頂のときこそ油断は禁物。隙は必ず生まれる。』

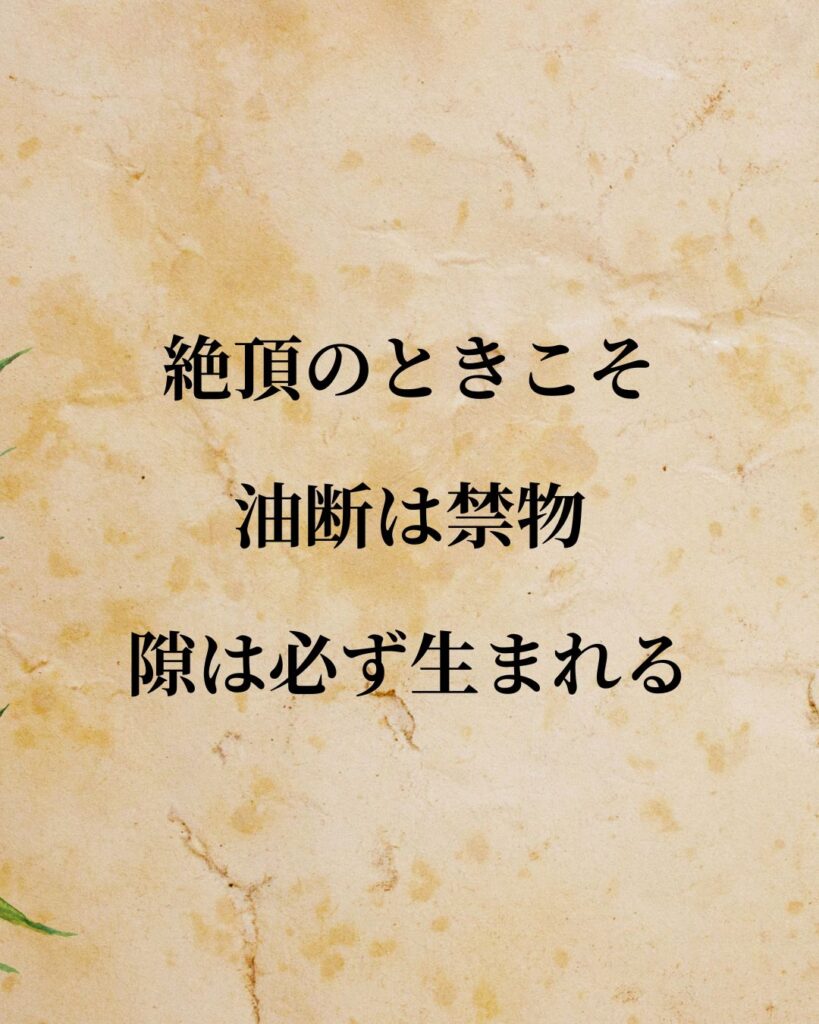
“絶頂のときこそ油断は禁物。隙は必ず生まれる。“
意味:この言葉では、成功や好調の絶頂にあるときほど気を引き締めなければならない、という意味です。
また人は順調だと慢心して隙をつくりやすく、その油断が思わぬ失敗を招きます。そして家康は、勝っているときこそ謙虚さを忘れず慎重に振る舞うべきだと戒めました。

“うまくいってる!”ってときほど、ほんとは気をつけないといけないんだね

家康は絶頂期こそ危ういと見抜きました。油断が必ず隙を生み、成功を崩す原因になるのです。
「徳川家康の名言」を日常で取り入れるコツ
この名言は、成功に浮かれているときに使えます。
たとえば、成果を出して安心したとき、「ここからが気を引き締めるとき」と意識を切り替えられます。
徳川家康の名言『足りぬことは、過ぎることよりも優れている。』

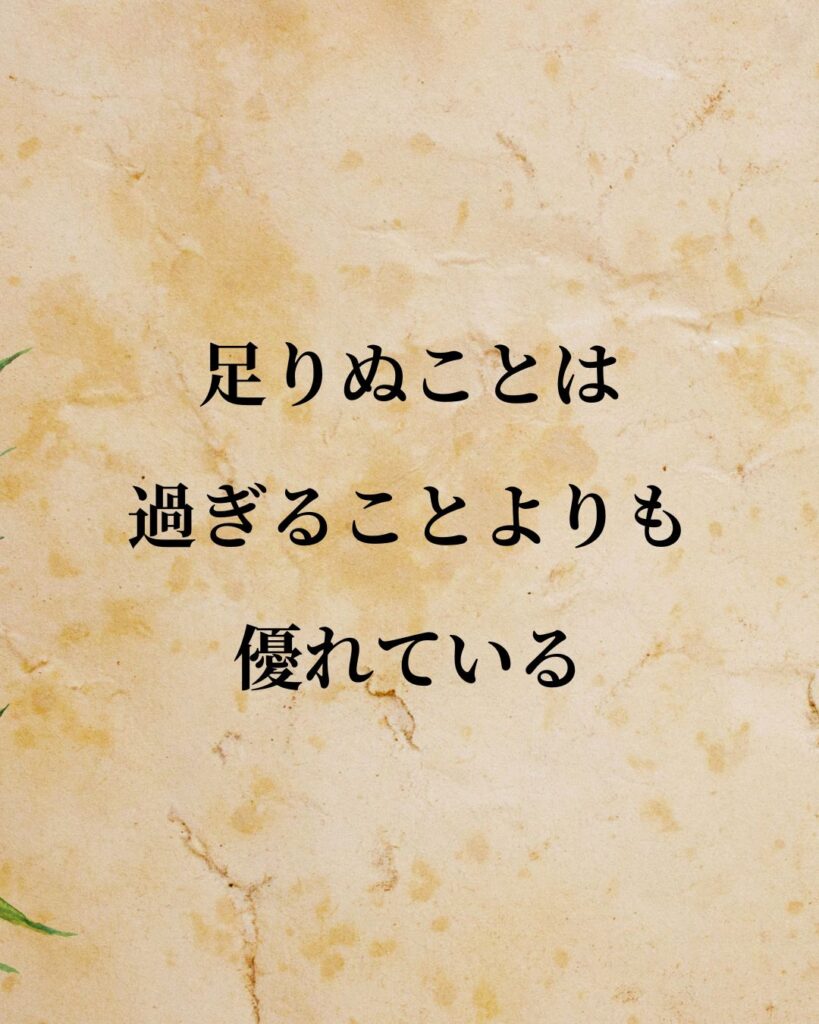
“足りぬことは、過ぎることよりも優れている。“
意味:この言葉は、ものごとが不足している状態は不便に見えても、やりすぎて害を生む状態よりは健全である、という意味です。
また節度ある不足は工夫や成長を生み、過剰はかえって破滅を招きます。そして家康は、中庸を守る知恵こそ長く続く力だと説きました。

ちょっと足りないくらいが、がんばる元気や工夫につながるんだね

家康は“過ぎたるは及ばざるがごとし”を実践しました。不足は成長を生み、過剰は害を生むのです。
「徳川家康の名言」を日常で取り入れるコツ
この名言は、やりすぎて疲れてしまうときに使えます。
たとえば、仕事や勉強で無理を重ねそうなとき、「少し足りないくらいでちょうどいい」と心を整えられます。
徳川家康の名言『人の一生は重荷を背負い、遠い道を歩むようなもの。急ぐべからず。』

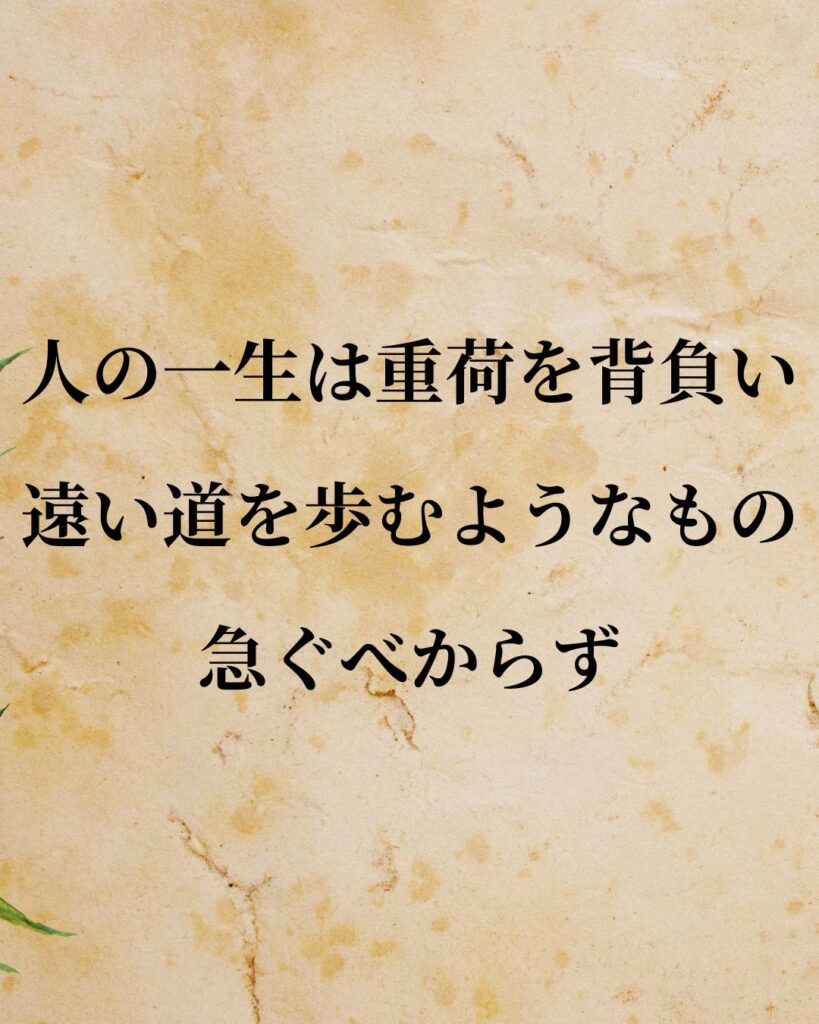
“人の一生は重荷を背負い、遠い道を歩むようなもの。急ぐべからず。“
意味:この言葉では、人生は重い責任を抱えて長い道のりを歩くようなものだから、焦らず一歩ずつ進むことが大切だ、という意味です。
また急いでも近道はなく、忍耐と努力を重ねることで確かな成果が得られます。そして家康は、忍耐と継続の大切さを強調しました。

人生ってマラソンみたいだね。あせらずに一歩ずつ進めばいいんだ

家康は人生を長い道のりにたとえました。焦りは誤りを生みます。忍耐こそが成功への道だと説いたのです。
「徳川家康の名言」を日常で取り入れるコツ
この名言は、焦って結果を求めそうなときに使えます。
たとえば、努力が実らず不安なときに、「急がず歩み続ければよい」と心を落ち着けられます。
徳川家康の名言『堪忍は平穏を長く保つ基なり。怒りは己を滅ぼす敵と思え。』

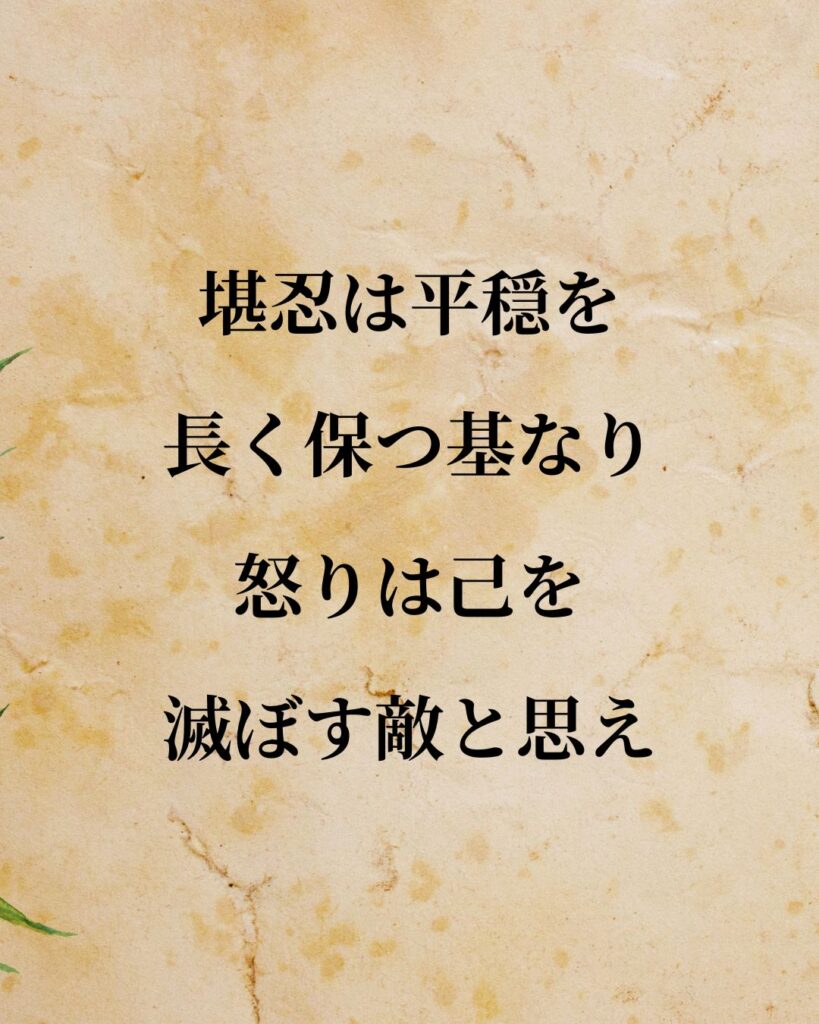
“堪忍は平穏を長く保つ基なり。怒りは己を滅ぼす敵と思え。“
意味:この言葉では、忍耐は平和を保つ土台であり、怒りは自分を傷つける最大の敵だという意味です。
また怒りに任せて行動すれば人間関係を壊し、後悔を生みます。そして家康は、感情を抑える忍耐が人生を安定させる力だと説きました。

カッとなったら負けなんだね。ぐっとこらえたら、平和が長く続くんだ

家康は怒りを“最大の敵”と見抜きました。堪忍が人を救い、怒りが人を滅ぼすのです。
「徳川家康の名言」を日常で取り入れるコツ
この名言は、感情を抑えられないときに使えます。
たとえば、怒りで言いすぎそうなとき、「堪忍が平穏を守る」と思えば冷静に行動できます。
徳川家康の名言『勝つことばかり知り、負けを知らぬは危うい。必ず身を損なう。』

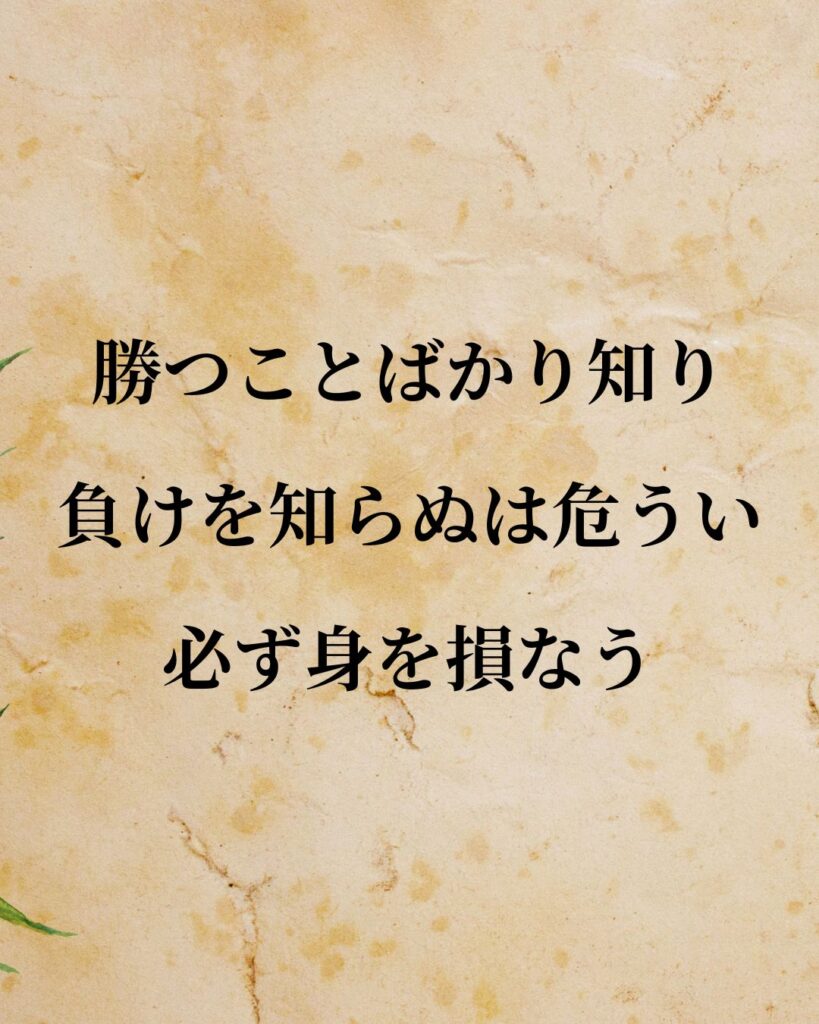
“勝つことばかり知り、負けを知らぬは危うい。必ず身を損なう。“
意味:この言葉では、勝つ経験ばかり重ねて負けの痛みを知らない者は、いざ失敗に直面したときに大きな挫折を味わう、という意味です。
また負けを知ることは謙虚さを学び、次への糧となります。そして家康は、敗北を受け入れる心が長い成功につながると説きました。

負けってイヤだけど、知らなかったらホントの強さにはなれないんだね

家康は“負けの経験”を重視しました。勝利だけを知る者は、いつか大きな失敗で身を滅ぼすのです。
「徳川家康の名言」を日常で取り入れるコツ
この名言は、失敗を恐れて挑戦できないときに使えます。
たとえば、負けを避けて動けないとき、「負けも学び」と思えば一歩を踏み出せます。
徳川家康の名言『滅びの原因は外にあらず、自らの内に潜む。』

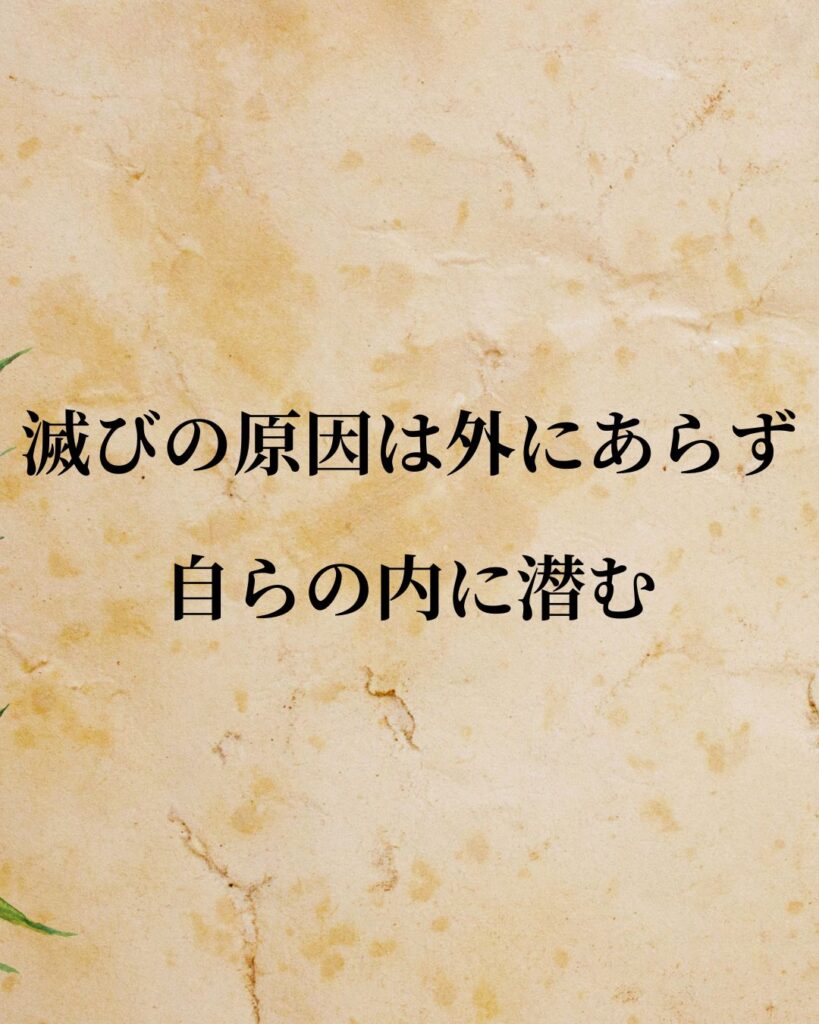
“滅びの原因は外にあらず、自らの内に潜む。“
意味:この言葉では、人や組織が滅びる最大の原因は外敵ではなく、自分自身の心の中にある油断や慢心だという意味です。
また外の敵を恐れるよりも、内側の弱さに気づき克服することが大切。そして家康は、内なる戒めこそ生き残りの要だと教えました。

ほんとの敵って、自分の中にある弱さや油断なのかもしれないね

家康は外よりも内を重んじました。慢心や油断が滅びを招く。だからこそ心を律することが必要なのです。
「徳川家康の名言」を日常で取り入れるコツ
この名言は、自分に甘くなりそうなときに使えます。
たとえば、成功に安心して努力をやめそうなとき、「滅びは内から生まれる」と意識できます。
ちょっとむずかしいクイズ
問題: 徳川家康が開いた幕府はどこにあったでしょう?
- 大阪
- 江戸
- 京都
名言シリーズ最新記事紹介
哲学者・思想家の名言
経営者の名言
政治家の名言
アスリートの名言
発明家の名言
作家の名言
登山家・冒険家の名言
征服者・君主の名言
芸能人の名言
まとめ
徳川家康の名言には、
忍耐や謙虚さ、慢心を避ける姿勢など、
現代にも役立つ知恵が込められています。
▶︎徳川家康の言葉から学べることは多いですが、歴史を動かした偉大な人物は他にもいます。
世界の征服者・君主の名言9選 – 歴史を動かした者たちの言葉では、信長やナポレオン、始皇帝などの名言を紹介しています。
あわせて読むことで、より深い学びが得られるでしょう。
👉世界の征服者・君主の名言9選 – 歴史を動かした者たちの言葉
勝つことだけでなく負けから学ぶ姿勢や、
怒りを抑える心の大切さは、
日常生活にも活かせる教えです。

家康の言葉は、長い人生を安定して歩むための道しるべとなり、私たちに落ち着きと力を与えてくれます。
※本記事の文言は、演説・発言等の趣旨を参照した要約・再編集です。原文の直引用ではなく、正確性を保証するものではありません。エンターテインメントとしてお楽しみください。
クイズの答え:2.江戸