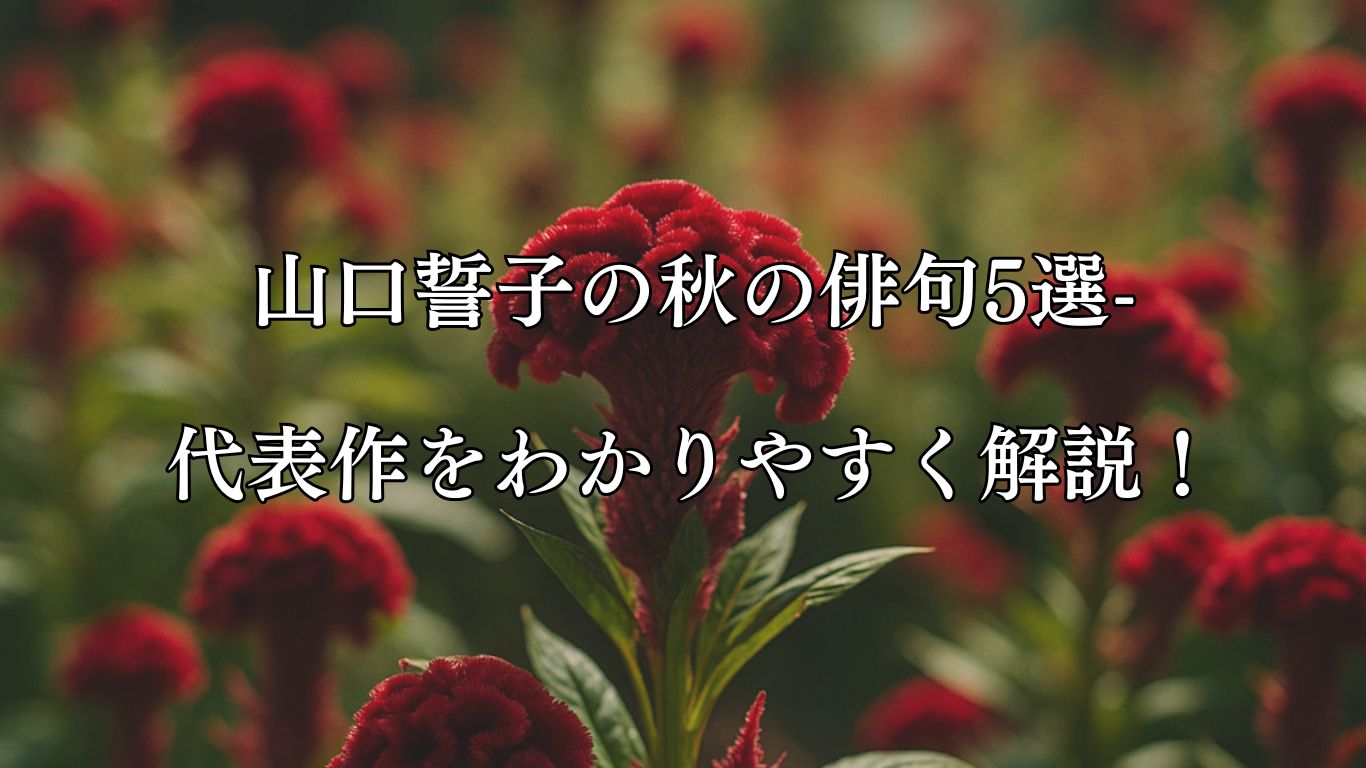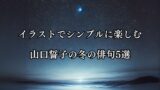山口誓子の秋の俳句で
秋の訪れを感じてみませんか?
山口誓子の俳句は、
自然を鋭くとらえる観察眼と、
人間の生き方を映す視線が大きな魅力です。

この記事では、秋を詠んだ代表的な5句を初心者にもわかりやすく解説します。

そして澄んだ空や風、花や生き物に込められた誓子の詩情を一緒に味わってみませんか。
▶前回の記事はこちらから!
前回は、山口誓子が詠んだ夏の俳句をご紹介しました。
夏氷やつばめ、夕焼けなど、鮮やかな季節の情景を映す名句をぜひこちらからご覧ください。
秋を詠んだ山口誓子とは?
山口誓子 – Wikipedia(やまぐち せいし)は、
昭和を代表する俳人で、
自然を科学のように冷静に観察する作風で
知られています。
とくに秋の俳句では、
澄んだ空や風景だけでなく、
人の心の影や命の厳しさを
鋭く切り取りました。

また美しいものを美しいと詠むだけでなく、醜さや残酷さをもそのまま描く姿勢が誓子の大きな特徴です。

そして季節の中に潜む真実を見つめた誓子の俳句は、現代にも新鮮な響きを与えてくれます。
山口誓子の秋の俳句5選

「意味」はわたぼうしの意訳なので、解釈の仕方は参考程度に読んでね!
『秋の雲 はてなき瑠璃の 天をゆく』

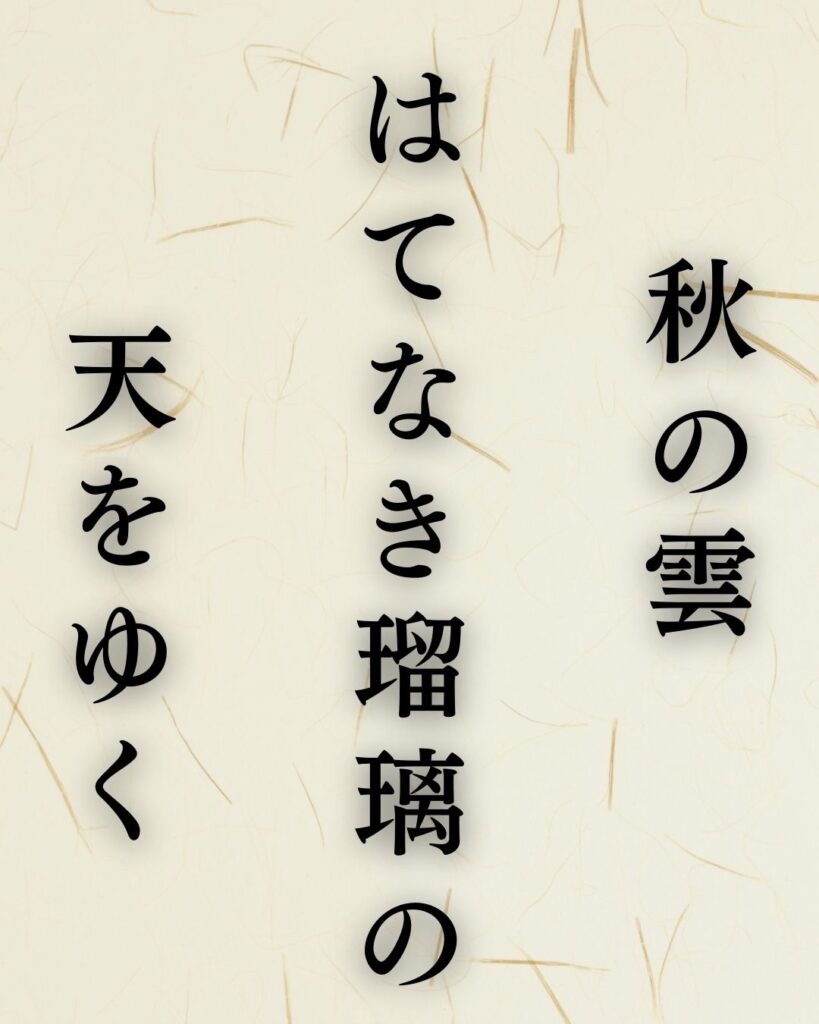
秋の雲 はてなき瑠璃の 天をゆく
読み方:あきのくも はてなきるりの てんをゆく
季語:秋の雲(あきのくも)
句意:この句では、秋の雲が瑠璃色の果てなき天空を悠々と流れていく情景が詠まれています。

つまりこの俳句は、秋の雲が瑠璃色の天を悠々と進む様子を鮮やかに描いています。

また、無限の空の広がりと雲のゆるやかな動きが、読者に静かな感動を与える点がポイントです。
天空の深い蒼と雲の白さの対比が、自然の雄大さを際立たせ、詩情を豊かにしています。
『秋の田の 只中石の 鳥居暮る』

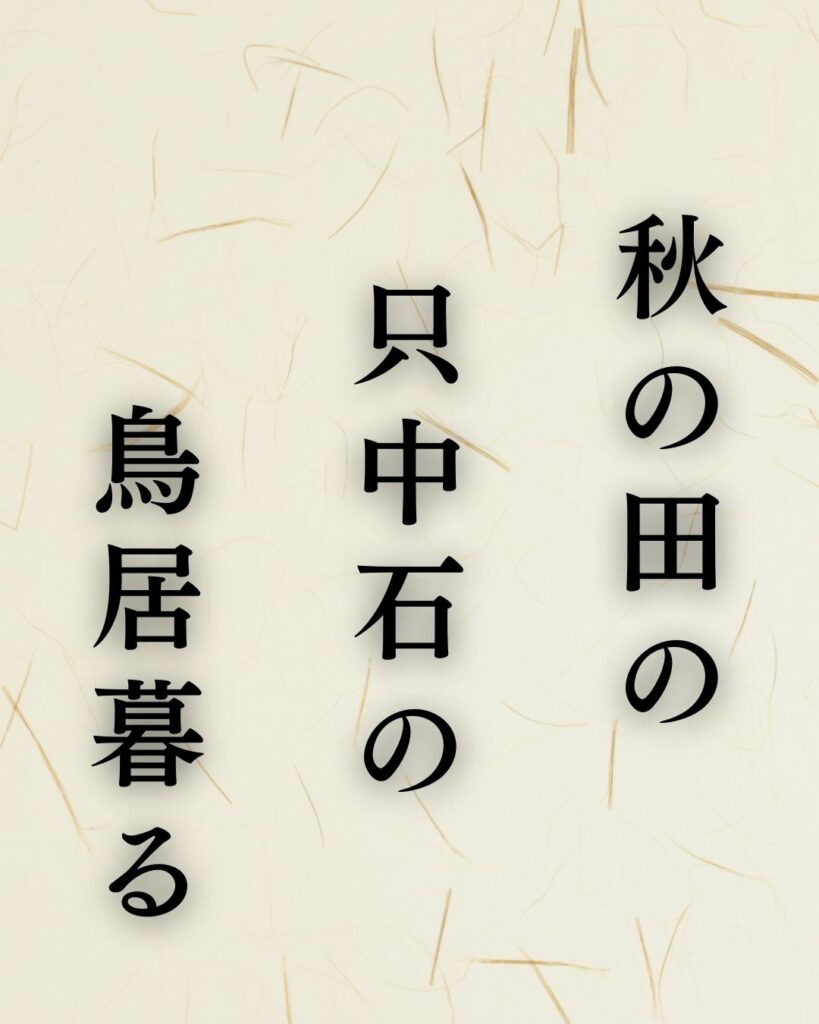
秋の田の 只中石の 鳥居暮る
読み方:あきのたの ただなかいしの とりいくる
季語:秋の田(あきのた)
句意:この句では、秋の田の中央に立つ石の鳥居が夕暮れに沈みゆく光景が詠まれています。

つまりこの俳句は、秋の田の只中に立つ石の鳥居を夕暮れに重ねて描いています。

また、田園の静けさと信仰の象徴である鳥居が一体となる点がポイントです。
秋の黄昏に映える鳥居の姿は、自然と人の祈りが溶け合うような余情を生み、詩情を豊かにしています。
『秋風に 歯牙なき口の ひた泣ける』

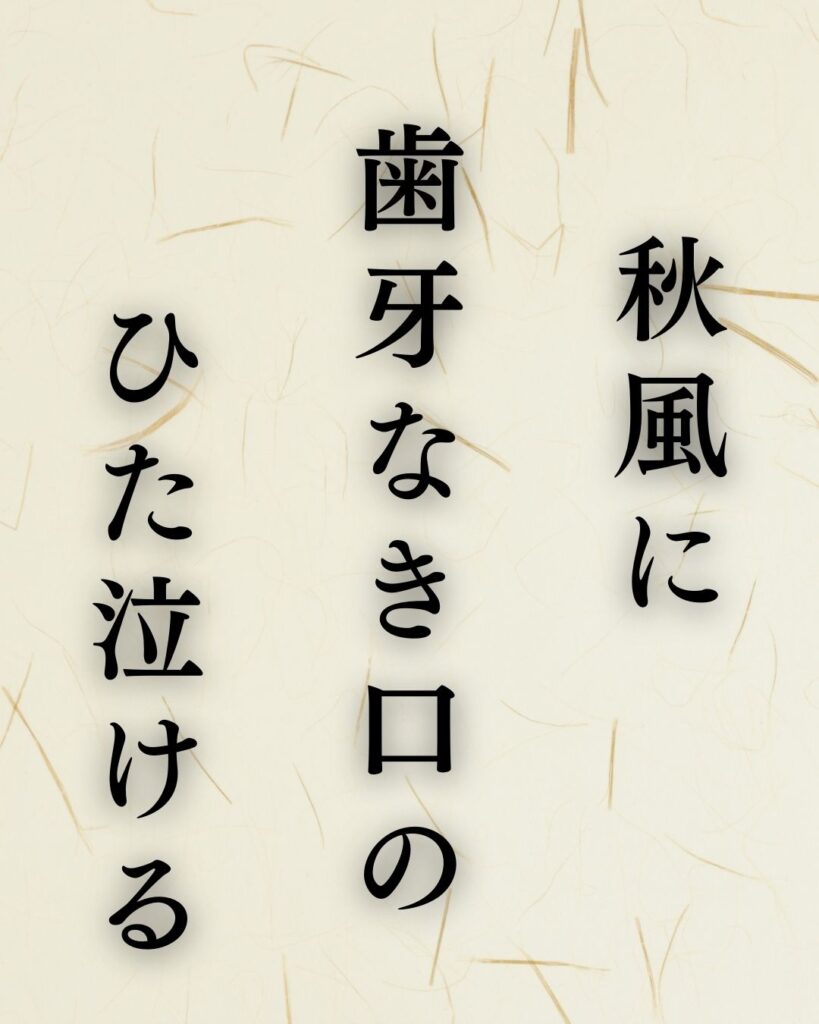
秋風に 歯牙なき口の ひた泣ける
読み方:あきかぜに しがなきくちの ひたなける
季語:秋風(あきかぜ)
句意:この句では、秋風に吹かれて歯のない口がひたすら泣き続ける姿が詠まれています。

つまりこの俳句は、秋風に吹かれる中で、歯を失った口が泣き続ける様子を生々しく描いています。

また、老いや無力感の象徴としての表現が、冷たい秋風と重なり合う点がポイントです。
人間の弱さと自然の厳しさを対比させることで、句全体に強烈な余情と詩情を生み出しています。
『鶏頭の 矮醜なるに ちかづきゆく』

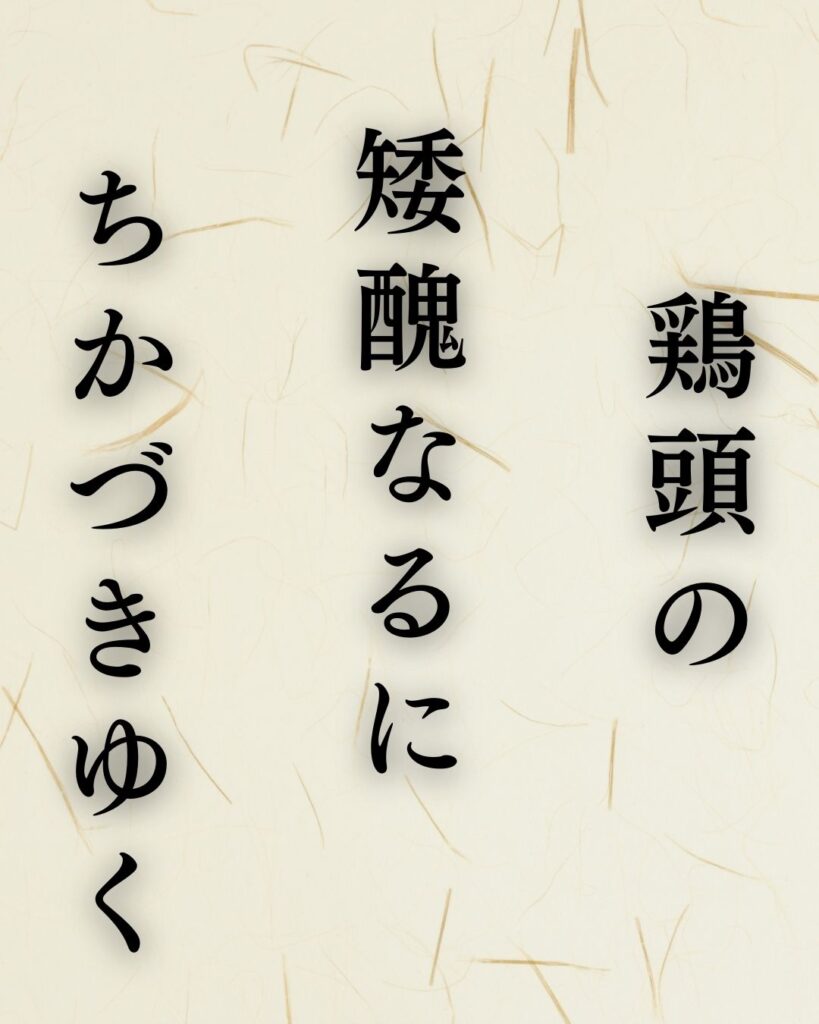
鶏頭の 矮醜なるに ちかづきゆく
読み方:けいとうの わいしゅうなるに ちかづきゆく
季語:鶏頭(けいとう)
句意:この句では、矮小で醜い姿をした鶏頭の花に近づいていく様子が詠まれています。

つまりこの俳句は、鶏頭の花の矮小で醜い姿に焦点を当て、自然を直視する眼差しを示しています。

また、美醜を超えた存在感に迫る姿勢がポイントです。
対象を飾らず観察することで、自然の持つ異様さと生命力を鮮烈に描き出し、詩情を新たな次元へと広げています。
『かりかりと 蟷螂蜂の 皃(かほ)を食む』

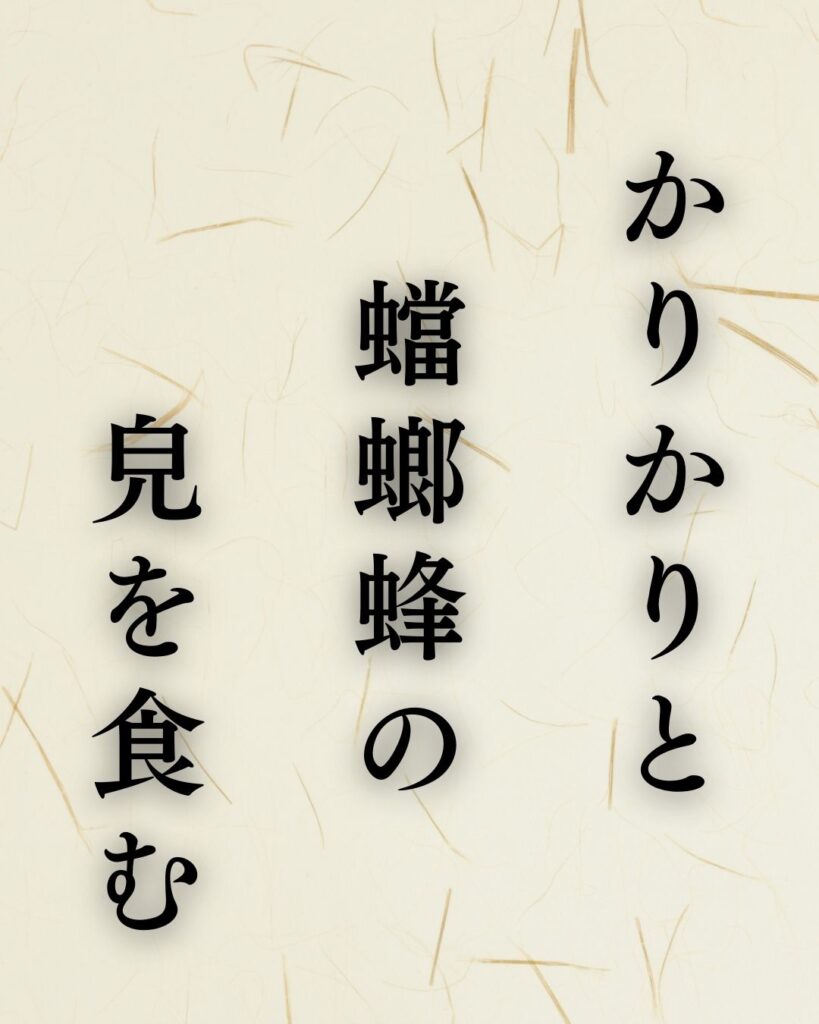
かりかりと 蟷螂蜂の 皃(かほ)を食む
読み方:かりかりと かまきりはちの かほをはむ
季語:蟷螂(かまきり)
句意:この句では、蟷螂が蜂の顔をかりかりと噛み砕いて食べている様子が詠まれています。

つまりこの俳句は、蟷螂が蜂の顔を食む瞬間を克明に切り取っています。

また、「かりかり」という音の写実が、残酷さと生々しさを強調している点がポイントです。
美を避け、命の争いを直視することで、自然の実相を突きつけ、そして強烈な詩的迫力を生み出しています。
山口誓子の俳句ちょっとむずかしいクイズ
クイズ:山口誓子が活躍した時代は?
- 江戸時代
- 明治時代
- 昭和時代
▶秋と冬の誓子句も気になる方へ——
イラストでやさしく味わえる名句を紹介した、
以下の記事もぜひご覧ください。
山口誓子の秋の俳句5選まとめ
山口誓子の俳句は、
自然を鋭くとらえる観察眼と、
人間の生や感情を映す視線が
際立っています。

この記事「山口誓子の秋の俳句5選-代表作をわかりやすく解説!」では、誓子の秋の俳句を5つ厳選し、初心者の方にもわかりやすく解説しました。

誓子の俳句を通して、秋という季節の奥深い表情を味わっていただけたら幸いです。
クイズの答え:3.昭和時代