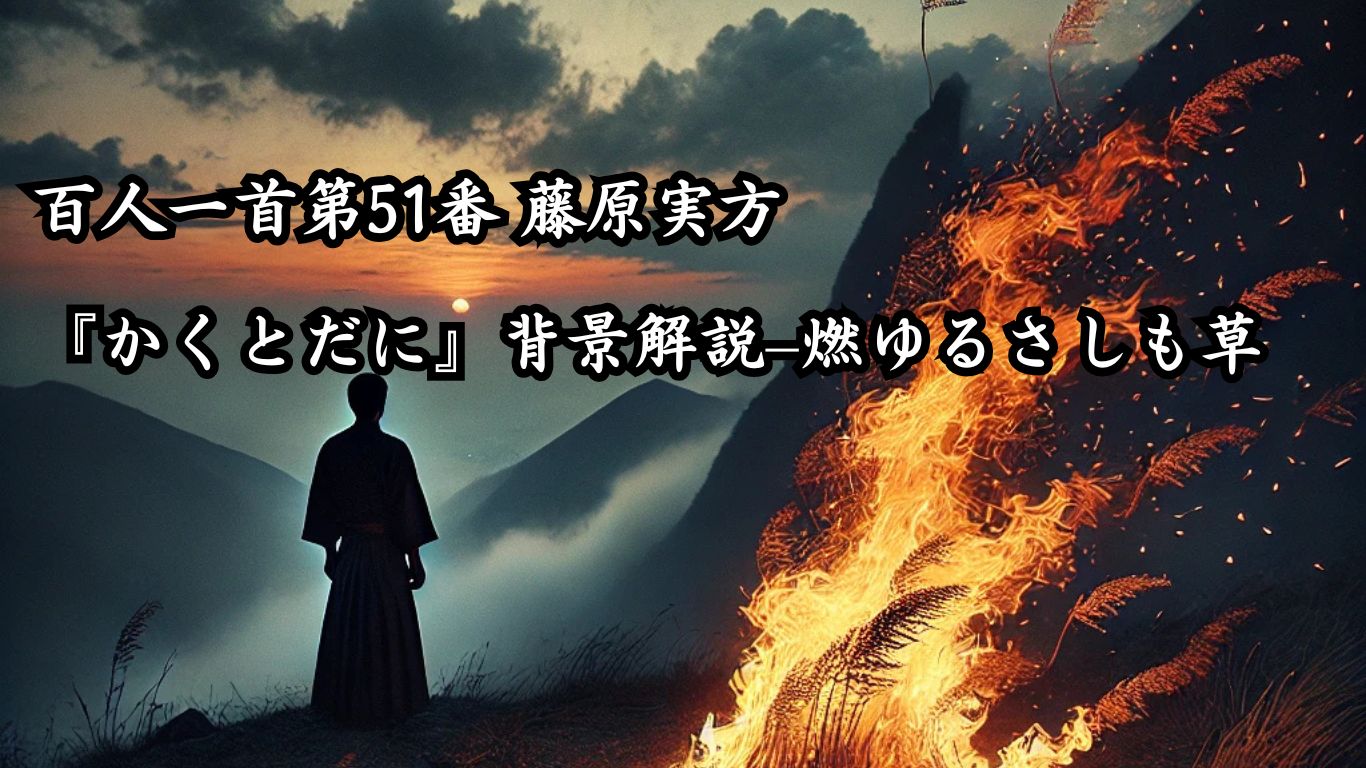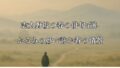百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』背景解説で、
和歌の世界を旅してみませんか?
第51番は、藤原実方が詠んだ、
言葉にできぬ恋の炎が静かに燃え続ける情熱の一首です。
恋の苦しさや想いの強さを、
伊吹山の“さしも草”にたとえながら、
相手に知られぬまま募る切なさがにじみます。
今回ご紹介するのは、百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』。伝えられぬ恋ゆえの葛藤と、沈黙の奥に燃える想いを、あなたも感じてみませんか?
▶前回の記事はこちらから!
前回は、命までも恋にゆだねた藤原義孝の一首をたどりました。若き情熱の中に、燃えるような恋の純粋さを感じます。
藤原実方の生涯と百人一首の背景
生涯について

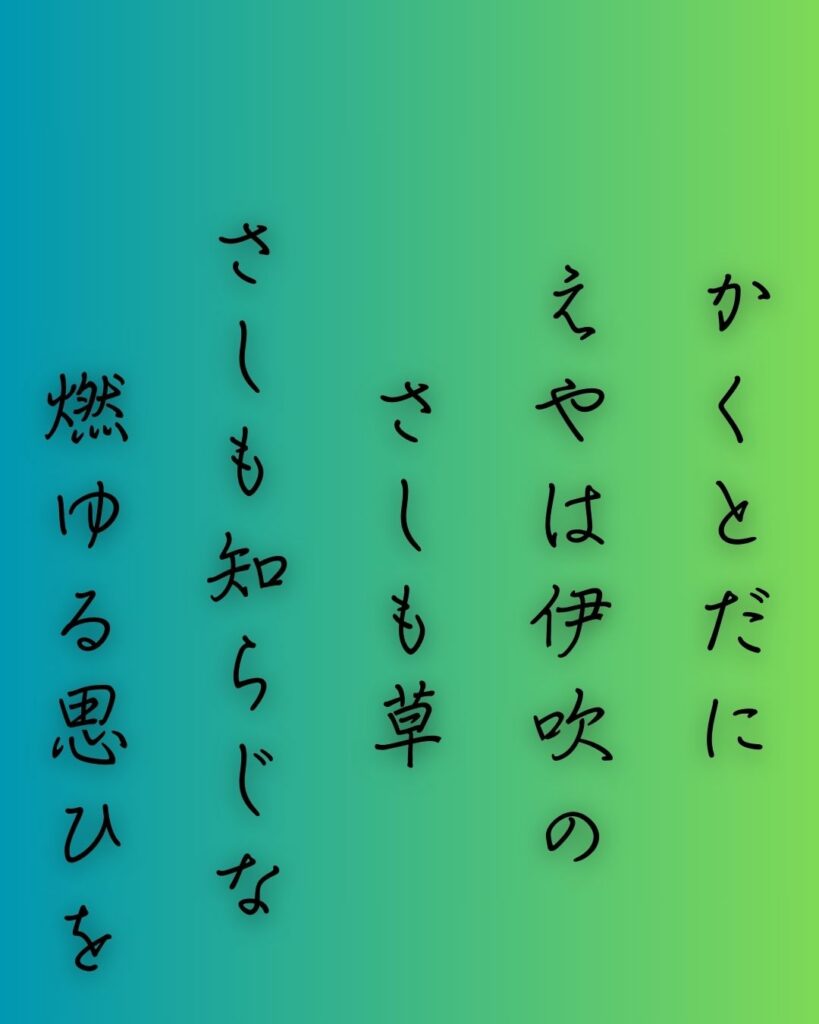
藤原実方– Wikipedia(生年不詳-999年)は、
平安時代中期の貴族・歌人であり、
左大臣・藤原師尹の孫、侍従・藤原定時の子
として生まれました。
また父の早世により、叔父である
大納言・藤原済時の養子となります。

そして右兵衛権佐・左近衛少将・右近衛中将などの武官を歴任し、正暦5年(994年)には左近衛中将に任じられ、公卿の座を目前にしていました。

しかし、長徳元年(995年)正月に突然陸奥守に任じられ、同年9月に陸奥国へ赴任しました。長徳4年(999年)に陸奥国で亡くなったとされています。
歴史的イベント
藤原実方は、
花山天皇の側近として重用されましたが、
一条天皇の時代に突然陸奥守へ左遷されます。
その理由には、宮中での言動や
藤原行成との対立など諸説があります。
赴任先の陸奥国で不遇のまま亡くなり、
その死には不吉な伝説も伴いました。

都の文化人として栄えた実方の、地方での孤独な最期は、彼の和歌の哀愁とも重なります。
他の歌について
藤原実方は『拾遺和歌集』に、
「五月闇くらはし山の時鳥 おぼつかなくも鳴き渡るかな」
という歌を残しています。
闇深き初夏の山中に、時鳥の声だけが頼りなく響くさまを
詠んだ一首です。
実方の歌には、自然の景と内面の情がしなやかに融合する美が宿っています。

“おぼつかなくも”という語に、聞こえるか聞こえないかの不確かさと、自身の心の迷いや孤独が重なります。

実方の歌には、自然の景と内面の情がしなやかに融合する美が宿っています。
百人一首における位置付け
『かくとだに』は、思いを伝えることもできないまま、
恋の情熱だけが内に燃え続ける苦しさを詠んだ一首です。
実方の繊細で抑えた表現は、
百人一首の恋の歌群の中でも、
内面の静かな激しさを最も端的に表した歌として
高く評価されています。
藤原実方がなぜこの和歌を詠んだのか?
百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』背景解説–燃ゆるさしも草では、藤原実方がなぜこの和歌を詠んだのか?についてポイントを3つに分けてみました。
- 思いを伝えられない恋の苦しみ
- 自分だけが知る想いの激しさ
- 恋の情熱と表現の美学
思いを伝えられない恋の苦しみ
恋の炎が燃えているのに、
それを言葉にするすべもない状況。
また実方は、沈黙するしかない恋のもどかしさを
「かくとだに」という冒頭で表現し、
そして恋心の行き場のなさを詠みました。
自分だけが知る想いの激しさ
「さしも知らじな」という言葉では、
相手には想像もつかないほどの思いが、
自分の中で燃え盛っているという
切実さが込められています。
また独りで抱え続ける恋の熱を、
実方は比喩を通じて描いたのです。
恋の情熱と表現の美学
実方は、直接的な告白ではなく、
自然物や比喩で恋を語る和歌の美学を体現しています。
「さしも草」では、そのまま恋の象徴としての草であり、
また静かに燃える炎のメタファーでもあるのです。

この和歌では、恋する相手に思いを告げることすらかなわない、沈黙と内なる炎の狭間で揺れる心を描いています。

また実方は、その苦しみや願いを、伊吹山に生える“さしも草”にたとえることで、情熱を秘めながらも抑制された表現を成立させました。
“言えない恋”というテーマを、比喩と調べの美しさを通して詠み上げた、恋歌の傑作と言えるでしょう。
読み方と句意
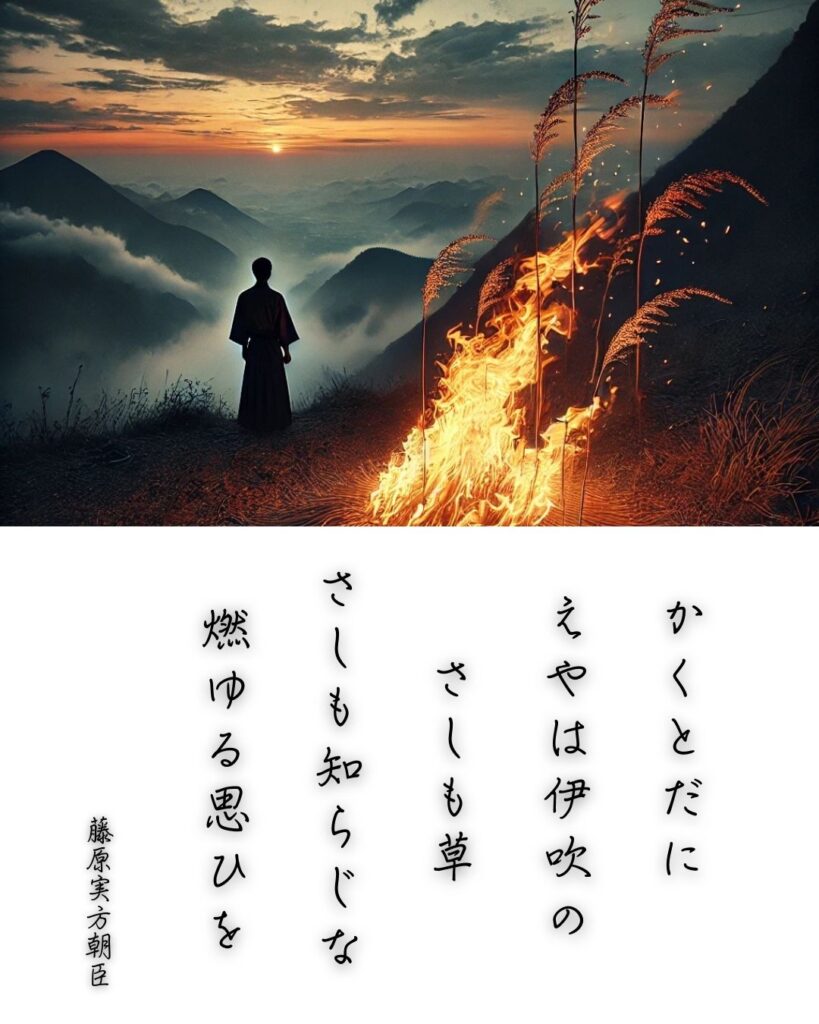
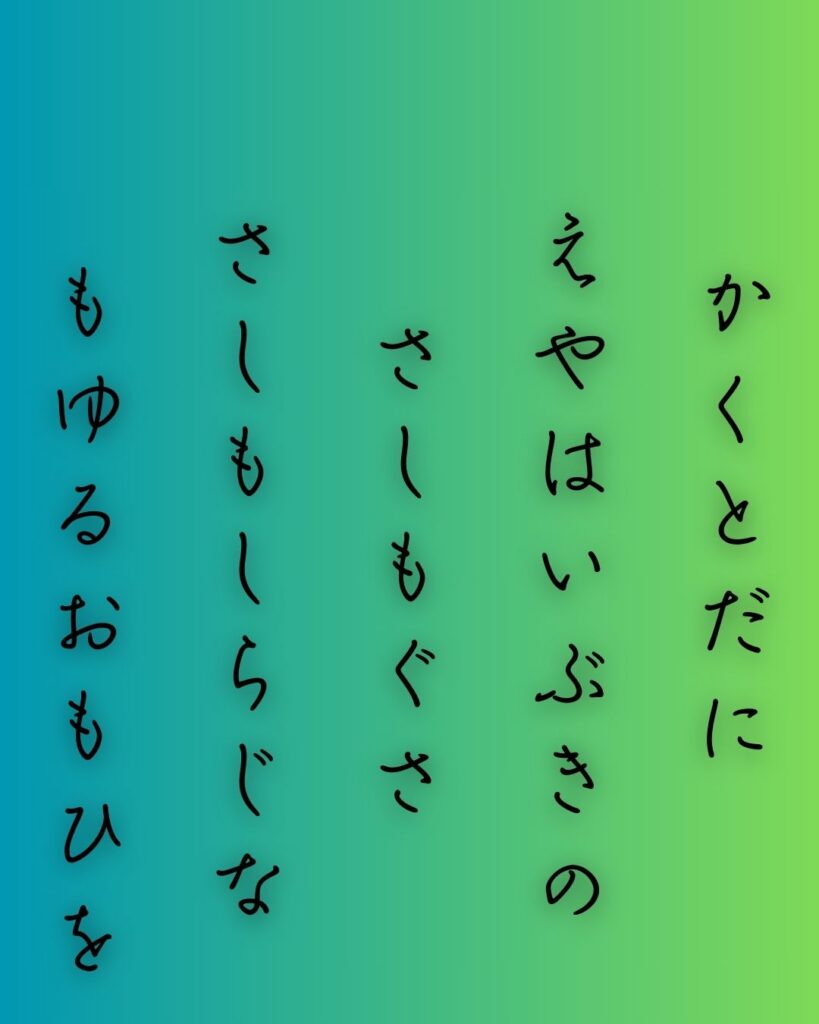
百人一首第 藤原実方
歌:かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを
読み:かくとだに えやはいぶきの さしもぐさ さしもしらじな もゆるおもひを
句意:せめて「好きです」と伝えることさえできずにいるが、あなたは私の燃えるような恋心を知りもしないのでしょうね。
百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』の楽しみ方
百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』背景解説–燃ゆるさしも草では、この和歌の楽しみ方のポイントをこの3つに分けてみました。
- 比喩表現に注目する
- 言えない想いの強さを感じる
- 読み手が共感しやすい感情描写
比喩表現に注目する
「さしも草」「燃ゆる思ひ」は、
恋の炎を草にたとえた巧みな比喩です。
植物の燃え方=感情の高まりとして描くことで、直接的に言えない恋心を美しくも切なく表現しています。また比喩を読み解く楽しさと、そこに込められた感情の深みが味わえます。
言えない想いの強さを感じる
「かくとだに」「えやは」は、
語ることすらできないという抑えた情熱を語る表現です。
この歌の魅力は、語らないことによって逆に情熱が強調されている点にあります。また静けさの中に激しく燃える恋心が読み取れる、深い余韻の一首です。
読み手が共感しやすい感情描写
片想いや届かぬ想いという主題は、
現代の私たちにも通じる普遍的な感情です。
「伝えたいけれど言えない」「相手には知られていない」といった感覚は、時代を超えて共感を呼ぶものです。また恋愛の中にある“言葉にならない想い”を、実方の和歌を通して感じてみてください。
百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』背景解説
上の句(5-7-5)
上の句「かくとだに えやは伊吹の さしも草」では、
「恋をしている」とさえ言えないもどかしさと、
その想いを象徴する「さしも草」の比喩が登場します。
また伊吹山のさしも草は燃えやすい草で、
言葉にできぬ恋が、胸の奥で静かに燃えている情景を
美しく切なく描いています。
五音句の情景と意味 「かくとだに」

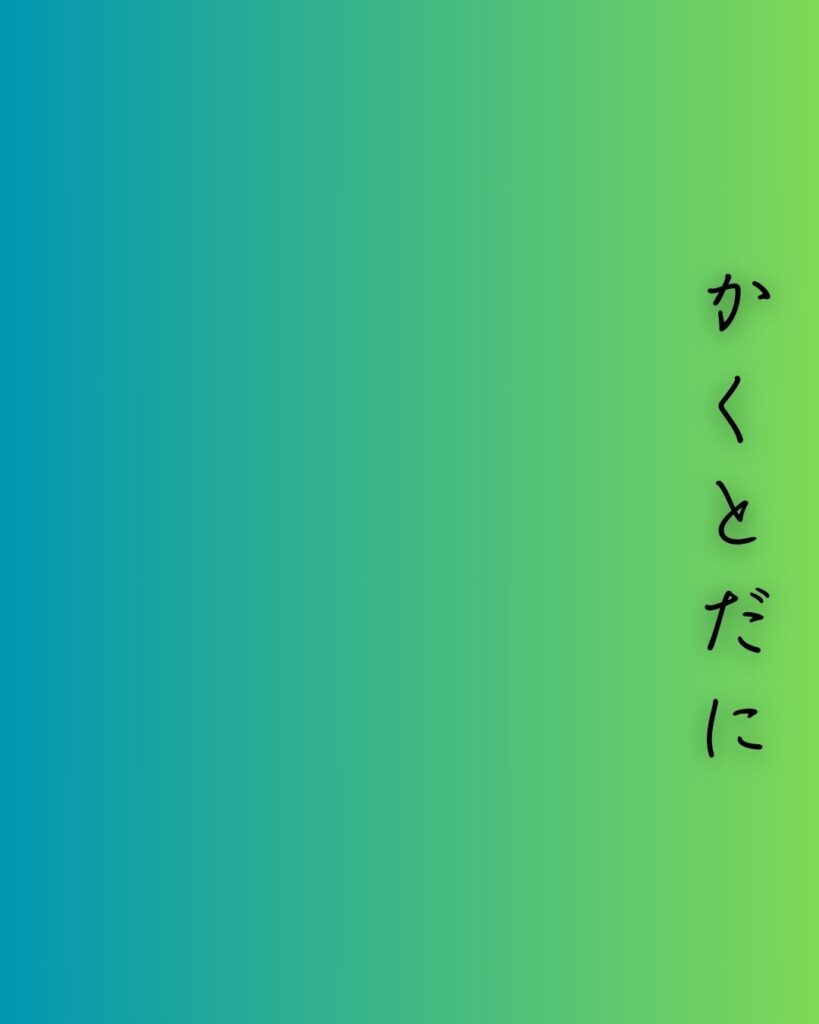
「かくとだに」では、「こうだ」と打ち明けることさえできず、思いを口にできない切なさが、この一語に込められています。
七音句の情景と意味 「えやは伊吹の」

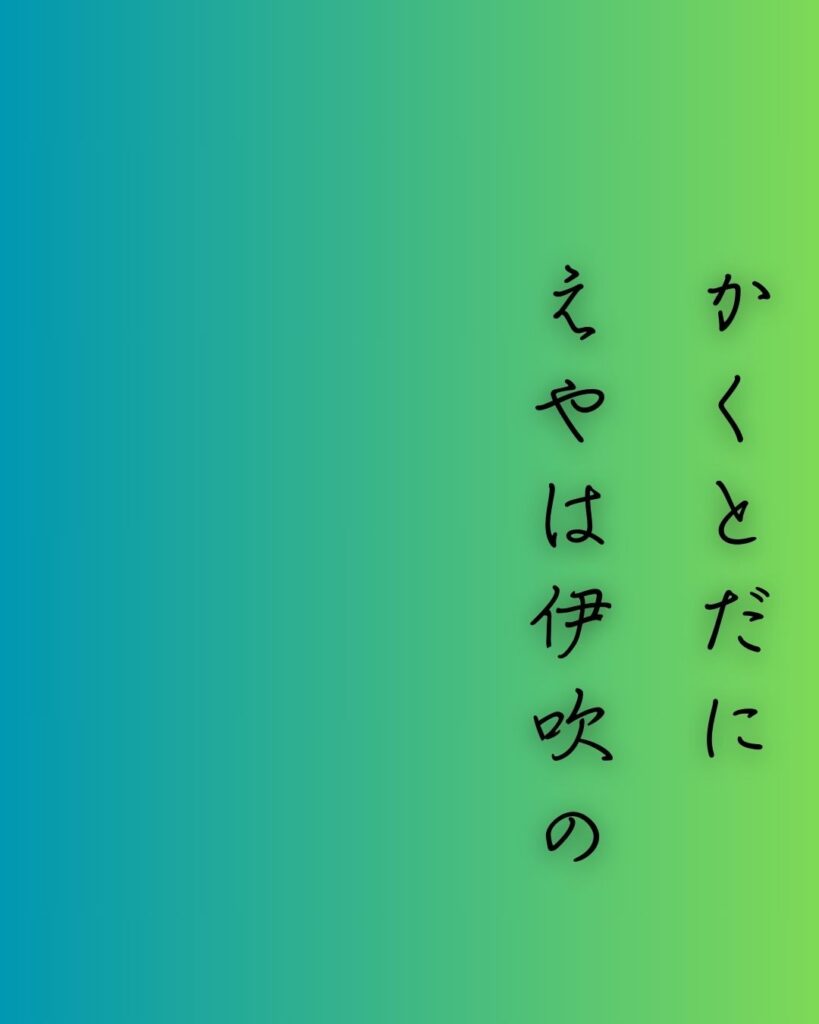
「えやは伊吹の」では、「えやは」は反語で、「できようか、いやできない」。伊吹山のさしも草に例え、恋心を伝えられない苦しさを印象的に描いています。
五音句の情景と意味 「さしも草」

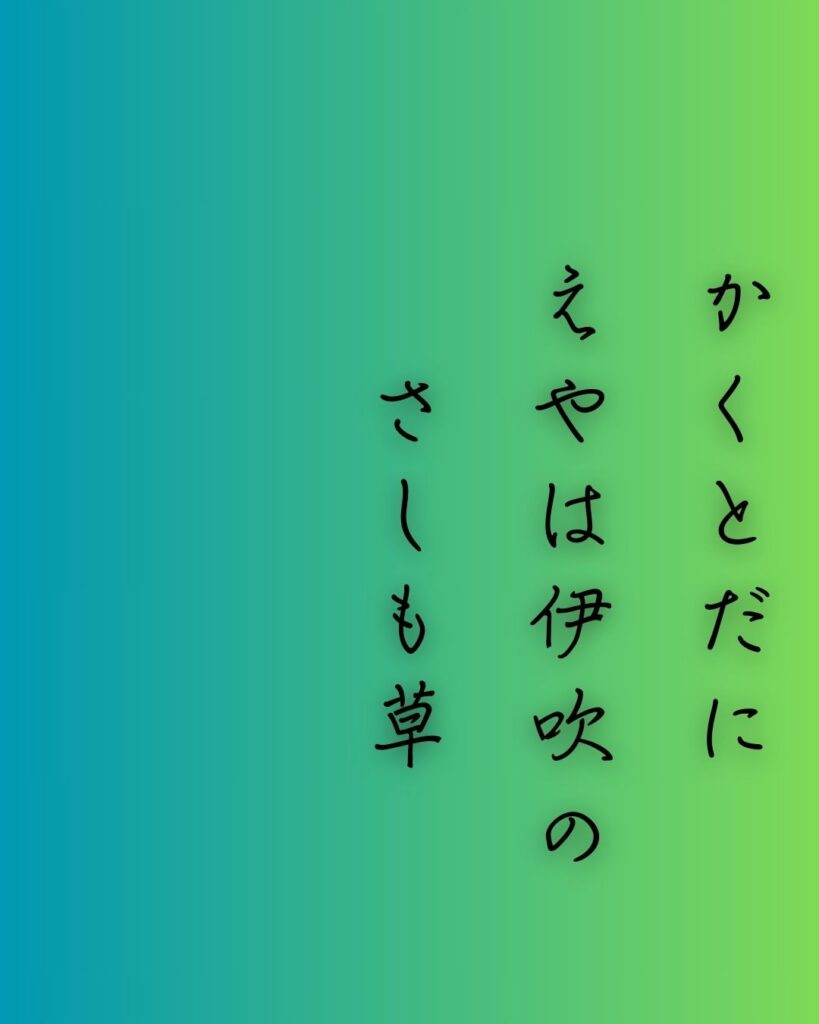
「さしも草」では、伊吹山に生える、火をつければすぐに燃える草。燃え盛る想いを秘めながらも、気づかれない恋心の象徴です。
下の句(7-7)分析
下の句「さしも知らじな 燃ゆる思ひを」では、
恋心が燃え続けているのに、
その相手はまったく気づいていないという
切なさが語られます。
また「さしも草」が燃えるように、
内に秘めた激しい想いがありながら、
それは相手に知られず、報われることもない。
まさに沈黙の恋の苦しみがにじむ一節です。
七音句の情景と意味「さしも知らじな」

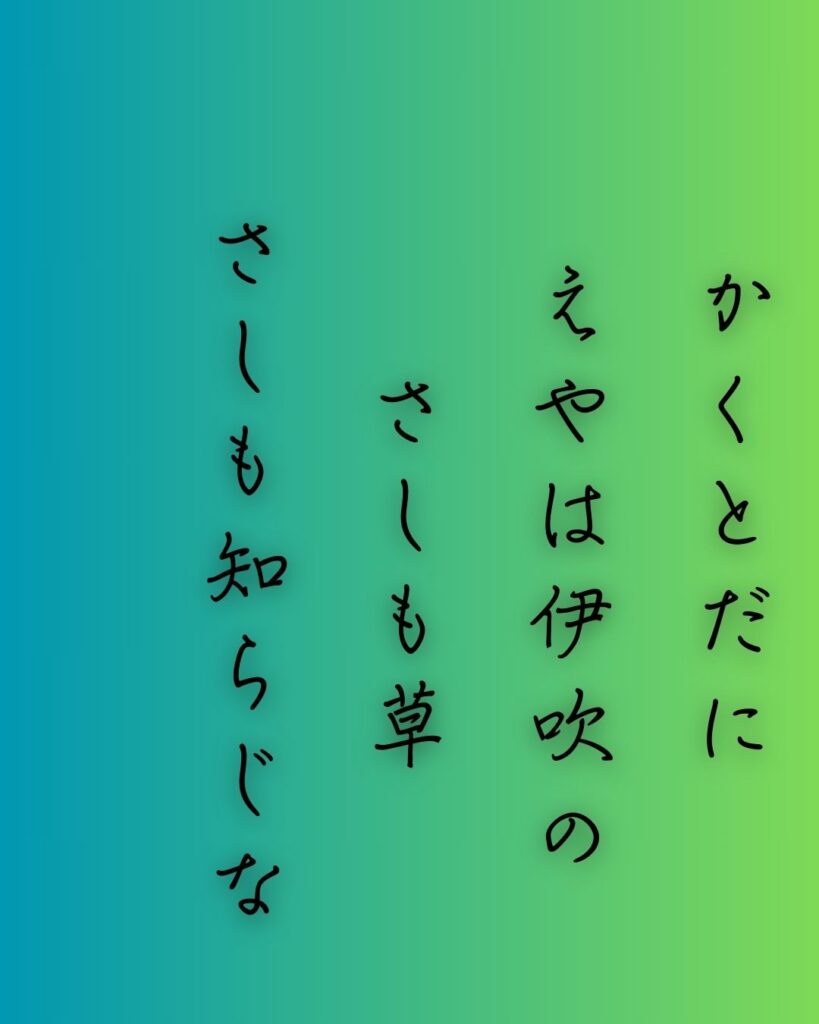
「さしも知らじな」では、あれほど強い恋心も、相手にはまったく気づかれていない。またその事実にこそ、悲しみが潜んでいます。
七音句の情景と意味「燃ゆる思ひを」

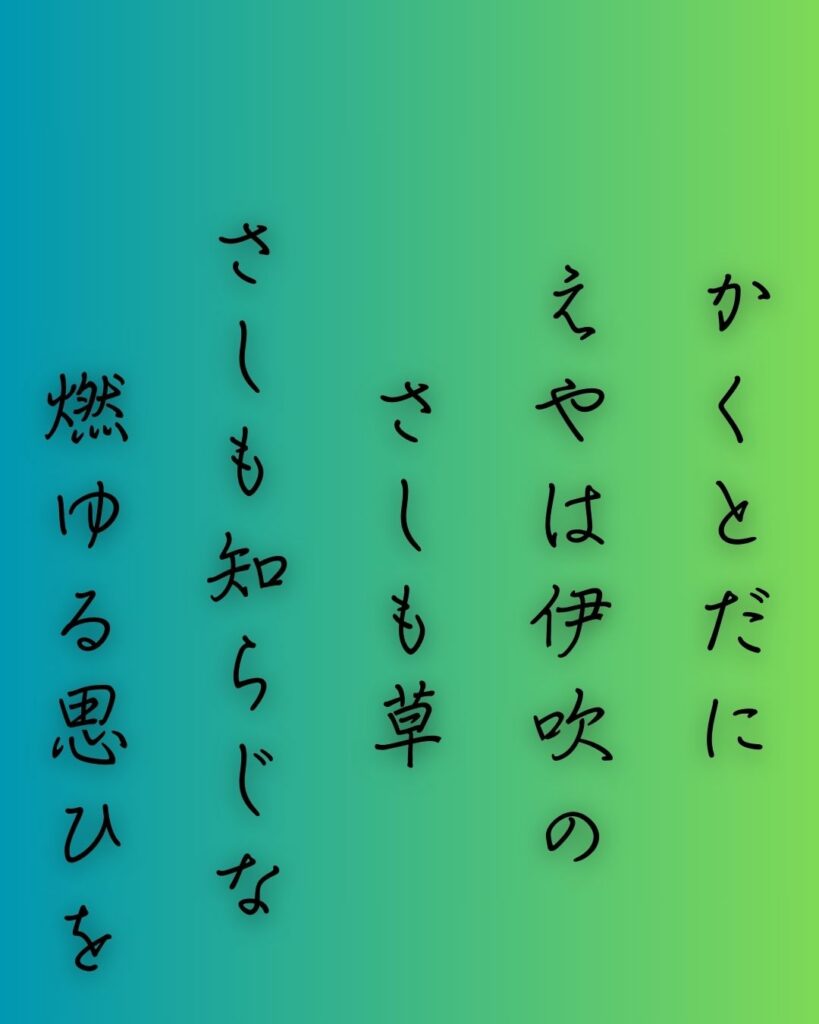
「燃ゆる思ひを」では、伝えられず、表にも出せない。心の奥で激しく燃え続ける恋心が、静かに、しかし確かに描かれています。
百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』和歌全体の情景
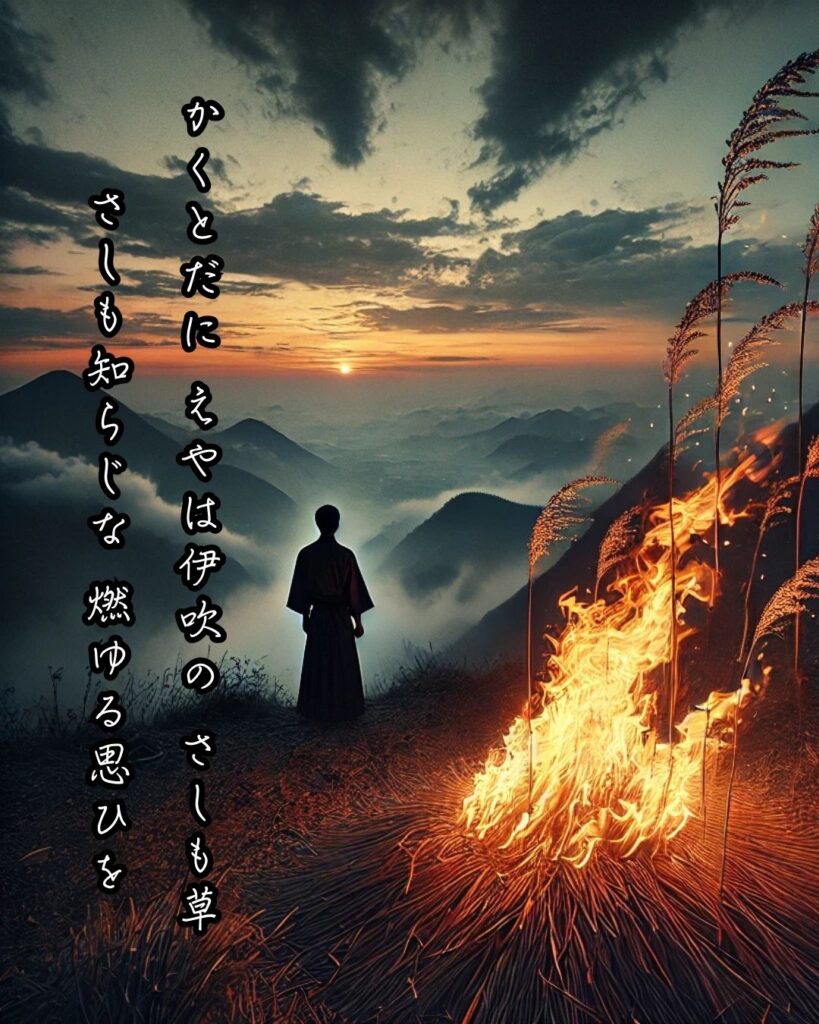
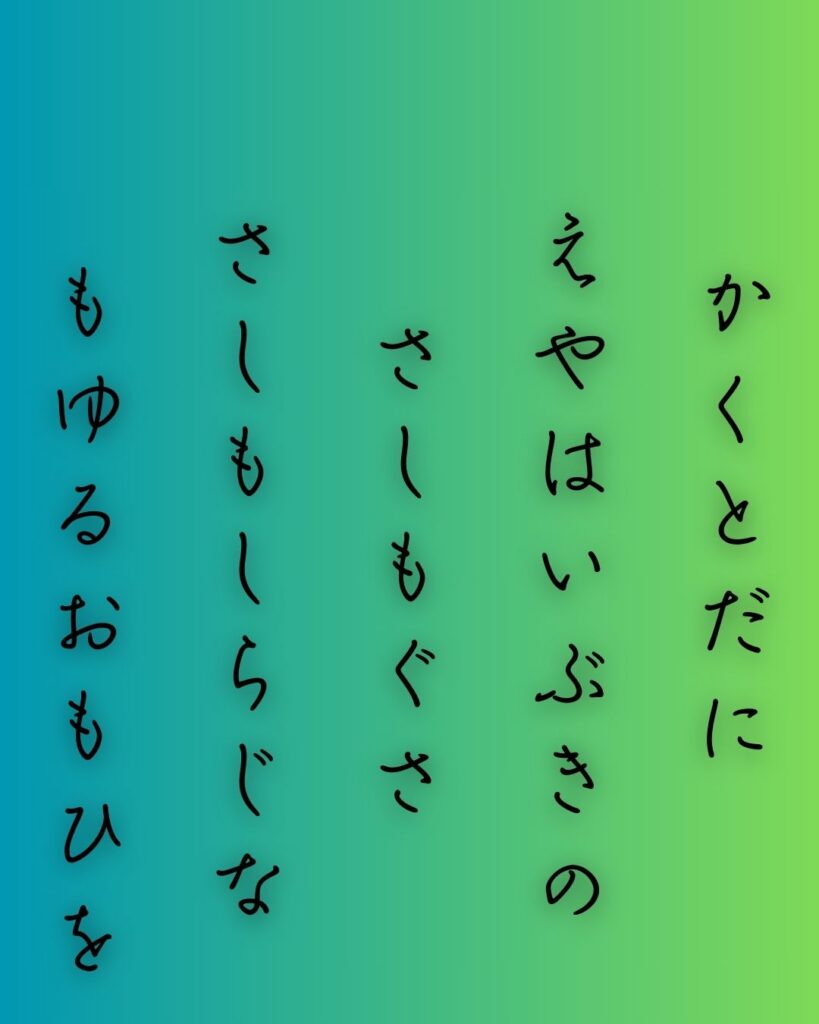
和歌全体では、恋の想いを打ち明けることすらできず、胸の内でただ静かに燃え続ける情熱。また伊吹山に生える“さしも草”のように、その火は絶え間なく心を焦がしているのに、相手には一切知られていない。そして伝えられない苦しさと、伝わらない切なさが交差する、沈黙の恋の情景が広がります。
▶次回記事はこちらから!
言葉にできぬ想いを胸に燃やした藤原実方の歌をたどったあとは、夜明けを惜しみながら別れを見つめる、藤原道信の切ない一首へと進みましょう。
👉百人一首第52番 藤原道信『明けぬれば』背景解説–惜しむ朝の恋心
百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』まとめ
藤原実方の『かくとだに』は、
伝えられない恋の苦しさと、
心の奥で燃え続ける情熱を、
見事な比喩で表現した一首です。
そして「さしも草」のように、
激しくも秘めた想いは、
平安の恋歌の中でもひときわ切なく響きます。

語らぬ愛の深さが、今も読む人の胸を焦がす名歌です。

百人一首第51番 藤原実方『かくとだに』背景解説–燃ゆるさしも草を百人一首の第一歩として、この和歌を味わうことで、和歌の魅力を発見してみてください。